現在、軽井沢風越学園の僕の仕事の一つが、同僚のKAIさんと一緒に来年度の国語科のカリキュラムを考えること。基本方針は「たくさん読み、たくさん書く」、つまり授業形態としてはリーディング・ワークショップやライティング・ワークショップを軸に据えることは決め、ミニレッスンを作っているのだけど、作っているうちに、自分のミニレッスンプランに対して「これじゃない」感が強まってきた。いま、自分が考えているのは「小学校のライティング・ワークショップでは何を「教える」べきなのか?」ということ。今日はその問題について、エントリをたてて整理してみる。
こんなに違う!小学生と中高生
僕はいま、週1回地元の公立小の授業に参加させてもらい、放課後は週2回「風越こらぼ」という地元の小学生向けの教室で「作家の時間」を担当させてもらっている。そこで小学生と接して、「こんなに中高生と違うのか」と驚かされることが度々ある。
まず驚いたのは、彼らが何のためらいもなく「見て見て!」と作品を見せに来ること。僕がこれまで相手にしていた中高生は、基本的には自分の作品を人に見せることに臆病だ。作品を見られたくないと隠すこともあるし、言い訳や自己卑下とともに見せることもある。そうでなくても、ちょっと恥ずかしそう。誰しも、自分の作品に対する他人の視線は気になるもの。臆病になって当然なので、だからこそ僕も「共有しない権利」をことさらに強調してきた。ところが、小学生たちは「見せる」ことに対するネガティブな姿勢がほとんどない。多くの子が読んでもらいたがる。これは本当に驚きだった。
そして、小学生は書く前のプランニングをしない。中高生なら事前にある程度展開を考えてから書くところを、彼らはすぐに書き始める。物語を書いている子に「この後はどうなるの?」と聞くと「まだ考えてない」と屈託無い笑顔で答える。同様に、「自分の作品の質をあげたい」欲望も乏しそうだ。書いたら、見直しも推敲もしないで、それでおしまい。ここがちょっとわかりにくいかなというところにコメントをしても、さして感じる様子もなく、ふーん程度で流されてしまう。中高生は素直にこちらの助言にしたがって改善する子のほうが圧倒的に多いので、これも面白いなあと思っていた。
おそらく、これらは同根の現象なのだ。子供たちは、書いた結果としての作品の質よりも、書くこと自体を楽しむ。読んで、その楽しさを共有して肯定してもらえたら、それで満足。だからこそ書くことへのハードルが低いし、思いつきで書くし、書いたものを見せるのにも屈託がない。その一方で、見通しを持って書くことはないし、書いた結果としての作品の質を向上させようという思いにも乏しい。
以前に、書くことの発達段階についての論文を読んで、「小学生の間までは読者意識を持つことは難しく、自分の思っていることをただ書くだけ」と書いたことがあったのだが、目の前に生きた小学生を前にして「まさに!」という感じである。
小学生ってどんな子たち? 同僚との話から
さて、僕が考えてしまったのは、こういう子たちを相手に、ミニレッスンで何を「教える」べきなのだろうかということ。僕はどうしてもレトリック(表現の技術)に焦点を当てて教える傾向が強いのだが、自分のミニレッスンプランを「風越こらぼ」で子どもに試してみても、そのやり方だとしっくりこない。彼らにはやや背伸びすぎ、求められていないものを与えている感じがする。
ここでもヒントになったのは同僚とのやりとり。小学校でずっとライティング・ワークショップを実践してきたKAIさんとは、一度、開校以降の利用を視野にお互いのミニレッスン案を持ち寄ったことがあった。僕が詩を用いてレトリックを学ぶためのミニレッスンを多く用意したところ、KAIさんの用意していたミニレッスンは、ほとんどが「意欲を持たせ、励ます」系のミニレッスンだったのである。この違いは、まさにお互いのこれまでの道の違いを象徴している。確かに、もしも作品の質を高めようとする気持ちをまだ子どもが持っていないのなら、レトリックよりも「励まし」系のミニレッスンが多くなるのは納得がいく。
また、いまや同僚になった、下記エントリの図工のKさんとの会話や、図工の学習指導要領も非常に参考になった。
それによると、小学校中学年くらいまでの子どもは、見通しを持って活動するというよりも、まだ目の前の材料に触れて「いいこと考えた!」と思いつきで発想を広げて動く段階。そして、すぐにファンタジーの世界に入れてしまうことが強みでもある。そういう子たちには、Kさんは無理に技術を教えず、材に触れてたくさん遊ぶ経験を大事にするのだそうだ。しかし、そんな子達も高学年になると、客観性も身につけ、見通しを持って活動し、「もっと上手くやりたい」という子も増えてくる。一人一人の「うまく作りたいタイミング」を捉えて技術を教えるのが自分の仕事だ、とKさんは言う。
作文教育でも同じなのだろう。小学生の多くは、まだ「客観性」や「見通し」を持つ段階ではない。したがって、技術への欲求も弱い。その代わりに、ためらいもなく文章を書き始め、その中で色々な発想を持って作品を作ることそのものを楽しむ。そういう時期の子たちには、無理に「大人と同じ書き方」を教えるよりも、その時期の強みを生かしたことを教えた方が良いはずだ。
こんな風にしてみようかな…?現段階の考え
以下は、その問いに対する現段階の仮説的な考え。幼児から小学校低学年では、とにかくたくさんの読み聞かせをして、そこから一人読みに進めることを重視する。まずはたっぷり読んで、物語の世界にひたること。低学年のうちに、自分の好きな本が選べるようになるといい。文字を認識したり書いたりは、発達の個人差もあるので、焦らないで、まずは耳と絵の助けを借りて、たっぷり言葉と物語にひたる。
この時期のライティング・ワークショップでは、遊び要素を取り入れたミニレッスンをしたり、詩を楽しく読んだりして、書くことを楽しむ姿勢や、言葉に対する敏感な意識を育てる。この時のミニレッスンは、文章表現の技術というより、書くことを楽しくする仕掛けを教えるもの。中学年頃までは、質よりも、とにかくたくさん読み書きをして、遊びながら言葉を操作する経験を積む。この、遊びの中で言葉を操作する体験が、のちに自分の言葉を操作すること、つまり推敲することの土台になるのではないか。その上で、小学校高学年くらいから文章を書く具体的な技術を手渡していけばいいのではないか。
同様に、カンファランスでの子どもへの言葉がけも、年齢に応じて変わっていきそうだ。「上手く書きたい」意欲がまだ育っていない子に改善点を指摘しても効率が悪い。そんな子どもに必要なのは、その子の書きたいことや苦労したことを捉えた「面白いね!」「頑張ったね!」の一言だ。そうやって励ます中で、その子の作品の良いところを指摘して、「良さ」の引き出しを増やす。そうして、やがて自分の作品をちょっと距離を置いて眺めることができるようになったところで、「こうするともっと良くなるよ」という技術を手渡す。こんなイメージでいれば良いのかなと思う。
以上はあくまで仮説だし、これからさらに変わっていくかもしれない。でも、ひとまずはこんな見通しを持って進んでみよう。






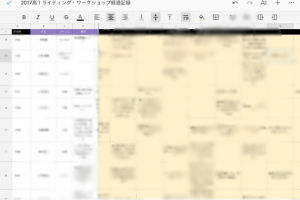











![[ITM]授業中に「書く時間」を確保する意味](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/511NgcY9IsL._SL160_-6-50x50.jpg)
![[ITM] アトウェルが批判するもの(2)](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/511NgcY9IsL._SL160_-9-50x50.jpg)