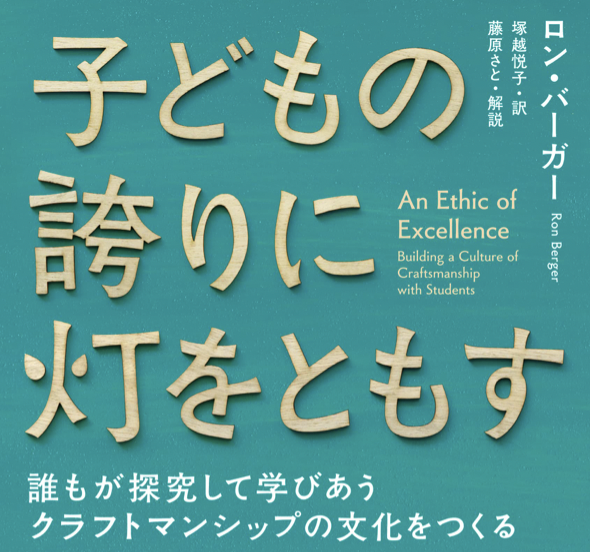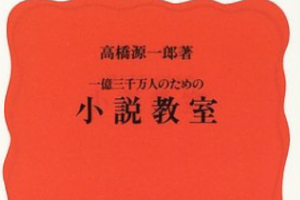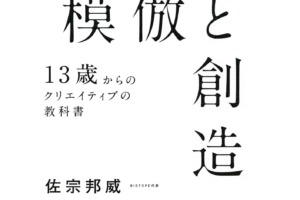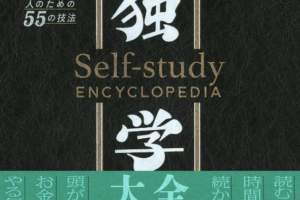ロン・バーガー『子どもの誇りに灯をともす』(原題An Ethic of Excellence)は、卓越した美しい作品をつくり上げる姿勢=「クラフトマンシップ」の文化を中核においた学校づくりの本である。まず言っておくと、これはとても素晴らしい本だ。書かれている子どもたちの物語(エピソード)も、それを支える授業の具体的な方法も、そこに一貫して流れる著者ロン・バーガーの思想も、『子どもの誇りに灯をともす』という邦訳も。
ただ、読書した時に感じる「素晴らしさ」は、読み手の固有の文脈と切り離して語ることはできないし、むしろ個々の内面に切り込み、揺さぶることこそがその本の良さの証明であるようにも思える。だから、このブログでは僕の固有の文脈(ライティング・ワークショップの実践者としての文脈)からこの本について書こうと思う。ハイ・テック・ハイに影響を与えたその思想は、プロジェクトの学びの文脈で語られることが多いが、このエントリではプロジェクトのことは一切出てこない。だからこのエントリは、「レビュー」と呼ぶには偏った、個人的な「読書メモ」である。読者には、そのことをご承知おき願いたい。
[ad#ad_inside]「作り出す喜びと誇り」を中核に置いた実践
筆者のロン・バーガーは、教師と大工の二足の草鞋を履く実践家であり、その経験から、卓越した美しい作品をつくり上げようとする誠実な姿勢=クラフトマンシップを育てることを自らの実践の中核に置く。子どもの誇りとは、単に褒めることから生じるのではなく、「良い作品をつくり上げるその過程で自尊心が培われる」(p103)のだとバーガーは言う。彼は子どもたちに草案をいくつも作ることを求め、相互に批評することを求め、質の高い作品を作らせようとする。そのことを通じて「子どもの誇りに灯をともす」のだ。いわば、「作り出す喜び」を中核に置いた実践だとも言える。
まず、僕はバーガーのこのビジョンがとても素敵だなと思っている。僕のやりたいことと、おおよその方向性としては同じだ(ただ、後述するようにかなり違う点もある)。もともとが僕の実践するライティング・ワークショップも、「作品づくり」を通して「表現する喜び」を中核に置いた実践である。木工作品と文章と形は違えど、根幹は変わらない。だから僕にとって、この本は、ごく自然にライティング・ワークショップの本として読めた。
クラフトマンシップの文化をどうつくるか
そして、本書で強調されているのが、そのようなクラフトマンシップを育てる上での、コミュニティにおける文化づくりの重要性だ。なぜ子どもたちが質の高い作品を作ることにこだわれるのか?という問いに対して、著者は「ほとんどの子が4歳の頃からそうしてきたから」と答える(p105)。彼の学校には、優れた作品が至る所に展示されており、それを見て自分も作って育ってきた子どもたちは、「作品の質にはクラス全体でプライドを持っており、高い基準を目指そうというピア・プレッシャーが」ある状態なのだという(p111)。これはすごい。
ところで、風越に来てからの僕も、自分が授業で直接的に「教える」だけでなく、「学校に読み書きを愛する文化をつくる」ことに関心を寄せるようになってきた。それは、読み書きが好きではない子がどうしたら書くようになるのか、しかも「書きなさい」「読みなさい」と大人の僕に言われるのではなくて、自然としてしまうようになるのか、それを考えた結果である。読み書きが嫌いな子は、基本的に国語が好きではないのだから、国語教師の僕の働きかけで変わる可能性も高くない。その子が変わるとしたら「みんながそうするから」である。読書好きの両親のもとでは自然と読書好きの子どもが育ちやすいように、集団の中で当たり前の水準になった時に、その子もごく自然とそうする。だから、読み書きを愛する文化を学校の中で作ることが、遠回りのようで近道なのだ…と思うようになってきた。
ただ、「文化を作る」とは簡単ではない。異学年の交流などをしながらもまだ満足のいく成果には繋がっていない中で、「クラシフトマンシップの文化を作る」を中核に置いたロン・バーガーの実践を読めたことは、大きい刺激になった。
では、どうしたらそんな文化を育めるのだろうか。この本にはルーブリックやチェックシートも登場するが(p112)、それをやれば文化が自動的にできるわけではないことは火を見るよりも明らかだ。
その問いについて考えるときに、頭の中に浮かんでいた本がある。それは、僕が尊敬するライティング・ワークショップの実践者、ナンシー・アトウェルの『イン・ザ・ミドル』である。僕自身も翻訳に関わった『イン・ザ・ミドル』は、本書ロン・バーガー『子どもの誇りに灯をともす』と、とても似た「匂い」がする本なのだった。
バーガーとアトウェル 2人の教育者
バーガーとアトウェルの間には、授業者としてのあり方や方法のレベルでいくつかの共通点があり、それが共通する「匂い」に繋がっている。また、それが「文化を作る」ことで大事な要素であるとも思える。というわけで、ここからは、両者の共通点を挙げてみよう。
自らも作品を愛する作り手である
バーガーは大工として、アトウェルは書き手として、何よりもまず自身が作品を愛し、作る「作り手」である。そのジャンルの作品を愛して、それを享受し、自らも作り手として子どもたちの前に立つ。アトウェルは、自分が作品をつくるプロセスや自分の作品を、実際の授業の教材とする(『イン・ザ・ミドル』p166)。結局のところ、バーガーやアトウェルの実践を根底で支えているのは、自分自身が愛する対象を持ち、その「作り手」(大工/書き手)であることを通して自己形成をしてきた確信なのではないかと思える。
モデルの真似を推奨する
ロン・バーガーはモデルとなる作品を、子どもやプロを問わずに常に収集する。彼は「エクセレンスの収集家」だ。そして、集めた卓越した作品を子どもたちに見せて、分析し、それを真似して自らの作品を作ることを推奨する(p129)。アトウェルも同じだ。彼女の「ジャンルスタディ」は、まずモデル作品の良さをみんなで分析し、優れた書き手や批評家がすることを真似するところから始まる(『イン・ザ・ミドル』p307)。彼女自身も、常に子どもにとっての良いモデルを探す蒐集家でもある。
作品の質にこだわりを持つ
本書では、卓越した作品を生み出すためにロン・バーガーがいくつも草案を作らせるプロセスが記述されている(p129)。子どもたちは単に作品を仕上げるのではなく、「優れた作品」をつくることを求められ、それをつくる過程で自信をつけていく。アトウェルも、子どもたちの作品の質にこだわる。「好きなことを好きなように書けばいい、欠点は指摘しない」という、一部のライティング・ワークショップ解釈を吹き飛ばすかのように、子どもの文章を細かく読み、順番や言葉の選択についてカンファランスで助言し、提出された草稿にも朱を入れて返却する(『イン・ザ・ミドル』p251など)。その徹底ぶりは、ちょっと唖然とするほどだ。それほどに、両者は作品の質を追い求める。
批評に必要な語彙を教える
質を高めることと車の両輪なのだと思うが、ロン・バーガーは、プロジェクトを通してその遂行に必要な言葉の力を鍛え(p114)、批評セッションでは、作品の批評に必要な語彙を教えていく(p148)。こうした取り組みは、アトウェルがリーディング・ワークショップのレターエッセイを書く時に、批評の書き方や語彙を教えることを彷彿とさせる(『イン・ザ・ミドル』p308-309)。単に「よかった」「面白かった」では済まさずに、質の高い批評をするための語彙(着眼点)を教える点も共通している。
作品を公開する
バーガーは、子どもの作品を常に公開する。校内は常に生徒の作品でいっぱいだ。作品を公開することは、子どもたちの重要なモチベーションにもなっている(p158)。アトウェルも同様だ。作品の読み手は教室を飛び越えて存在するし、機会を見つけては作品を出版する(『イン・ザ・ミドル』p345)。僕が2016年にアトウェルの学校を訪れた時にも、校内は子どもたちの作品でいっぱいだった。
芸術を愛する雰囲気をつくる
先に書いた通り、ロン・バーガーは「卓越した作品を作る文化」を学校に作ろうとしているが、アトウェルも同じく「芸術を愛する雰囲気」を作ろうとしている。それについては『イン・ザ・ミドル』よりも下記の本に詳しい。あと、僕も彼女の学校を訪問した時にそれを実感してブログに書いた。朝の会で詩を読んだり歌を歌ったり、文学者について知ったり、壁には生徒たちの絵をたくさん貼ったり…芸術を核としたコミュニティを作ろうとしているのだ。
どちらも「作る」がモチーフの実践
いくつかの共通点を挙げてきたが、アトウェルもバーガーも「作る」をモチーフにして、作り手としての文化を育てようとしている。ライティング・ワークショップは、ワークショップ(工房)という由来の通り、作家が芸術作品としての小説をつくる工房をモチーフにした実践なのだから、大工のバーガーの実践と共通点があるのは、ある意味で当たり前なのかもしれない。どちらにも、自分が所属する文化集団の中で、素晴らしい作品を生み出す先達に学びながら自分の作品の質を上げていく、状況的学習論を思わせる学びのプロセスがある。そして、「子ども」というより「美しい作品」をど真ん中におくそのやり方は、もともとが「子どもよりも読み書きが好き」な僕にとっても、非常に親和的なものに思える。
相違点:相互批評をどう捉えるか?
ところで、これほどまでに多くの共通点がある両者だが、ひとつ大きな違いがあるのも興味深い。ロン・バーガーの「質の高い作品を作る」実践には、「批評セッション」(「ギャラリー批評」と「深い批評セッション」)という形式で行われる相互レビューがある。そのやり方も詳細に紹介されており、これが彼の実践の核であることは容易に想像がつく。
一方のアトウェルは、この子ども同士の相互批評にほとんど重きを置いていない。p99-100でピア・カンファランスについて紹介しているが、アトウェルの実践で子どもたちの作品を批評し、改善に向けて助言をするのは、基本的には教師たちなのだ。子どもたちは批評の書き方は習うが、その対象はプロの作品のみで、子ども同士が制作途中のお互いの作品を批評し合う場面は全体としては設定されない。これは、アトウェルの学校を訪問した時でも同じだった。基本的には生徒の作品に改善に向けたコメントをするのはプロである教師の仕事、という姿勢を貫いている。
この違いはどう考えれば良いのだろう。僕もアトウェルと同様、ピア・レビューを今は導入していない。中高教員時代はやっていたのだが、やればやるほど難しさを感じて、やめてしまった。そもそも、効果的な助言とは、(1)作り手の作品が表現したいところを受け止めて、(2)そこと現在の作品の状態や、作り手の力量を見て、(3)そのギャップを埋められるのに役立ちそうなことだけを選んで言う、非常に高度な営みである。子どもの同士のピアレビューでは、大抵の場合、読み手が書き手の希望や技術レベルを考えずにただ感想を言うか、配慮し合ってお世辞をいうか、悪くすると逆に勉強ができる子ができない子に「教えてあげた気になっている」だけの結果をうみかねない。だから、基本的には僕もピアレビューには慎重で、アトウェルの方にシンパシーがある。
ただ、ロン・バーガーもアトウェルが念頭に置くような1対1のピアレビューは「効果は限定的」として実施していないことにも注目したい。彼の批評セッションは「クラス全体で批評しあい、クラスメートに知識とスキルを共有する」(p143)目的で実施されているので、ライティング・ワークショップのフレームワークの中では、彼の批評セッションは「ミニレッスン」や「共有の時間」に近い。こうすることで場の主導権を教師が握り、ピアレビューのデメリットも低減できると考えているのではないだろうか。
相違点はさておき、ロン・バーガー『子どもの誇りに灯をともす』を、ナンシー・アトウェル『イン・ザ・ミドル』と合わせて読むことで、両者の共通点がはっきりと見えてきた。これら卓越した2名の実践家の共通点は、おそらく「文化をつくる」上でも大事な鍵になっているのだと直観する。自分の実践を照らす鏡として、大事にしておきたい。
これからの自分の実践への「問い」
最後に、本書を読んできて浮かんだ自分の実践への「問い」を書いておきたい。それは、質の高さ、「より良い」を目指して全力で改善することを、どこまで子供達に要求するのかという問いだ。これは、具体的には、教師がどこまで子どもの作品を批評するかだけでなく、子ども同士の批評セッションをするかどうか、という問題とも関わってくる。
かつてを振り返ってみると、中高教員時代、僕は「編集会議」と称したピア・レビューをやっていた(下記エントリ参照。2017年のもの)。
当時の僕は、「ただ書くのではなく、書き直すときに力がつく」という信念のもと、いったん草稿(下書き)を書いてそれを書き直すことを全員に求めて、子ども同士のピア・レビューを盛んに実施していた。昔の僕は、ごく自然に生徒に質の高いものを要求していた。それは、生徒が中高生だったこと、しかも学力レベルの非常に高い中高生だったことも関係しているだろう。
ただ、2017年当時のブログで書いているように、書き手の心理的安心性のことなどを考えて、だんだんこの編集会議の実施に消極的になってきた。そうして、風越に来てからは、それもやめてしまった。
そして今の僕は、子供達に正面きって「質の高さ」をあまり求めない。逆に学力差の幅が広い小学生を相手にしている今は、できるだけ気軽に書けるように、あえてハードルを下げ、楽しく書いているうちにうっかり力がついてしまうような課題設定の工夫を目指してきた。下記エントリの、子どもを自由にする制約などはその一例であり、それが僕なりの風越への「適応」だったのだ。
そう変化してきた僕の考えは、こうである。そもそも、質の高さを求めた改善点の指摘は、書き手(作り手)側の「改善したい」「より良いものを作りたい」気持ちがないところには意味がない。そして、僕の接する小学生の書き手は、現実として書いたことだけで満足で、「さらに改善したい」と思わないことも多い。おそらくは、「より良いものを作る」気持ちにまだ乏しく、欠点を指摘されるのも単純に嫌なのだろう。僕もそれを受け入れて、ひとまず楽しんで試行錯誤して書くことを最優先にして、文章の改善点の指摘は、それを望む子どもにしかしていない。
また、質の高さを求めることは、力のある子には良いけれど、書くプレッシャーを高めて、気軽に失敗できなくなる気持ちも同時に醸成する。負担感も増す。書き直すことが嫌な子や面倒臭がる子、書けなくなってしまう子も間違いなく出てくる(過去に実際にそうだったし、風越でも何人もの顔が頭に浮かぶ)。少なくとも今の風越の子たちは、そういう「負荷」をかけられる状態ではない。それよりも「表現する楽しさ」を優先して、子どもの側から求めてこない限り、僕はダメ出しはほとんどしていない。
総じて、僕は以前よりも質の高さを直接には求めなくなってきたし、直接「教える」ことにも、随分と禁欲的になってきた。それに変わって僕が力を入れるようになってきたのは、子どもの作品に潜む良さを見つけ、全体に共有することである。良さの共有をミニレッスンや共有の時間で積み重ねることで、子どもたちが書き手としてのお互いの良さを見つけ、リスペクトし合う関係を作ること。そこに力点を置いている。だから、子供からすれば「別に力を入れて書いた作品ではないのに褒められる」経験もきっとあるし、それは子どもの誇りを生まない、とバーガーは言うだろう。(そして、確かにその通りだと僕も思う)
バーガーの実践は、「質の高さを求める」ことが中核にある。それは「教えること」「改善点を指摘すること」と切り離せない。一方で、風越に来てからの僕は「直接教えることを減らし、改善点の指摘もせず(子ども同士でもさせず)、子どもの良さを共有することを通じて教える」ことを目指してきた。だから、今の僕はロン・バーガーとは随分違う(アトウェルからも距離が離れてきた)。
バーガーの育てるような「誇り」は、確かに今の僕の実践からは生まれにくいだろう。もともとが「鍛えたい」系の僕には、そういう「誇り」を育てたい気持ちもある。ただ、それでも、「質の高さ」を自分が求めることの弊害に実際に出会って試行錯誤してきた歴史があるだけに、どうしたらいいかを考えてしまうのだ。僕が出会ってきた問題た問いに、バーガーはどう考え、対応してきたのだろうか。これは実際に聞いてみたいところだ。
「作り手」の倫理を育てる
アトウェルとの比較を中心に書いてきたように、ロン・バーガー『子どもの誇りに灯をともす』は、僕にとってはライティング・ワークショップの本でもあった。久しぶりに『イン・ザ・ミドル』を読み返したり、過去の自分の実践から変化してきた点を自覚したり、今の自分について反省したりと、この本のおかげで、色々な経験ができた。ありがたい読書体験だった。この春休みは、この本を参考にして、文化を作ること、そして質の高い作品を求めることについて、ぐっと考えていきたい。
また、作り手の倫理を育てるこの本は、「子どもも大人も『作り手』である」ことを目標にする風越学園にとっても、示唆の多い本だ。風越学園の目指す「作り手」とはどういう人なのか、その問いについても同僚と考えてみたいなと思う。
とまあ、このエントリでは極めて個人的な視点で書いてきたが、別にライティング・ワークショップの実践者でない人にも薦めたい本である。「子どもの誇りに灯をともす」、本当に素敵な邦訳だと思うが、それを志す全ての人に、手に取ってほしい。
[ad#ad_inside]追記)文化を作る条件
文化をつくる条件について、本書の解説者・藤原さとさんもブログで書かれていたので、リンクを貼っておこう。ここでは、教師の関わりとして、「意義のある学習活動を割り当てる」「エクセレンスの事例を研究する」「批評の文化を構築する」「複数回の見直しを要求する」「公のプレゼンテーションの場を提供する」の5つを挙げている。
High Tech High ―最上のアウトプットを求める学校文化の育み方