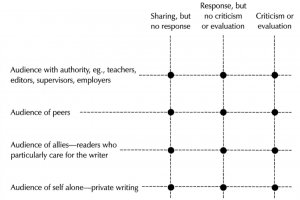以前に下記エントリで、アトウェルがミニ・レッスンで教えている「一粒の小石の法則」を扱った。文章を書くときに、一般論で書かないで、具体的な特定のものについて書く、というやり方のことだ。
[ad#ad_inside]
問題点をズバッと指摘、アトウェルのカンファランス
アトウェルがp223で例示しているのは、アメリアという少女が、父親の誕生日に送るために、父との思い出について詩を書いていた時のカンファランス。アメリアの下書きを読んだあと、アトウェルは開口一番にこう言う。
アトウェル:リストですね。とても大切な思い出が書かれています。ただ、今のままだと何粒もの小石が並んでいますね。お父さんとの関係をもっともよく描く一粒の小石が見えません。思い切って、一つを選んでそれを他のと区別してごらん。一つを選び、それに肉付けして、考えたことや感じたことを加え、お父さんとアメリアがどんなふうかを示せないものかしら?
アメリア:でも、どの一つを選べばいいのか…あ、もしかすると、夜に二人で散歩したことかも、お父さんと二人だけで。
アトウェル:それでやってみましょう。
ここでのアトウェルは、ズバッと問題点に切り込んでいる。「リストですね」とは、お父さんとの思い出がリスト状になってしまっていて(思い出全般になっていて)、もっとも大切な思い出(一粒の小石)が選べていないということ。それを、ミニ・レッスンで教えた「一粒の小石の法則」の言葉を使って端的に示しているのだ。ミニ・レッスンとカンファランスが連動し、短時間で改善につなげている。
カンファランスというと、「生徒の話をじっくり聞く、励ます」みたいなイメージを持っていた時期が僕にもあったのだけど、アトウェルのカンファランスはそうではない。短時間でポイントを絞ってしっかり教えるカンファランスだ。ある日のアトウェルのカンファランスは、30分の授業で12人ほど(p212)。短時間で全員に関わり、個々の文脈に応じて必要なことを教えていくのが、アトウェルのやり方というわけだ。
読み書きの知識をオーダーメイドで手渡す
短時間でこうしたカンファランスをするのは、とても大変。というのも、決して「パッとみてすぐに目についた欠点」を言えばいいというわけではないから。アトウェルは、その子の今学期の課題や、今の状態を見て、目を瞑るところをつぶるし、校正の指摘も一箇所までに留めている。カンファランスの際、彼女の頭の中ではこういうことが起きているのだと思う。
- 読み書きについての知識や、学ぶべきスキルの体系が頭の中に入っている
- 目の前の生徒についての知識がある。いま、読み手や書き手としてどんな状態か。
- 生徒の文章を読み、読み書きについての知識を使って、できていることとできていないことを見分ける
- それを、目の前の生徒の状態についての知識を照らし合わせて、「いまは何にポイントを絞って教えるべきか」を判断する
- ミニ・レッスンで教えたことを使って生徒に思い出させながら、ポイントを教える
いうなれば、自分の持っている知識の体系を、毎回その生徒向けにオーダーメイドして手渡しているわけ。これはちょっと凄いですよ。まず自分の中に読み書きのスキルが全て入っていて、しかもそれを、目の前の生徒の状態と照らし合わせて再構築して、最善のコメントをする。理想的にはそういうことを目指している。なかなか真似できる気がしない。「マンパワーで行うアダプティブ・ラーニング」っぽいところがある。
カンファランスが真髄、アトウェルのワークショップ
今回紹介したのはライティング・ワークショップのカンファランスの話だけど、リーディング・ワークショップの場合は、ブログ「WW/RW便り」の下記エントリで紹介されている。こちらでも、アトウェルが極めて短時間で、効果的にカンファランスを行なっていることがわかる。
WW/RW便り:読み手を教える個別カンファランスを、短時間で効果的に行うには?
http://wwletter.blogspot.jp/2017/11/blog-post.html
僕はもともと「生徒数の多い日本の教室で、カンファランスをやるのは無理」派なのだけど、アトウェルのカンファランスの事例を見ると、自分のそれとの大きな違いに驚くし、自分ももう少しなんとか工夫できるのではないか、と思えてくる。「カンファランス・アプローチ」と言われるくらい、カンファランスはライティング・ワークショップにとっては大事な要素なのだ。実際、カンファランスを通じてしっかり「教えている」ことこそ、アトウェルのライティング・ワークショップの真髄なのだろうなとも思う。
こういう点を見逃して、「教師の仕事はファシリテーター」とか、「生徒同士で協力し合うのが良い」という方向に、安易に流れたくはないな(もちろん、そっちでも読み書きの力を鍛えていればいいのだけど)。少なくとも自分のカンファランスには、まだまだ良くなる余地がありそう。