「待つことが大事」と口で言うのは簡単だが、そうと言ってばかりもいられない。僕たち学校教員の仕事は、生涯学習とは違って期限付きの仕事だからである。そうだからこそ、作文教育でも「待つか、与えるか」のジレンマに時々悩まされる。今日は、それについてのエントリ。
教師から「与える」行為、添削
作文教育における「与える」行為の一つが、教師による添削だ。僕は、添削についてはずいぶん前に書いたことがある。結論は、「添削が有効に機能するには、一定の条件が必要になる。その条件が整わない添削はほとんど効果がない」というもの。2014年の文章だけど、今でも、基本的な考えは変わらない。
しかし、尊敬するナンシー・アトウェルは子どもの文章にびっしり添削をする。「子どもが書いた作品が、きちんと読んでもらえるように」である。僕が彼女の学校に行ったときも、一行おきに下書きがタイプされた原稿に、先生たちが赤をびっしり入れていた。
そして僕自身は、子どもたちが「作家の時間」で提出する作品に、「優れたところやプロセスについての文章コメント」と「最低限の添削」をして返している。指摘はほぼ一種類だけ。添削の箇所を抑えることで学習率をあげようとしているのだ。子どもたちは、僕の指摘を受けてもう一度作品を提出しなおし、それで完成となる。
子どもたちの完成品を読んでみると…
しかし、である。先週、ショートショートの出版を迎えて、再提出された子どもたちの作品を読み直して気づいた。こちらの指摘に答えていない子がけっこう多い。せっかく僕が修正案も書いているのに、修正をコメントに反映させないでそのまま再提出しているのだ。これには反省しきりだった。こちらの添削が反映されないのは、つまり、先方が修正点の指摘を期待していないか、こちらが先方の能力以上のものを求めてしまっているかのいずれかである。添削は、子ども自身がそれを求めていない時には、ほとんどの場合が徒労に終わる。いつのまにか、やってはいけないとわかっていたはずのことをやってしまったのだ。
書くことを指導する教師なら共感してもらえると思うが、書くことの指導の要諦は「書くのが好きになってもらうこと」である。好きでないものをうまくなりたい(書きたい)とは思わないし、うまく書きたいと思わなければ、上達させることもできない。こんなにシンプルな結論を、それでも時々見失うのは、僕たちの仕事が「時間制限」のある仕事だからだろう。おおらかに「好きになるまで欠陥を指摘しないでいる」のはなかなか難しい。けれど、それが求められる仕事でもあるのだ。相手が改善点の指摘を求めてくるレベルに達するまでは、余計なことは言わないほうがいい。
事前の説明をできるだけ減らすこと
この「求められるまで与えない」という観点ではもう一つ、先週、風越学園の甲斐利恵子先生(りんちゃん)と話した話も面白かった。「ダイコンは大きな根?」の模擬授業にあった段落の10の役割(「導入」「呼びかけ」「問題提起」「説明」「解説」「根拠」「例示」「引用」「まとめ」「主張」)をあらかじめ説明しない理由について聞いたところ、甲斐先生は「ほとんどの子は事前の説明を聞いていないから」だと答えたのだ。
その上で甲斐先生は、「赤坂中でもそうしてきたつもりだけど、今思うと、今よりもずっと説明していた。風越にきてから、赤坂中の頃よりも説明の量はぐっと少なくなった、言っても聞いてもらえないんですもの」とも言った。なるべく事前の説明は減らし、子どもが知りたいと思ったタイミングで手渡していく。これも、添削の話と通じる姿勢である。
「求められるまで与えない」
添削にせよ、授業中の説明にせよ、「求められるまでは与えない」は、一つの真理なのだろう。しかし、時間制限のある学校教育を担う僕らにとっては、なかなか実践するのが難しい真理でもある。つい、求められていないタイミングで渡して、というより押し付けてしまう。そんな我が身を顧みつつ、ひとまずは次回の「作家の時間」から作品の最終チェックでの添削をやめてみるつもりだ。優れた点の指摘だけで、どこまでいけるかやってみよう。
[ad#ad_inside]






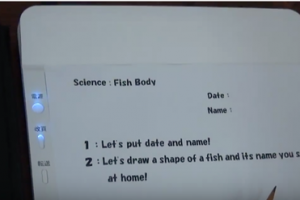






![[ITM初版]ライティング・ワークショップで教師がするべきこと](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/51rNbV5S1ZL._SL160_-5-50x50.jpg)