2018年に僕も訳者の一人として翻訳を刊行した、ナンシー・アトウェル『イン・ザ・ミドル ナンシー・アトウェルの教室』を、ひさしぶりにちゃんと読み直す機会を持っている。せっかくなので、ここでも、少しずつ再読の記録を書いておこうと思う。不定期で連載して、今日は第3章まで。
[ad#ad_inside][ad#ad_inside]
アトウェルの「きびしさ」が印象的…
今回、『イン・ザ・ミドル』を読み直したきっかけの一つに、ロン・バーガー『子どもの誇りに灯をともす』を読んで、アトウェルとバーガーの間に共通点を感じたことがある。どちらも「より良い作品」づくりに向けて妥協がないのだ。
そういう経緯で読み返しているせいかもしれないが、ここまでのところ、やはり、アトウェルの緻密さ、丁寧さ、そして厳しさが印象的だ。例えばライティング・ワークショップ(作家の時間)のp87の子どもたちの予定表を見ても、多くの子が「書き直し」作業をしている。書いてそのまま提出、なんてことはない。おそらく、子どもが「面倒くさい、これでいい」と言っても、アトウェルは認めないのだろう。
また、リーディング・ワークショップ(読書家の時間)では、毎日30分の読書を宿題として課している。
宿題を必ずするように指導する代わりに、その価値のある宿題だけを出すようにしています。毎晩、30分読むというのは、そのよい例でしょう。毎日読み続けることは不可欠です。この宿題をやってこない場合、なんでやってこないのかを生徒・保護者と話し合います。…理由を考えたあとで、いつ、どこでなら、毎日読めるのかということについて、相談します。すべての生徒が毎晩読んでくれるといいな、というような希望的観測で満足するのではなく、必ず読むように、私は自分のできる限りのことをします。(p124-125)
この徹底ぶりは何度読んでも苦笑する。他の箇所でも、「少なくとも昨日読んだ箇所より20ページは進んでいるか」をチェックしている(p89)くらいだ。僕なんて子どもたちにも「毎日30分読もう」と呼びかける程度なので、到底足元にも及びません….(ページ数のチェックはしていて、これはその子の読書ペースを把握する上でも良い参考になる)。
期待に裏打ちされた厳しさ
こうしたアトウェルの厳しさ、細かさは、当然15名の子どもたちと週4回関わるという好条件にも支えられているが(p51)、何よりも文学や子どもへの高い期待に裏打ちされている。
誰もが、すべての生徒が、いいストーリーが好きなのです。この本質的な真実に辿り着くのに、恥ずかしながらこんなにも長い時間がかかってしまったと、私は認めざるを得ません。ストーリーそのものの魅力は、国語教師にとってはスーパーヒーローに匹敵する力をもっています。
学校での書く授業と同じように、読む授業でも、生徒たちはそのチャンスさえ提供されたら、しっかり成果を出せるのです。それも、私が生徒から教わったことです。理解しつつ楽しんで読むことには、性別も、社会的な地位も、家庭環境も、これまでの経験も関係ありません、。選択、特に優れた作品を選ぶことができ、読むための時間が確保され、文学と生徒一人ひとりをよく知っている教師がいれば、実現可能です。(p44-45)
「すべての生徒が、いいストーリーが好き」という確信。「文学と生徒一人ひとりをよく知っている教師」によってすべての子どもたちが導かれるという自信。こうしたものが、彼女の実践を支えているのだ。
そして、書くときにも、子どもたちに対して、書くことを通じて大切なことを成し遂げようと語りかける。「自分がどんな人であるのか、あったのか、あるいはどんな人になりたいのか。それに関わるような、価値のある題材を選びなさい」(p94)と。
こうした呼びかけはともすると子どもの側の「息苦しさ」に繋がりかねない。しかし、子どもや文学に関する知識とその譲り渡しの手腕によって、実際に子どもたちが読み書きに浸る文化を作ってしまえる点が、彼女の卓越した点なのだと思う。ロン・バーガーも書いていたが、そういう文化が成立した中においては、読み書きに懸命に取り組むことは子どもにとって「当たり前」になるのだから。
それでも、子どもが主役の授業
こういう高い期待をもって授業に臨むアトウェルと子どもたちの関係は、おのずと、彼女が子どもたちを教え導く「TーC(先生ー生徒)関係」の色濃いものになっていく。『イン・ザ・ミドル』でも、子どもたちの関係性形成に関する話題はほとんどなく、そこはたとえば小学校の先生からすると、読んで物足りないと感じるかもしれない。
そのことに対する賛否や好みは当然あるだろう。でも一方で、彼女が(自分の計画の範囲内で、という留保つきだが)授業のときに子どもたちを主役にしている点も間違いない。例えば子どもが使いやすいようによく整備された教室(p71-78)は、本当に子どもの書きやすさ、読みやすさが考え抜かれている証拠だ。この教室で読み手・書き手として自在に思考をめぐらせる子どもの姿が目に浮かぶようである。
また、彼女は毎日詩を読み、さまざまな文学の技について教えているが、「今日の詩」で使われる詩の多くは「今教えている、あるいは過去に教えた生徒たち」ということも見逃せない(p114)。つまり、毎回誰かしら子どもが主役になっているのだ。これについては僕も似たようなことをやっているが、子どもの作品をミニレッスンなどで使うためには、作品を読むときにそれをミニレッスンの項目別に整理するなど、ストックを日々作る作業が必要になる。こういう手間をかけても、子どもを主役にしている。この点は、アトウェルとはだいぶ色彩の違う「作家の時間」の本『国語の未来は「本づくり」』とも共通していて、こういう点がアトウェルが単純な「教え込み」の人とは違うゆえんである。
彼女自身、自分の授業スタイルについて次のように語っている。
ライティング・ワークショップの両輪は、教師の知識と、生徒の自己決定です。私は、自分が教える書き手たちの選択、意図、必要を尊重しながら、同時に彼らに対応し、導き、成長する方法を示しています。日々探究しているのは、このちょうどよいバランスです。(p37)
動的に揺れ続ける教師のありかた
本書の「少し長めの訳者前書き」にも書かせてもらったが、僕にとってアトウェルとは、「ティーチャーとファシリテーターの間を揺れ動いた人」である。教師中心でも、生徒中心でもない、そのあいだ。最初にライティング・ワークショップに出会った1980年代の自分を、アトウェルは批判的にふりかえってこのように書く。
1980年代の頃を振り返ってみると、当時の私は「ライティング・ワークショップでは、書き手たち一人ひとりが平等である」という考え方に心酔していたように思います。無理もありません。当時はまだ20代でしたし、私自身が、絶対の権威者としての教師としての役割から、書くプロセスを支えるコーチやファシリテーターという役割へ、変容を遂げている真っ最中だったのですから。画期的に変容した時期であり、教師が課題も期限も決めるという従来型の考え方から離れるためには、思い切ったジャンプが必要だったのでしょう
…(中略)…
ところが、私の中に別の変化も生じました。教師として大きく変わる時期には、ありがちのことかもしれません。自分が変わるなかで、新たに学んだ教え方こそが正しいと思い込んでしまったのです。それはたとえ生徒中心のものであっても、従来、こう教えるべきだと言われていたやり方と同じような危険があります。それは、書き手としての生徒の可能性や、教師としての私の可能性を狭めてしまうという危険でした。(p32-33)
久しぶりにこの箇所を読んで、自分にとってアトウェルが「ザ・ベスト」であり、惹かれ続ける理由が、あらためてわかった気がする。ちょうどいまの自分も、筑駒的な価値観と風越的な価値観(と書くのは、それぞれをあまりに単純化・戯画化しているけれど)の間や、福祉的な「ありのままのあなたで素晴らしいよ」的価値観と、教育的な「もっと変化しなければいけないよ」の間で揺れ動いている。僕はこういう「動的に揺れ続ける教師のあり方」に魅力を感じる人なのかもしれない。
まだ第1章〜第3章の「総論」的な部分だけだけど、やはりアトウェルはすごい。自分にも子どもにも高い期待をもって、手を抜かないところ、つねにベストを求めて揺れ動いているところ、そして、文学への愛と知識に裏打ちされて、しっかりと文学を愛する文化を根付かせているところ。彼女に追いつけ追い越せとまでは思わないけれど(なにしろ相手はグローバル・ティーチャー賞の人である)、自分にもまだまだできることはありそう。憧れを新たにするここまでの読書だった。続きも楽しみだ。
[ad#ad_inside][ad#ad_inside]






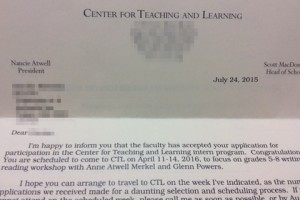
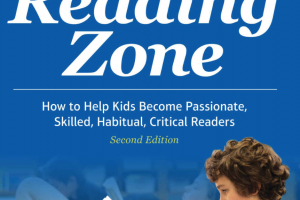



![[読書]概念型カリキュラムの丁寧な解説と教師の成長の手引き。H.リン.エリクソン他『思考する教室をつくる 概念型カリキュラムの理論と実践』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2022/08/63784dbe670a1c78282cacc70d06eae2-50x50.png)
