I Confess.
初版は、彼女の初めてのIn the Middleだけあって、後の版よりも「ライティング&リーディング・ワークショップ前」の彼女の様子や、ライティング・ワークショップを前に戸惑う彼女の様子が詳しく描かれている(これは第二版だと結構残っているが、第三版だとあまり見られない)。初めてライティング・ワークショップのことを聞いた時の彼女の反応は、次のようなものだった。
スーザンがアトキンソン・アカデミーのライティングの授業について私に話した時、8年生(中学二年生)の英語の授業でのワークショップなんて絶対に間違っていると思った。実際、それは危険だと思った。予測不能の大きな子どもたちが、いきなり自分でお題を設定する自由を与えられて、教室内をうろつき回って、友達とおしゃべりをして、彼らなりのアイデアや興味について書くなんて。(p40)
私はどうやって生徒に責任を分け与えればいいのかわからなかった。それに、私が本当にそれを望んでいるのかどうかも。私は教師用の大きな机に守られているのが好きだった。書くべきお題を設定し、ペースややり方を指定して、プロセス全てを自分の責任で周到に用意するのが好きだった。それが私の仕事ではないの? それが生徒のもとに渡ってしまったら、私は何をするの? (p11, 第二版ではp13)
私は最近、自分の教室の中で学んでいる。それは、これまで私が作ってきたもの(カリキュラム)を捨てたからだ。私はそうしなくてはいけなかった。私が自分自身や自分の授業法ばかり見るのをやめて、生徒たちと彼らの学びに目を向けた時、私が見たのは、自分と彼らの間にある大きな裂け目だった。それは、私が言葉の教師としてやってきたことと、彼らが言葉の学び手としてやってきたことの間にある裂け目だった。p4






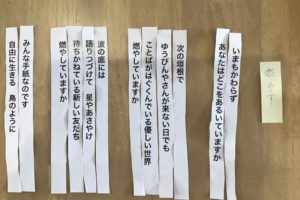
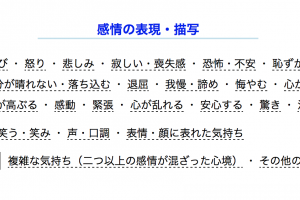




![[読書]石井英真『今求められる学力と学びとは―コンピテンシー・ベースのカリキュラムの光と影』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/51O4gmLhXWL._SL160_-1-50x50.jpg)
![[読書]ネガティブな感情に向き合える子をどう育てるか?藪下遊/髙坂康雅『「叱らない」が子どもを苦しめる』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2024/04/4e685d6ad4dbe60ad73a4e1359b7d9c5-50x50.png)
