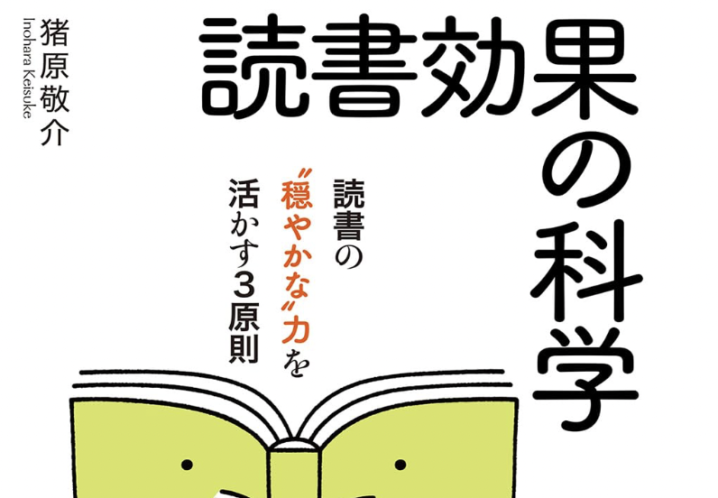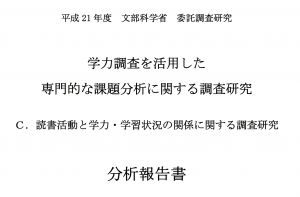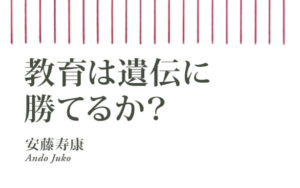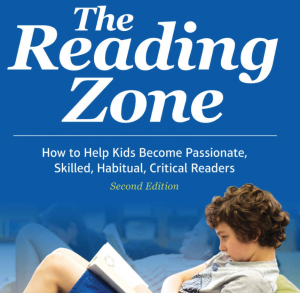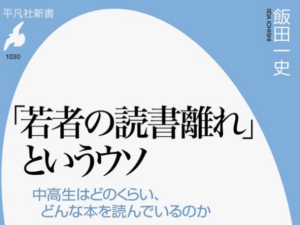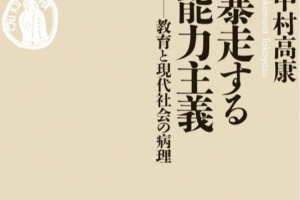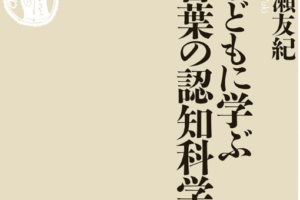発売されたばかりの猪原敬介『読書効果の科学』は、間違いなく、今後の読書教育を語る上で基礎文献となる一冊だ。読書教育にとりくむ国語科教員や図書館司書は絶対に読むべき本で、「この本の内容を踏まえずに読書教育を語っても仕方ないよね」という、今後の議論の共通の土台を設定する本だと思う。また、本書冒頭で「もっとも念頭においた読者」として想定されている小学校の教員や保護者も、関心のある人は手にとってほしい。
ただ、先に断っておくと、本書は「家庭でとりくめるやさしい読書教育」について書いた本(たとえばつい先日紹介した中本順也『おうちでできる子どもの国語力の伸ばし方』や、ヨンデミーの笹沼颯太『ハマるおうち読書』)とは全く違い、一般書にしてはガチ目の読書研究レビューの本である。一般読書向けに易しく用語解説もあるが、慣れない人にはハードルが高く感じるはずだ。大学院で教育研究のトレーニングを一応は履修している僕も、よくわからないところがあった。そういうところまでちゃんと伝えようとしているところは著者の誠実さの表れだろうが、難しかったら飛ばしてもいい。本書のエッセンスは十分に伝わるはずである。
[ad#ad_inside]読書研究の蓄積が導く「穏当な結論」
世間には、読書の効果を絶対視するものから逆にそれを否定するものまで、読書に対するさまざまな言説がある。それこそ「世の中の成功した企業人はみんな本を読んでいる。読書こそ社会的成功に基づく!」から、その逆張り的な「読書は学力と関係がない」まで、たくさんだ。本書を読めば、そういう極論がいずれも膨大な研究やエピソードのごく一部だけを都合よく切り取ったものであり、全体として読書研究の科学的知見に基づいていないことがわかる。
本書の柱は、近年進展を見せた読書研究をレビューして、「言語力」「人格」「心身の健康」「学力」「収入」といった切り口で、読書にどのような効果があるのか?を論じている点にある。レビューされる論文は海外のものから日本のものまで多岐に渡り、相関だけではなく因果関係をも推定できる研究をきちんととりあげている。
それらの研究をふまえて結論を言えば、上記の切り口の全てに関して、読書は効果がある。しかし読書の効果は劇的ではない「穏やかな」もので、短期間では効果の見込めない「長期的な」効果であり、しかも、個人差が大きい。言われてみれば当たり前の「穏当な結論」を、本書では最新の研究を用いて、地道に導いているのだ。
そうした研究の成果にもとづいて、筆者は3つの原則を提言をしている。どれも、読書教育の基本的な指針になるもので、この原則が本書では何度も登場する。
【原則1】 平均的には効果は穏やか。気長に気楽に。
【原則2】「 読みすぎ」は弊害を生む。目安は1日30分~1時間。
【原則3】 個人差は大きい。読書そのものが合わない人もいる。
このうち、原則2は各種の読書調査でもこの傾向が指摘されていて、過去のエントリでも触れたことがある。シンプルに言えば、なにごともやりすぎはバランスを欠く、という話でもありますね。
読書における遺伝の影響
上記の原則3に絡んで書くと、本書の大きな特徴は、近年の行動遺伝学の知見をふまえて、遺伝の影響を正面から論じていることである。たとえば、家庭の蔵書冊数が子どもの言語力の相関はよく指摘されるところだが、それは環境の影響だけでなく、そういう環境を用意する両親が遺伝的に言語力が高いからでもある。遺伝と環境の相互作用を考えたら、遺伝を抜きに「純粋に環境の影響」といえるものはわずかなものになる。
これは、近年の安藤寿康さんの本でも何度か指摘されてきたことである。僕も安藤さんの本をこのブログで何度か紹介しているが、さまざまな人間の営みに遺伝が影響していることは明らかで、読書もその影響からは免れない、という、これもまあ当たり前の話である。だからこそ、個人差が大きいのだ。
読書は「できる子の加速装置」か?
この議論に関連して、読書の効果が「穏やかで長期的」なものであることと、一方で読書に向く子とそうでない子の個人差が大きいことを考えたら、読書はどうしても「できる子の加速装置」的な側面を持ってしまうようだ。読書と言語力や学力との関係として、読書に向く子は、早い時期から読書をすることで言語力が高まって読書が容易になり、さらに読むことで言語力が高まる…というループ(語彙力と読書の相互促進関係)があり、同時に「早期に言語力が高ければ学習に有利になり、それがその後の学力向上に基礎になるのでさらに学力が高まりやすくなる…というループ(言語力と学力の相互促進関係)がある(p240)。だから、遺伝的に言語力に恵まれて勤勉性が高く生まれついた子(そういう子の多くは、親にもその傾向があって環境的にも恵まれている可能性がある)が、早期から読書教育を受けることで、どんどん読書の効果が促進されていく。
一方で、すべての子がそのように長期的に読書活動を維持できるわけではない。小学1年生の段階ですでに余暇時間の不読者が15パーセント程度存在し、読む子と読まない子の傾向差は、読む時間だけでなく、読んでいる本のジャンルに関しても、小学校3年生くらいになるともっと明確になる。この個人差は基本的にそれ以降も変わらない。むしろ、遺伝的傾向は成長するにつれ発現するので、「読まない子は読まない」ままなのだ。読む子との格差は決して逆転しないのである。
「読書を諦める」という選択
熱心な読書教育活動家であれば、「だからこそすべての子に読書を!」「読む楽しさを!」と主張する論拠になりそうなデータだが、本書の結論は逆である。筆者は、読書の個人差の大きさをふまえて、「『読書を諦める』という選択肢も含めて読書教育を行う」(p250)ことを提案する。たとえば、「大人の介入によって『非読者の児童を書籍読者にさせる』ようなことが自由自在にできるとは筆者には思えない」(p65)というのが筆者の基本的な立場だ。
そもそも遺伝的に読むのが苦手な子に対して、いくら教員・司書が頑張ったところでその効果は一時的である。その教員・司書が担当する一年やそこらは読書行動が改善するかもしれないが、それが終わればまたもとにもどってしまう。成長すればするほど遺伝的特質が発現される以上、ちょっとのあいだ頑張ったところで、長期的には効果は逓減するだけである。
その人らしさをどう生かすか?
こういう筆者の結論は、ある人にはドライに見えるかもしれないし、「結局のところ遺伝なのか」と思われるかもしれない。でもそうではなくて、どんなに遺伝的特質があっても環境に恵まれなければ伸びるものも伸びないので、教育が無意味ということは決してない。また「遺伝的に読書に向かない人には何をやっても向かない」ということは、優しいとか冷たいとかいう人柄とは無関係の単なる事実だし、その傾向が年齢とともに強まることも、周囲の影響から自由になるにつれてその人らしさが前面に出てくることでもある。その事実を認めた上で教育の役割を考えることは、「その人らしさを尊重する」ことと結びつくとさえ思う。
たとえば、飯田一史『「若者の読書離れ」のウソ』によれば、不読率は未就学期から高校まで基本的に上がり続け、日本でも韓国でも中国でも一定の数値に収束する。飯田はこの事実を「当然視」することを提言しているが、そもそも読むことが人間にとって生徳的な能力ではないことを考えたら(メアリアン・ウルフ『プルーストとイカ』etc)、「およそ半数の人は大人になれば読まなくなる」ことは、読書教育が解決すべき課題というよりも、読書教育の前提なのだ。この数値を下げる(月一冊でも読む人を増やす)ことは社会全体で努力をすれば多少はできるだろうが、それでも「向かない人には向かない」事実が変わるわけでもない。
風越学園は小学生のうちからの多読読書を国語教育の柱にしているけど、そういう機会があっても明らかに読んでない子も一定数いる。本書を読むと、多読を薦めるアプローチも大切だけど、一方では、読むのが苦手な子に対しては「本をなんとか読ませる」以外のアプローチだってありえることを、もうちょっと真剣に考えるべきかなあと思う。問題は、「読むのが苦手な子」のみきわめの時期なのだが、前述の通りすでに小学1年生から読書傾向の違いは出始めており、本書によれば「小学3年生以降に徐々に判断」(p250)するのが良いのではないか、ということだ。
そういう時期に苦手な子を判断して、たとえば、別に読書だけが言語力や学力向上の手段ではないので、読書以外の方法で学力を伸ばすことを考える(筆者によると、一番学力を向上させるのは、端的に言って勉強だそうだ。これもまあ当たり前の話。でも、読書が苦手な子はたいてい勉強も苦手だからなあ…)。それも苦手なら、文字情報以外から情報を手に入れて生きていく手段を手に入れるほうが良い。「無理しないで、気楽に構えようよ」が、筆者の基本的な提案である。
個人的な感想を言えば、この基本的スタンスには、僕は共感するところがある。僕は根がまじめなので、読み書きが苦手な子にもなんとか適切なハードルを…と一人一人へのカンファランス(個別指導)をちゃんとやろうとしてしまって、「魚を木に登らせようとしているように見える」と元同僚(現MIMIGURI)のあっきーに指摘されたことがあった(下記エントリ)。
少なくとも自分の場合、そうやって子どもを真面目に悪意なく追い詰めてしまう可能性がある。負荷の見極めは難しいが、「無理なものは無理」「教育で人は変わらない」とどこかで割り切ってないと、教育なんて怖くてやってられない。
今後の読書教育を論じる基礎になる一冊
繰り返すけど、本書は間違いなく、今後の読書教育を語る上で基礎文献となる一冊だ。少なくとも、日本語で読める文献で、本書ほどこれまでの読書研究を観点別に丁寧にレビューしてくれた本はないはずである。また、それぞれの研究の読み方やその限界なども含めて一般の読書にも伝えようとしている点で、稀有な本であるとも思う。本書は、決して読書教育に関係する人の耳に心地よいことばかり言ってくれるわけではない。特に「遺伝的にそもそも読書に向かない子はいる」という話は、熱心な読書教育実践者の中には、冷や水を浴びせられる思いで読む人もいるかもしれない。しかし、読書好きの実践者の個人的な思いとは別に、事実は事実なのだ。そういう当たり前の、読書をめぐる「穏当な事実」に改めて立ち帰らせてくれる本で、僕らはここから出発するしかないのだと思う。
[ad#ad_inside]