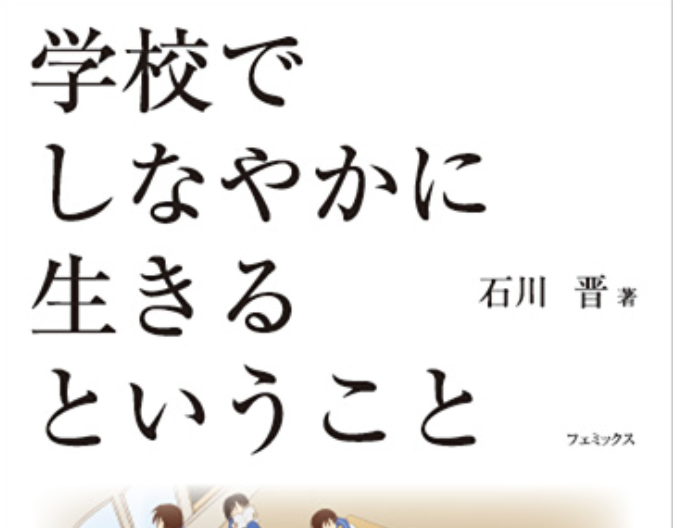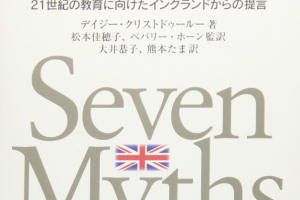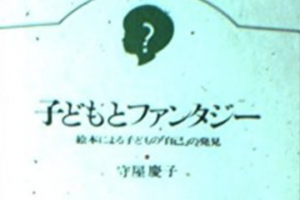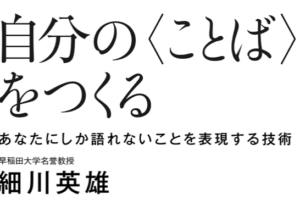北海道の上士幌町にある中学校で国語の教師をされている石川晋さんのエッセイ集。肩の力を抜いた闘いの記録である。
[ad#ad_inside]自然体の授業をする公立中学校の先生
個人的なことを書くと、僕は2012年の冬に、北海道まで石川さんの授業を見学に行っている。一番の動機は、公立中学校で、しかも北海道の学校で(この「しかも」は北海道に失礼か)ライティング・ワークショップをやっている先生とはどういう先生なのだろうと思ったのだ。当時の僕は、ちょっと前に過労で体調を崩していたこともあり、それまで熱中していたライティング・ワークショップを、少し距離を置いて見てみようとしていた時期のことだった。東京周辺を離れたことのない世間知らずの僕が「最寄のバス停や電車の駅からどのくらいですか」と間抜けに質問したのを笑って流して、最寄の空港まで車で迎えに来てくださった。すでに小学校で実践を重ねられていた伊垣尚人さんや広木敬子さんも同じ車に乗っていた。
石川さんのライティング・ワークショップの授業や詩の授業を見て、僕はとても好感を持った。もちろん僕と違いはあるけれど、授業を貫く思想とか、ちょっとした仕草とかが、僕の好みだったのだ。詩の扱い方、生徒を人として扱う態度、根底にある「学校的なもの」への違和感。そういう方向性が、一言で言って似ていた。おまけに、僕と違って終始肩の力が抜けていて、それも自然体でいいなあと思った。特に、ハンドベルを持参して声を出して指示する代わりにハンドベルの音で伝える場面があり、僕はそれがたいそう好きで、新年度からすぐに真似をして使うようになる。
全編が闘いの記録
それはさておき、このエッセイ集には、そういう石川さんの自然体の思想や生き方が、酒飲みの席のとなりのおじさんの話のように軽妙に語られているのだけど、一方で、その彼が、自分のしなやかさを保つためにどれほど遠くを見て、入念に準備をし、計画を張り巡らしているのかが、随所に伝わってくるところに、静かな迫力を覚える。
例えば、いらいらした生徒が一人でこもれるように、教室のレイアウトを変える時。
そうすると、管理職がやってきて、「見えない場所ができると生徒指導上ちょっと…」。…ニコニコ笑って、「すみません、すみません」といいながら、さらにハムスターを飼い、プランターでイチゴを植えて収穫したりしながら…ぼくもなんとかしなやかに生きるための対策を考えつづけながら教室の中に立っている。(p.14-15)
特定の生徒を頭に思い浮かべながら、たくさんの学級通信を発行するとき。
ぼくは実は、学級通信のすべての号を、同僚全員に配付している。各種研修会などの研修資料もすべて配付している。事務の方には、「通信の号数が多くなるので、紙は自分で持ち込みます」と、年度当初に話し、実際にそうしている。先手必勝とすべてを仲間に還元する姿勢とで、自由に学級通信を出す権利を担保してきたのである。(p.34)
しなやかに生きるために、こういう、一つ一つの泥臭い「政治」を実に丁寧にやっているのだ。同僚だけでなく保護者も巻き込んだこうした政治が、何事も前例踏襲主義のはびこりやすい学校という場でいかに時間がかかるかは、想像に難くない。エッセイの中では時折その「闘う」姿勢が露わになるが、全体を通じては授業と同様、肩の力を抜いた筆致で語られていく。そうであっても、これは全編が闘いの記録である。別に同僚や保護者と闘っているわけではない。彼が闘っているのはもっと別のものだ。
今と十年後の町を見つめて
このエッセイを読んで一番印象的なのは、まずはこの「政治」の話だが、同時に、一見飄々と政治をおこなっていく彼の、日本の教育や、街そのものの将来を見つめる冷徹な視線も心に残る。こういう視線がまずあって、
いまや日本の教育は、いかにハプニングをなくすかということに、教師も保護者も生徒自身さえも腐心するようになり、結果、限りなく息詰まるつまらない場所に堕していきつつあるわけである。(p.33)
育児の基準も平均点主義かあ (p.46)
田舎の教師は十年後の町の地盤沈下が見えるんですよ。そこを子どもたちでなんとか話し合いができるようにするのがぼくの仕事だと。で、あんなふうに教室のレイアウトをした。(p.163)
こうしたボソッとした呟きのようなところに、この人が見据えている日本の現在と将来が見える。それは、北海道の田舎町だからこそくっきりと見えるものでもあるが、同時に衰退していく日本全体の問題にもなるはずだ。彼が対峙する闘いの相手は、こういう問題群である。
読んでわかる自分の子供っぽさ
この本を読んで、僕は自分の子供っぽさを少し恥じるような気持ちになった。僕と石川さんは、実のところ全然似ていない。確かに、やりたいと思う教育、シンパシーを覚える教育の姿は似ているかもしれない。でも僕は、結局のところ自分の人生が楽しいことが大切なので、自分にとって「より楽しい」と感じられる環境、そういう教育がやりやすい環境を選んできた。
僕自身が中高一貫校の出身ということもあって、公立校で働くことは最初から選択肢になかったし、生徒への画一的な指導に疑問があれば、そうでない学校を。受験対策ばかりで本当の勉強を教えていないのではないかという疑問が湧いてくれば、教師が自分の裁量で自由に授業ができる学校を。僕はそんな風にして、自分にとってより心地よい、言うなればより特権的な環境を選んできた。もちろんそこでも政治はあるが、授業にしても何にしても相当やりやすいことに変わりはない。
一方の石川さんは田舎町の教師であることにこだわり、その町の十年後を見据えながらその撤退戦を生き抜く生徒たちを育てることを自分の「仕事」と任じている。僕が東京の中高一貫進学校で、いわば特権にあぐらをかいてライティング・ワークショップをやるのと、石川さんのように北海道の公立校で覚悟を持って、自分が身を置く仕事の場所で泥臭い政治を続けてライティング・ワークショップを実施するのとでは、覚悟にも、理念にも、そしてそれを実現させる上での苦労にも、もう雲泥の差がある。僕の性格も生き方も経験不足も今さら変わることはないと思うが、それでも彼のような仕事をする人には深い尊敬の念を覚える。
息苦しさを感じさせない筆致の、重い内容の本
内容的には実は息詰まるほどに重苦しい問題を扱っている。それなのにそれをあまり感じさせないのは、筆者のキャラクターと、豊かな芸術的素養に支えられた筆致のおかげだろう。その意味で、このバランスはこの人でこそ表現できた本なのではないか。短くて、さらっと読めてしまう、重い闘いの本。新人の教師よりも、ある程度経験を積んで「政治」の難しさを肌で知った年齢の教師が読むと、その「闘い」の意味が一層感じられるのではないかと思う。
[ad#ad_inside]