ご自身も不登校の当事者だった貴戸理恵さんは、不登校問題を軸に「コミュニケーション能力」と言われるものについての論考を書き続けている。『「コミュニケーション能力がない」と悩む前に』で、本当は人と人の間に発生するはずの「コミュニケーション」が、個人の能力として捉えられることで生じる苦しみを描いていて、とても興味深かった。
今回読んだ『「コミュ障」の社会学』もそうした「コミュ力」研究の延長上にある著作だ。僕自身、自分を「コミュ障」と自嘲する一人なので、興味深く読んだ一冊だった。
「コミュニケーション能力」と「コミュ力」
国語の先生なのにコミュ障なの? と思う人がいるかもしれないが、そもそも学校で扱う「コミュニケーション能力」と「コミュ力」は全くの別物だ。前者は、プレゼンテーション、ディベート、討論などのフォーマルな場でわかりやすく話したり書いたりする言語運用能力をさす。この意味での「コミュニケーション能力」なら、僕はまあ平均以上の水準で持っている。論理的に筋道立てて話すことも、相手の議論の論理的な整合性をチェックすることもできる。
しかし、ご存知の通り、それは広義の「コミュニケーション能力」ではない。とりわけ「コミュ力」と呼ばれるものと、学校国語的な「コミュニケーション能力」には大きな差がある。この本で筆者は「コミュ力」を「学校の休み時間などに可視化される、周囲の空気を読み、ノリに合わせて盛り上がる能力」と定義しているが、「周囲の空気を読む」とか「ノリに合わせる」とか「盛り上がる」とかは、僕には苦手で、近寄りたくないことなのだ。
「コミュ力」がある/ないとはどういうことか
この本の魅力の一つは、「非社会性の社会性」という概念を切り口に、「コミュ力がある/ない」ことはどういうことか書いていることである。「コミュ力がない」=「社会性がない」のではない。もしも本当に社会性がないのであれば、自分に社会性がないことに苦しみ、自嘲することはできない。コミュ力がない人は、自分が非社会的な存在であることを自覚する程度の社会性は持っている。そして、「社会に適合できない自分」をメタに見たり、そんな自分が周囲からどう見られているかを意識することで、ますます自分を追い込み、ぎこちなくなり、疲れていく。社会性があるがゆえに、社会性がない自分に苦しむのである(いやあ、この辺は本当にわかりみが深い話ですなあ…)。
一方で、「コミュ力のある」人は、そういう社会にうまく適合するし、社会に働きかけて自分の「ノリ」を尊重させる空気を作るのがうまい。そしてコミュ障との大きな違いとして、空気への適合という極めて作為的な所作を、自然に(=作為がないように)やってのける。作為がないように自然に振舞える人たちにとっては、コミュ障の人が必死で周囲の空気を読んで合わせようと頑張っている姿そのものが滑稽で、しばしば嘲笑の対象になる。
「異文化に対する寛容性」という別の軸
こうしたコミュ力のある人とコミュ障の対立軸は、なぜ生じるのだろう。筆者によれば、それは「同じ空気を共有する社会に限定してコミュニケーションを考えている」からである。もしも、空気を全く読めない、異文化の他者がいることが当たり前の社会であれば、違いを明示的に言葉にして伝え合う作法や、自分がどのような人間か、相手がどのような人間かを伝え、聴き合う作法が必要になる。そこでは、同じ空気を共有する空間でのみ通用する「コミュ力」を磨いてきた人は、空気が異なる異文化を前に沈黙してしまうかもしれない。逆に、「コミュ力がない」とされる人たちが、そこでは別のコミュ力を発揮するかもしれない。
別の社会のあり方を想定することで、「コミュ力がある/ない」という対立は、偽の二項対立であることがわかる。問題はコミュ力のあるなしではなくて、まして、コミュ障の人がどうすればコミュ力を持てるようになるのかでもなくて、異なる社会性を異なる配分で持つ僕たちが、互いに安心できる場をどう作るのかにあるのだ。
「コミュ力」を切り口に、社会の生きづらさを描く
筆者はこうして、「コミュ力」を切り口に、私たちの社会がどのような社会なのかを描いていく。主なターゲットとなっているのは不登校支援だが、話題はさまざまだ。「コミュ力」という俗語の意味、不登校の論じられ方の変化、不登校児たちのその後、支援者たち、対話することや書くことの意味、筆者が当事者として経験した不登校、娘の不登校…。13年間書きためた論考をまとめたため、一つのロジックで強く束ねられてはいないし、文体も話題も硬軟織りまざっている。特に後半は夫婦関係や介護など、一見遠い話題のエッセイもある。
アマゾンでのレビューがいまいち高くないのはそういう構成のせいもあるようだけど、さまざまな話題が副旋律となって主旋律をより豊かに読ませる本書の構成が、僕はとても好きだ。こういう話題があることで、「コミュ障」「不登校」が、特定の人の話ではなく、もっと大きな広がりを持つ話題であることが伝わってくる。ページを行ったり来たりすると、思わぬ共鳴もある。筆者にとってこの問題がライフワークであることもわかる。
コミュ障とは何かを考える本というよりも、コミュ障という存在を生んでしまう僕たちの社会はどのような社会なのか、そして、全ての人の「生きづらさ」を軽減する社会はどのような社会なのか。考えるきっかけになる一冊だと思う。

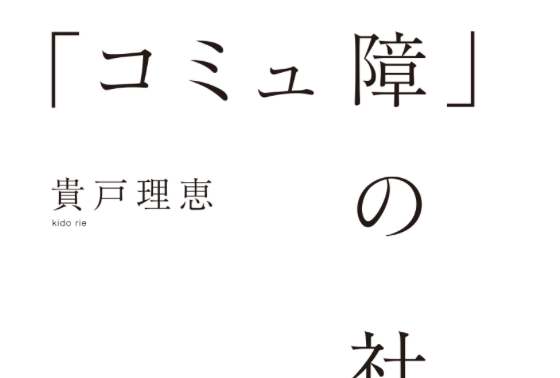



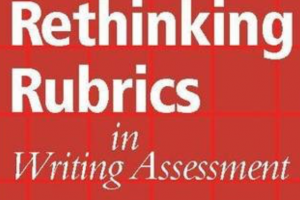




![[ITM]第3版の鍵概念、hand over(手渡す)という考え方](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/511NgcY9IsL._SL160_-36-50x50.jpg)

![[読書][ブクログ]道徳教科化のいま読み直したい、松下良平「道徳教育はホントに道徳的か?」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2019/03/スクリーンショット-2019-03-11-23.40.39-50x50.png)