今更ながら清岡卓行「手の変幻」を読んだ。「今更ながら」と書いたのは、高校1年生国語総合での評論の定番教材「失われた両腕」(ミロのヴィーナス)の出典となる本だからだ。どうやったらこういう文章が書けるのだろうと思わせる、表現の力強さを感じさせる「手」についてのエッセイ集である。
変幻自在の「手」の姿
「手の変幻」というタイトル通り、この本ではさまざまな「手」がそれこそ変幻自在な姿を見せてくれる。教科書に載っている、失われているからこそ美しいヴィーナス像の手。人間の未来を思いまどろんでいる、広隆寺の半跏思惟像の手。萩原朔太郎の詩に登場する、鉱物的で無機質な手。バレーボールの女性選手たちの、過ぎ去ろうとする青春への哀愁を漂わせる手。客観的な生の美しさを、消え失せるような儚さで伝えるピカソのキュビズムの手…。彫刻、絵画、詩、映画、体操、さまざまな芸術の形態に見られる「手」の一瞬の表情を、筆者は言葉で切り取っていく。
言葉の不思議な力強さ
この本を読むと、こんなにも手について形容する言葉があるのか、と驚く。同じ対象を見ても、僕では到底こんな文章は紡げない。よくもまあ、と感嘆しながら読み進めていくことになる。
言葉の狭い意味で論理的な文の進め方ではない。「いわば」という比喩の言葉や、「ふしぎな」という形容が各所に見られる文章で、筆者自身も、自分の文章があくまで自分ひとりの感じ方を示すものであることは承知しているはずだ。それなのに、筆者の文章には、誰だってそう感じるに違いないと思わせるような、不思議な力強さがある。例えば、教科書に掲載された文章「失われた両腕」の、
ミロのヴィーナスを眺めながら、彼女がこんなにも魅惑的であるためには、両腕を失っていなければならなかったのだと、ぼくは、ふとふしぎな思いにとらわれたことがある。
という書き出しや、東京オリンピックの選手たちについて語りはじめる、
自分の勝利に羞恥を感じている人間の姿は、なぜかしら美しいものである。特にそれが精根をかたむけたスポーツの競技ののちに眺められるとき、そこには、ふしぎに精神的な爽やかさが漂っているかのようである。
という書き出しは、どちらにも「ふしぎ」という留保の表現はあるものの、同時に「こうでなければならない」と僕たちに確信させるような、一種の力強さをも感じさせる。
論理ではない、表現による説得力
この本には、たしかに説得力がある。たとえば「ミロのヴィーナスで失われたものが両腕でないといけなかった理由」など、もちろん実際には存在しないのだけど、筆者の文章を読み終える時には、「なるほど失われたのは両腕でないといけなかった」という気になってくる。ここに書かれているのは、あくまで筆者の感動や、筆者にとっての「意味」であるにすぎない。けれども、それが普遍的な説得力を持っている。その普遍性をもたらすのは、論理というよりも、様々なレトリックを駆使した筆者の表現の力だ。
こういう文章が、教科書で「評論」のジャンルに入っているのは興味深い。別にこれは「随想」でもかまわないし、狭い意味での「論理的文章」かと言われると首をかしげるところもあるのだけど、人に自分の考えを伝えることの成否が、論理だけでなくて表現にも大きく影響されることを示しているからだ。
国語教師にとっては表現の力をあらためて教えてくれる一冊だし、それ以前に、筆者がつくりだしていくさまざまな「手」の表情に、見惚れてしまう一冊でもある。こういう文章、書けるようになってみたいなあ…。



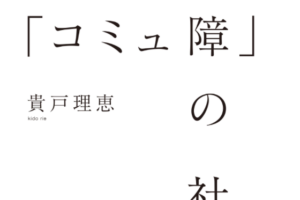






![[読書]今月はお仕事系以外もノンフィクションの月!2024年7月の読書](https://askoma.info/wp-content/uploads/2020/02/book-2388213_1920-50x50.jpg)

![[2019年度版]夏休みにどうぞ!小学生・中学生・高校生が応募できる作文コンクール](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/04/artistic-2063_1280-50x50.jpg)