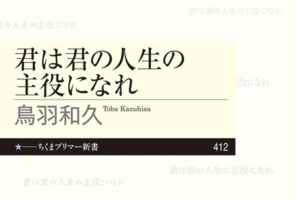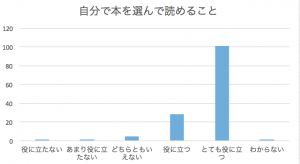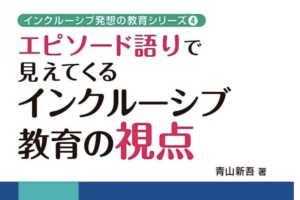幅允孝『差し出し方の教室』は、「本を人に差し出すこと」を生業とするブックディレクターの幅允孝(はば・よしたか)さんが、様々な分野の「差し出し手」へのインタビューや対談を通して、本の「差し出し方」について改めて考える一冊だ。学校の教師や学校図書館関係者をはじめ「子どもに本を差し出す」ことについて考えるときの思考の補助線になる。また、学校教育ど真ん中じゃない本から得られるヒントの多さを感じた本でもある。本について考える言葉も散りばめられていて、楽しく面白い一冊です。
[ad#ad_inside]読むきっかけは、読書家の時間の「悩み」
僕がこの本を手に取ったきっかけは、「読書家の時間」(リーディング・ワークショップ)がらみの悩みにある。読書がもともと好きな子や、そうでなくてもカンファランスでこちらの提案に乗ってくれる子はいいのだけど、読書が嫌いな子、こちらの提案も「嫌だ、やりたくない」と拒否する子に対してどう手を打つのがいいのかな…というのが僕の課題の一つだった。そういう子は、僕が直接アプローチしてもうまくいかないことが多い。ではどうしたら…というのを、よく考えている。
「気がついたら読んでいた」を作る工夫とは?
そんな中で出会った筆者の本のプロローグに、こんな言葉があった。
僕が本を届けるときに最良だと思える状況は、「読め、読め」と圧力や切迫を感じさせて読んでもらうのではなく、「気がついたら読んでいた」という状況をつくることです。(プロローグ、Vii)
まさにまさに。じゃあ、どうやってそんな状況をつくるのだろう?そのヒントを求めて、筆者は、いろいろな分野の「差し出し手」と対話をする。博物館の展示デザイナー、動物園の元園長、ウェブデザイナー、ワインソムリエ…。こうした人たちとの対話の中に、「差し出す」ヒントを探っていくのだ。ね、面白そうでしょう?
出会うための環境をつくる
その詳細を全てここに書くことはしないが、たとえば、僕にとって直接的に発見したことが一番多かった章「博物館での差し出し方」では、東京国立博物館の木下歴青さんが、差し出す空間や環境の影響の大きさについて言及していた。
対象に出会うための空間やその気配の作り方、鑑賞者がそこに至るまでのストーリー作り。でも、余白をしっかり確保して自由にみてもらうこと。そして、鑑賞者が対象と向き合い、いつの間にか時を過ごしてしまうような環境づくりや、そのために鑑賞者の体をリラックスさせるための空間をどう作るか….。こうした話題の中に、ブックディレクターとしての筆者の知見も色々と盛り込まれている。たとえば、POPについては筆者はこう述べている。
POPの量を調整し、受け手が自由に本と本の間を泳げること。その余白の調整を、本棚のユーザーによって変えていくことが僕の仕事では求められます。若く読書に慣れていない方が多い本棚では、POPを多く作成し、しかし一つひとつの文字量を少なくします。一方、読み慣れた読者が多い場所では、POPの総量を減らすだけでなく、何版目なのか?とか装幀家の名前など、気にする人は気にしているポイントを抽出するようにします。そうした、細やかな試みを積み重ねることで、受け手の本を手にとるモチベーション喚起ができると思っています(p28)
本を出し出す場所の環境や情報について考えることは、風越の校舎の設計を生かすことともつながってくる。偶然の出会いがあるように設計された風越の校舎、そしてその通路のあちこちに展示されている本…その意味をちゃんと考えた時に、僕たちにアプローチできることはまだまだありそうだな、と感じた。
また、時間という観点では、デジタルコミュニケーションについて話をしているときの次の話が印象的だった。
僕が最近気になっているのが「読書空間のアスレチック・ジム化」です。どういうことかと言うと、「ここでは読むぞ」と決めて、時間と場所を整える。2時間なら2時間、スマホの電源もオフにして、集中できる環境を用意する。…時間のフレーミングが決まっていると、大人も子どももびっくりするくらい集中して本を読むんです。一日中オープンして、朝から晩まで居てもよいシステムを採用していたら、途中でスマホを見たり、昼寝をしたり、休息をしたりして、こんなに集中して読書する人が集まる景色をつくることができなかっただろうなと思いました。(p99-100)
これもとてもわかる話で、読書家の時間が「読むための時間」として確保されている意味も、こういうところにあるのかも、と思った。
自分を消して「いってらっしゃい」をする差し出し手
一方、差し出し手としての自分について考えた時には、ソムリエの永島さんの話が面白かった。ソムリエ(ご本人は「ソムリエ」ではなく「サービスマン」と名乗っている)の永島さんが、若い頃の自分と今を比較してこう語っているのが印象的だったのだ。
若い頃は、お客様に提供する以上はワインに関しても、そのすべてをわかっていないといけないと思っていました。でも、それって突き詰めていくと、酸度だったりpHだったりの話になってくるんです。
…でもそれは、お客様に対して全く有効ではありません。人の魅力とかカリスマ度を数値化できないのと一緒で、ワインもそういうものです。(p138)
もう若くない僕だが、それでも、差し出す本について「そのすべてをわかってないといけない」欲望から自由なわけではない(まあ、無理という諦めはあるにしても)。それだけに、そこから軸足を移したという永島さんの話は面白い。
お客様一人ひとりにベストな状況でワインを楽しんでいただける時間を提供することが大前提で、むしろ僕はワインの前で自分をどれだけ消せるかがすごく大切だと思っています。恥ずかしながら、若いときには自分がこれを選んだとか、自分がこれを寝かせたとか、そういうエゴみたいなものがありました。ところが、自分を消して「本当に素晴らしいお酒ですから、どうぞ(いってらっしゃい!)」と差し出せるようになってからの方が、お客様から店やサービスを評価していただけるようになったんじゃないかなと思います。
十数年前からやっていることは変わりません。でも、差し出し方が変わってきたんだと思います。すべてにおいて「いってらっしゃい」ができるようになったと思いますね。(p139)
これ、自分に置き換えるとどういうことなんだろう、と思いながら読んだ箇所だ。読み手(つまり子供達)一人ひとりにベストな状況で読書を楽しんでもらえる時間を提供することが大前提、という気持ちになれているかな、いや、それよりも授業のしやすさを優先してるなあ…とも反省した。とはいえ、子どもに自由に場所を選んでもらうと結局おしゃべりやゲームしちゃうのも現実だよな、とか、「いってらっしゃい」をするってどういうことだろう、とか、色々と考えてしまう。
ハッとしてホッとする、幅さんの読書論
本書では、こんなふうに周辺領域の「差し出し手」との対話を通じて、本の差し出し手としての自分について色々と考えられるのだが、同時に本の差し出し手としての幅さんの、読書についての考え方(読書論)が、ハッとするものもあり、ホッとさせてくれるものもあって、とても良い。
- 本は自分のペースで読んだり、読まなかったりできるので、主体性を持ってコントロールでき、自らの痕跡と接合しやすい気がします。(p91)
- 「良い本を教えてください」って言われていつも困るんです。ないですもん、良い本の定義とか。悪い本だってありません。人によって感じ方、受け取り方は違うし、それは食欲のように刻々と変わっていくものなので。今のあなたに「合う」「合わない」という言い方しかできません(p148)
- 紙の本は五感を総動員して向かうのが一番の醍醐味(p255)
- 本を読まない自由を謳いながら丁寧に本を差し出すくらいがちょうどいいんじゃないかなと思うんですよね。(p258)
- 誰かが今まで生きてきた時間。好きで好きで、ずっと何かを愛でてきた時間。それが、その人の記憶の核となり、差し出された1冊の本と結び目をつくる鍵穴になると思っています。(p268)
- 僕は本の読み方の自由を支持しています。人はあるときは集中して、あるときはぼんやりしながら、またあるときは眠い目をこすりながら、教室で、電車で、ベッドで、お気に入りのソファで、公園で本を読むのでしょう。その色とりどりの読書時間に対して、誰かが何かを指摘しジャッジするなんて、ずいぶん野暮なことのように思えます。(p307)
他のメディアに比べた時の(紙の)本の特徴をしっかり理解しながら、そのポテンシャルを引き出すような時間と空間を作れたら理想だ。そのために、何をしていくといいんだろう。
「自発的に読んでいた」場を作っていこう!
最後に、改めて大事なことを。筆者はこう書いている。
本を手に取ってもらう環境をつくるときも、「読んで、読んで!」という差し出し手の想いが、受け手にとってのプレッシャーになってはいけないといつも考えています。…繰り返しになりますが、僕は「気がつけば、自発的に読んでいた」という本の差し出し方が、最も理想的な本の伝え方だと思っています。(p70)
本当にそうである。僕は時にプレッシャーをかけながら読んでもらう立場だが、やはりそれは理想ではない。「読もうよ!」「読め!」という台詞が出た途端、それはもう幸福な本との出会いとは言えないのだ。
僕は「読書文化」を風越に根付かせたいと思っていて、それをこのブログにも書いてきた。そして、まだその道のりは遠い。「読書文化がある」ことをもう少し具体的に書くと「気がつけば読んでいた子がたくさんいる状況を作る」ことでもある。そして、そんな状況は、授業内の一教師の働きかけでできるものではない。もっともっと大きくて細やかな視野が必要なものだ。
今回、本書を読むことで、「読書文化を作る」に向けてのヒントをもらえた気がするし、何よりも風越の校舎の環境をうまく活かす意識を持てるようになった。風越の回遊型空間を活かした、本との出会い方のデザインが、きっとあるはずなのだ。そして、そこにふさわしい「差し出し手」としての僕の振る舞い方も。本当だったら幅さんに風越の校舎を見てもらって色々教えてもらいたいくらい。でも、この校舎で日々過ごしている同僚たちと相談しても、きっと良い活かし方が見えてくると思う。新年度に考えたいことがまた増える、楽しみな読書体験だった。
[ad#ad_inside]