『学び合い』(二重かぎかっこ学び合い)の実践者である高橋尚幸さんの『流動型『学び合い』の授業づくり』を読んだ。『学び合い』自体にはあまり好意的ではない僕でも読んで得るところの多かった本なので、メモを残しておきたい。
[ad#ad_inside]個人ではなく集団に働きかける
この本からうかがえる高橋さんの特徴の一つは、徹底して個人ではなく集団に働きかけているところだと思う。個人を褒めないで集団を褒める、個人を注意しないで集団に呼びかける。例えば、全員での課題達成ができなかったら誰かを注意したくなるところでも、そうはしない。良い関わりをしている子がいても直接その子を褒めるのではなく、集団の中での効果を考えて(必要であれば)褒める。こういうスタンスは、もしかして集団づくりや学級づくりに力を入れている先生たちの間では当たり前なのかもしれないけど、その方面への関心も技術も薄く、授業でも1対1の関わり(カンファランス)を重視する僕にとっては、高橋さんの徹底ぶりが興味深い。
子どもは大人と同じように有能で、愚かである
僕が一番勉強になったのが、高橋さんが子ども集団の(というか人間集団の)愚かさをちゃんと視点に入れて、長期的な視点で集団を育てていること。人間は動機づけられればそれだけで前向きに持続的に学習できるほど単純な存在ではない。面倒くさがりだし、飽きっぽいし、他人の目を盗んでずるいこともする。そういう人間の「愚かさ」や「思うようにならなさ」に合わせて、高橋さんは柔軟に計画を修正してゴールに進んでいく。調子よく進んでいたクラスも、3ヶ月もすればトップランナーが油断する。仲良しグループの中にいようとする。いつも他人ばかり教えていた子が飽きてくる…。そういう状況に対して高橋さんがどんな手を打つかが、本書では極めて具体的に、生き生きした子どもたちの様子も交えて描かれている。何か問題が起きた時に、僕ならつい「その子の」問題として捉えがちなところを、高橋さんは「集団であれば起きて当たり前」の問題として捉えて、対応する手を打っていく。その手並みが鮮やかだ。
高橋さんを支える原則はとてもシンプルなのだ。彼の判断は「子どもは大人と同じように有能で、愚かである」という子ども観に基づいている。だから、教室で起きることをしばしば大人の仕事や職員室の風景に置き換えて、起きていることの意味を探り、どうしたらいいかを考えていく。そして、この職員室の比喩は、僕たち読者にも有益だ。子どもたちが異なる教科を同時に学ぶことの「自然さ」が、職員室の比喩を通して見えてくる。
高橋さんの『学び合い』は最終的には異学年での『学び合い』や、時間割も含めて子どもが決める流動型『学び合い』にまで発展する。そこでも、例えば異学年『学び合い』でも「コンテンツ」を学び合うのではなく「学び方」を学び合うという、鮮やかな視点が示されている。「ゆるやかで多様なつながり」や「自己モニタリング」の経験を重ねながら、1時間の一課題の『学び合い』からここまで進んでいく、その手並みには感嘆した。
根っこにある「一人も見捨てない」信念
高橋さんのこのような授業づくりの根っこに「一人も見捨てない」信念があり、その信念が東日本大震災の経験に支えられていることも、本書では書かれている。ここも本書のハイライトのひとつ。そう軽々に使えるものではないはずの「一人も見捨てない」という言葉は、多用されるとかえって「軽さ」を感じてしまうが、東日本大震災の経験に裏打ちされた高橋さんの言葉にはその軽さがない。この「一人も見捨てない」信念こそが、個ではなく集団への働きかけが最善であるという判断や、その具現化としての『学び合い』に繋がっていくのだろう。「一人も見捨てない」信念と、「愚かさ」も視野に入れたドライな人間観の両方が、高橋さんの実践を支えているのだと思う。
さて、自分には、彼のような信念はあるのだろうか。僕はそもそも、自分が好きな読書や勉強を続けていくことと生活費を得ることの交点として教員という職業を選んだデモシカ人間である。今でも授業のあらゆるプロセスの中で予習が一番楽しいし、今後も楽しく学び続けられたらいいなというのが一番で、「一人も見捨てない」というような信念は…ないな…。正直すぎるか。いやまあ、最近では自称するほど実は子ども嫌いじゃないな、とは思うんですけど、それでも「一人も見捨てない」とまでは思えないなあ…。
高橋さんと僕はちょうど同年(どちらも1977年生まれ)ということもあり、彼我の違いを色々と感じながら、感嘆したり、自分とは違うなあと思ったりしながら、楽しく読んだ本だった。そして、概ね、自分の未熟さを感じながら読んだ(40歳を超えて未熟というのがダメなら、不完全さ、でもいい)。『学び合い』の人ではない僕は、僕の個性を活かして成長していくしかないのだけど、学ぶところの多い本である。
[ad#ad_inside]
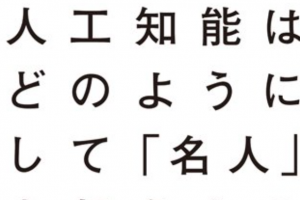


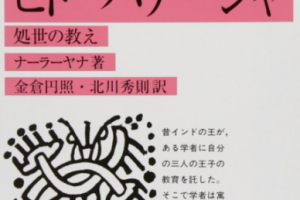


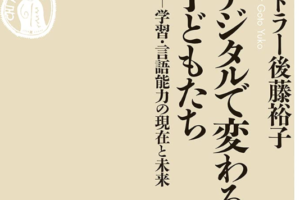

![[資料]勉強になります、国立国語研究所言語学レクチャーシリーズ(試験版)](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/04/10a827de7599454501520b5141cf4217-50x50.png)

![[読書]子育て中の親、幼稚園&小学校の先生は必読! 今井むつみ「親子で育てることば力と思考力」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2020/04/078719b8b1317ed69f561b210290049f-50x50.png)