読書記録を振り返ると、2020年は自分の読書傾向の変化がはっきりと出た年だった。高校現代文教員だった頃によく読んでいた評論系をほとんど読まなくなり、代わりに児童書が一気に増えた。読む対象が児童書中心になったので読む冊数は増えたけど、通勤電車での黄金の読書時間がなくなり、家での時間のゆとりもなくなったので、読む時間は減ってしまった。うーむ、とは思うけれど、まあ仕方ない。読んだ本の中から、それぞれジャンル別に5冊ずつ記録して、2020年の読書のまとめにしたい。どれも、僕の個人的な読書記録で8点〜9点以上の好きな本ばかり。合計15冊のお薦め本リストです。
[ad#ad_inside]ヤングアダルト向けの物語5冊
今年は小6・中1の国語の授業を担当していたこともあって、小学校高学年から中学生くらいが対象になりそうな本をよく読んだ。結果として、物語系のおすすめも、児童書系ばかり。
パトリック・ネス『怪物はささやく』
読書記録を読み返して、「やっぱり物語ではこれが一番かなあ」と思えたのがネスの『怪物はささやく』。主人公は13歳の少年コナー。自分の母が重い病気にかかっている彼のところに、イチイの木の怪物が夜の12時7分に訪れて不思議な話をする。怪物の目的がわからず、またその語る物語も不思議な寓話であり、挿絵の雰囲気も相まって、暗いダーク・ファンタジーの雰囲気で進んでいく作品。ラストシーンがとても美しく、切ない。とにかく読んで!
アレックス・シアラー『13ヵ月と13週と13日と満月の夜』
アレックス・シアラーは小学生だった頃の現中3娘から「読め!」と言われていた作家で、今年になってようやく読みました。この本は12歳の女の子カーリーが、転校生のメレディスと仲良くなろうとするけど、実はその転校生は自分の体を奪われていて…というお話。「ああ、こういうお話なのかな、なるほどなるほど」と思ってからの一捻りがいい! チョコレートが禁じられた世界でチョコ密造を企む男子たちの活躍を描いた『チョコレート・アンダーグランド』とどちらを選ぼうか迷ったけど、子供特有の(40代の僕にはやや居心地が悪い)老いへの軽蔑や恐怖がストレートに出ているこっちの方を選んでおきます。シアラーは、他にも読んでみたい作家。
椰月美智子『しずかな日々』
大人になった語り手が、自分の人生のターニングポイントとして小学校五年生の夏を回想する物語。母子家庭だった「ぼく」が、学校で押田という明るい友人を得て、しかし母親がみどりさんという女性と一緒に新しい仕事を始めるために、おじいちゃんの家に住むことになる。そのおじいちゃんや押田、そして徐々に距離が離れていく母親との日々を描いた小説です。タイトル通りのしずかな日々。でも、出来事だけを追えば小5年生の「ぼく」には激動の一年であったはずその一年を「しずかな日々」として意味付け、追憶とともに語る語り口が素晴らしい。回想小説の傑作だと思います。
ナタリー・バビット『時をさまようタック』
古い本(原作は1975年刊行)だけど、読んだのは今年のはじめでした。KAIさんや岩瀬さんのブッククラブ向けお薦め本で、八月の初めの一週間が、観覧車のてっぺんのように時が止まっている….という描写から一気に引き込まれる冒頭が素晴らしい。不思議な泉の水を飲んだせいで時が止まってしまって決して老いないタック一家と、そのタック一家に出会う少女ウィニーの物語。長く生きること、周囲が歳をとっていくのに自分だけ歳を取れない人たちをめぐる、不思議なストーリーで、生きることについて考えたくなります。
辻村深月『ツナグ』
辻村深月、実は本屋大賞受賞の『かがみの孤城』しか読んだことなかったんですよ…。それで何か他にも読もうと思って手に取ったのがこれ。映画化も大ヒットしたそうで、ご存知の方も多いと思いますが、死者と生者を一度だけつなぐことができる「使者(ツナグ)」を軸にして展開される連作小説。みなそれぞれに良かったけれど、女子高生同士の関係を描いた「親友の心得」が強烈な後味だった。辻村深月は生徒も好きそうだし、2021年には一通り読んでおきたいな。この冬休みに買い込んで積んでおきます。お薦め本を教えてください。
新しい世界に出会うノンフィクションの5冊
今年はお仕事の関係もあって、ノンフィクションを読む機会に恵まれた年でした。こちらも印象深い作品に幾つも出会えたな。あー、幸せ。こういうお仕事は大歓迎。
齋藤陽道『異なり記念日』
日本語を母語とするろう者の筆者と、日本手話を母語とするろう者の妻。その夫婦の元に生まれた聴者(コーダ)の赤ちゃん、樹(いつき)さん。異なる言語と異なる身体感覚をもつ3人の暮らしが、丁寧に描かれているエッセイ集です。写真家でもある筆者の細やかな観察や、家族への愛情に溢れた筆致が素晴らしい、とても上質な一冊。読んでいて心地よいな。こういう文章が書けたら素敵。
日高敏隆『チョウはなぜ飛ぶか』
科学系の読み物からは、岡ノ谷一夫『言葉はなぜ生まれたのか』と迷ってこの本に。今さらといえば今さらな大御所・日高敏隆さんの『チョウはなぜ飛ぶか』が、今年、岩波少年文庫で装い新たに刊行されました。初版1975年だけど、チョウの飛ぶ道をめぐる問いとそれを解決していく過程や、それがさらに次の問いを生んで探究が深まっていくストーリーが今読んでもとてもスリリング。よく教科書に採録される(今はさすがにピークをすぎたかな?)のも納得のわかりやすさと面白さで、風越学園の蝶大好き少年にどのタイミングで手わたそうか楽しみな一冊。
宮下洋一『安楽死を遂げるまで』
著者が世界の安楽死の現場を巡っていくノンフィクション。最初の取材先であるスイスの自殺幇助団体エリカ・プライシックの、自分の父の自殺幇助からこの仕事を続ける信念に圧倒されるはず。また、死んでいく人のそれぞれの様子や言葉から安楽死が良いことのように感じつつも、「死は個人のものなのか」「安楽死していたらなかったその先の人生があるのでは」と考え悩む筆者の姿も印象的だった。読んで、自分もどんな風に人生を終わりたいか、妻としみじみと話してしまいました。
マイク・トムソン『戦場の希望図書館』
シリア国内のアサド政権に包囲されたダラヤで、市民がどのように秘密図書館を作り、守り、そしてダラヤ陥落とともに破れていったのかを綴ったノンフィクション。創設メンバーのアナスやバーシド、「教授」シハーダやメディア担当のマーリクが、シリアの未来のために内乱のダラヤに残り、知識を残そうとする姿や、14歳の少年アムジャドが司書長として図書館を守ろうとする姿には胸を打たれる。アサド政権の包囲網でダラヤが陥落してイドリブ県に移った後も、一部の仲間が移動図書館を継続している点に読者としては希望を抱けただけに、2020年9月の政権側のイドリブ県爆撃のニュースには胸を痛めた。多くの人に読んでほしいし、何が起きているのかを知ってほしい。
外川浩子『人は見た目!と言うけれど』
コロナ禍の中で風越の子もマスクをつけて過ごすことの多かった2020年だけど、もしかして、外見が非常に気になる思春期の生徒の中には、マスクで救われた気持ちになる子達もいるのかもしれない。本書は病気で「見た目」に大きな問題を抱える人たちを支援する団体「マイフェイス・マイスタイル」の代表である著者と、当事者とのインタビュー。外見とのコンプレックスを抱えながら、前向きに生きていこうとする当事者もさることながら、当事者とインタビュワーである外川さんの関係性が良い。これほど支援しつつ、それでもちょっとした会話で当事者を傷つけてしまうことがあること、それを受け入れつつ、より丁寧に関係を作っていこうとする外川さんの姿勢が印象に残る。このテーマでは、登場人物も重なる水野敬也『顔ニモマケズ』という本もあって、生徒に薦めやすいのはさくさく読める『顔ニモマケズ』だろうけど、個人的な好みはこっちかも。いずれ生徒にもこちらに手を伸ばしてほしい。
締めくくりは、教育についての5冊
教育系の本はけっこうブログに読書記録を書いているので、過去のエントリとかぶってしまうのだけど、改めて5冊を選んでみた。広い意味で教育を考える本と、国語教育について考えるときの本の2本立て。
岡田美智男『弱いロボット』
随分話題だった本の今さら読書。人の役に立つ有能なロボットではなく、「弱さ」をデザインすることで、人間が思わず動きたくなるコミュニケーションを生む、という発想が面白い。人のコミュニケーションが「賭け」と「受け」によって成り立つことととか、間にものを介在させることで「並ぶ関係」になるとか、なんだか教育でも成り立ちそうな話がたくさんあった。教室で一見「弱い」とみられる生徒の存在によってコミュニケーションが成り立っている現実にも気づかされる。
福森伸『ありのままがあるところ』
鹿児島県の福祉施設・しょうぶ園の施設長によるエッセイ。上手くなることを目指さずに、ただその人のありのままを認めることで、その人が持つ本来の面白さを引き出そうという理念とその実践がつづられる。前は「障害者が健常者と対等になるために技術の向上を」と考えていた筆者が、葛藤しつつ「ありのまま」の保証へと向かう様子が興味深い。過去に別エントリでも書いたように、「ありのまま」を認める福祉の論理だけスキルのでは、結局は社会に出られなくなる(しょうぶ園の利用者も、ずっとしょうぶ園に止まり、外に出られない)。だからそれを全肯定する気は僕にはないけれど、教育とは何かを考える上で揺さぶられる本であることは間違いない。
ここから先は国語教育がらみのお薦め本。
今井むつみ『親子で育てることば力と思考力』
現在、『英語独習法』がヒット中で、これまでも数々の啓蒙書を書いてきた今井先生だけど、この本は「乳幼児〜小学生の子育て中の保護者」を対象に書いたところがポイント。言語の発達が思考力を伸ばすのになぜ大事なのか、そしてどうすれば子どもの言語発達をサポートできるのかが書かれていて、実用性も抜群。親子での会話や本の読み聞かせ、読書の大切さや、会話の具体的なポイントまで、子育て中の人に参考になるように書かれています。風越の保護者にもおすすめしたいなー。
チャールズ・ピアス『だれもが〈科学者〉になれる!』
ちょっと教科教育色の強いものからはこの本を。元々は探究型の理科の授業についての本だけど、国語を他教科の実践の中にどのように埋め込んでいくかという観点でも、とても参考になる一冊。風越でも何かをやる際に企画書を書くなど、実用としての書く場がプロジェクトに埋め込まれているのだけど、まだまだこれから。のプロジェクトの中にどう言語活動を埋め込んでいくか、もっと頑張っていきたい。
ナンシー・アトウェル『イン・ザ・ミドル』
最後は思い切り自分が関わった本だけど、かつて翻訳した本を、実は今年も何度か読み直した。主に、評価の仕組みについて考える時が一番多く、実際に、風越での僕の授業の評価は、アトウェルのやり方にだいぶ倣っている。なるほど、こうすれば力がつくだろうということが、前よりも実感を持って感じられてきた。授業をすればするほど、アトウェルの徹底ぶりや教えることへの情熱やこだわり、多様な働きかけをするカンファランスの質の高さが見えてきて、どう考えても追いつけそうにないのだけど、それでも偉大な先達の背中を追いかけるのは楽しいもの。来年もまたどこかで集中して読み直す時期が来るのだと思う。読者の方も、未読でしたらぜひお読み下さい。
[ad#ad_inside]


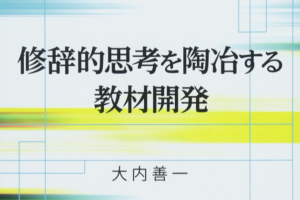
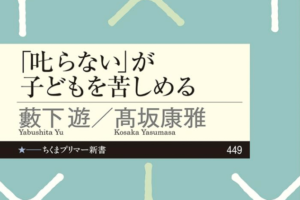




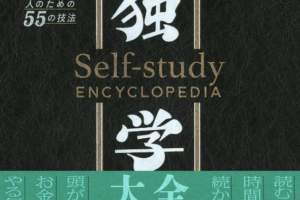
![[読書]「言葉が世界を作る」ことを改めて考えさせられた、2018年11月の読書。「物語としてのケア」はお勧めです。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2018/12/スクリーンショット-2018-12-05-22.34.12-50x50.png)

