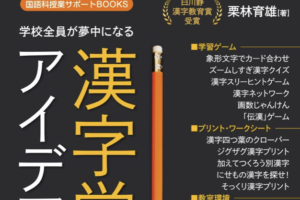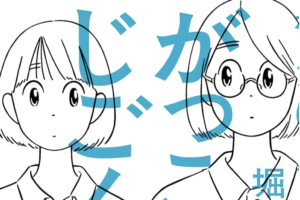フランクルの『夜と霧』を読んだのは初めてではない。最初に読んだのも大人になってからだったのでそう遠い昔ではないが、「この本を読んで大学の志望を医学部に変えた」という生徒の影響で、再読もした。けれど、昨年の冬にアウシュヴィッツに行き、そしてクリストファー・ブラウニング『普通の人びと』を読んでから再びこの本を読むと、その印象にはやはり奥行きが出てくる。
[ad#ad_inside]例えば、強制収容所に到着したばかりのフランクルらユダヤ人が「意外と悪くない場所だ」と思い込みたがるという話は、アウシュヴィッツで見た「人々の生きる希望を利用して統治する仕組み」とオーバーラップする。
もう一つオーバーラップするのは、そこで描かれている人々の内面だ。収容所に入れられたユダヤ人にせよ、彼らの虐殺に関わったドイツ人にせよ、大多数の人々は自らを取り巻く過酷なシステムに押しつぶされて、変質を余儀なくされたように思える。しかし同時に、ごく少数ながら、そのような環境から我が身を守り抜いた者もいた。二冊を読むと、加害者の側にも、被害者の側にも、そのような構図があったことがわかる。
人間とは、人間とはなにかをつねに決定する存在だ。人間とは、ガス室を発明した存在だ。しかし同時に、ガス室に入っても毅然として祈りの言葉を口にする存在でもあるのだ。
この有名な一節は、希望の言葉になり得るのだろうか。『普通の人びと』は、多くの人が、苦しみながらも自分を取り巻く周囲の環境に飲まれてしまったことを描いている。一方で、『夜と霧』は、周囲の環境から自分の精神の自由を守り抜いた例外的人びとに焦点が当たっている。加害と被害、大勢と例外と焦点の当て方こそ違うが、この二冊は同じ出来事を描いている本なのだ。その時、希望と諦観のどちらを見出すか、それは見るものの視点の取り方による違いに過ぎないのかもしれない。
[ad#ad_inside]