戦争になると、多くの国で職業軍人だけでなく、警察官や市井の人々が動員される。第二次大戦期のドイツでもそうだった。この本は、綿密な史料を元に、第二次大戦期に第101警察予備大隊に編入され、ユダヤ人の虐殺(ホロコースト)に関わったそういう人々が、自らの関わる残虐な行いにどう対処したのかを描いた作品だ。「普通の人びと」がいかにして大量虐殺を行えるように「適応」していったのかがよくわかる本である。
[ad#ad_inside]苦痛を受けていた多くの加害者たち
当たり前すぎて見落としてしまうことなのだけど、『普通の人びと』を読んでまず痛感するのは、多くの人々が望んでユダヤ人虐殺に関わったわけではない、ということだ。少なくとも最初のうちは。命令を与えられた時に即座に拒否して作戦から外れる者もいた(ただし、少数だった。多くの隊員は、訳もわからぬうちに「みんな残るから」「臆病者と思われたくないから」という理由で、そのまま残った)。いざ銃殺したあとでそれ以上続けられなくなる者置いた。神に懺悔する者もいれば、アルコールに逃避して中毒になる者もいた。多くの人々が自己の行為を恥じ、苦痛を感じていたのである。
洗練し、慣れていく人びと
しかし同時に、虐殺を重ねるにつれて、虐殺の苦痛が減じるように、やり方はより「洗練」されていった。虐殺場所まで強制移送する役割と実際に銃で殺す役割を分けて、後者は外部からの傭兵部隊に任せれば、実際に殺す瞬間を見ないで済む。母子を殺す時には、まず母親を殺せば、どうせ放っておけば死んでいく子どもを殺す時に苦痛を感じずに済む。そうやって徐々に虐殺に慣れていき、しまいには感覚が麻痺していく。「みんなそうだから」「自分だけ抜けるわけに行かない」「周りに男らしくないと見られたくない」…集団意識が、一つの方向へと人々を収斂させ、しまいには、最初は虐殺現場を避けていたのに、虐殺を楽しむようになる者も出てくる。第101警察予備大隊に属する人々を通して、人間は、人間の集団は、何にでも慣れていくのだということを痛切に感じさせられる。
読みながら思い出したのは、去年の12月にアウシュヴィッツを訪れた時のことだった。絶滅強制収容所の横で5人家族の生活を営んでいた所長のルドルフ・フェルディナンド・ヘス。ヘスや彼の部下たちもまた、こんな風に「慣れて」いったのだろうか。
著者のブラウニングは、第101警察予備大隊がこのような殺戮集団になった理由を分析した後で、一番最後の一行で問うている。「どのような人々の集団ならそうならないと言えるのであろうか」。本当にそうだ。集団である以上、こうした変化は不可避だったのではと思えてしまう。
今回の本は、高校の授業での「ノンフィクション系を3冊以上読む」という課題に合わせて、高田博行『ヒトラー演説』に続く二冊目として読んだもの。次は、フランクルの『夜と霧』を再読することにしたのだが、それはまた別のエントリで書くことにしよう。



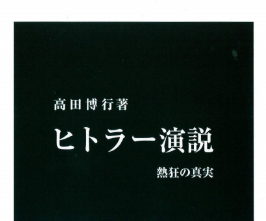


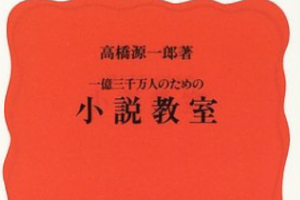
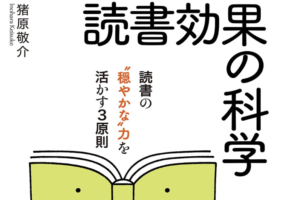





![[読書] 好きなものの「価値」の伝えかた。川崎昌平「はじめての批評」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/05/スクリーンショット-2017-05-25-19.01.34-50x50.png)