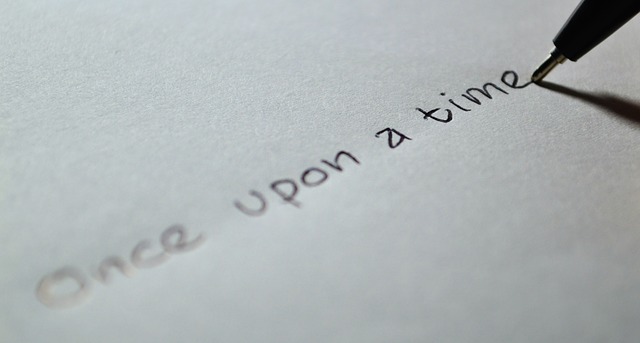ライティング・ワークショップを始めた頃、自分でもよくわかっていなかったことの一つに、次の言葉がある。
良い作品を書かせるのではなく、良い書き手を育てる。
良い書き手ってなんだろう。それは結局のところ良い作品を書く書き手のことではないのか?
[ad#ad_inside]
わからないまま始めたライティング・ワークショップ
もともと添削指導から作文教育への興味を持った僕は、そんな疑問を抱えながらライティング・ワークショップの実践をしていた。おそらく最初にこの実践に取り組み始めてから3年ぐらいは、この言葉の意味がよくわかっていなかったのだと思う。今思うと、そのせいで多くの生徒に迷惑をかけてしまったかもしれない。というのも、僕は結局のところ良い作品を書かせようとしていたからだ。
教師が目を向けるべきは「作品」ではなくて「書き手」
この言葉がどういう意味なのか、今は前よりは少し分かる気がする。この言葉は、教師が目を向けるべきは、書かれた文章ではなく、書いている生徒だということなのだ。
「添削指導」という言葉からイメージできるように、僕たち教師はつい目の前に書かれた作品を相手にしてしまう。この文章はどんなところが良いか。どこを直すべきか…。しかしそんな風に文章を相手にしていると、大事なことを忘れてしまう。それが、その作品の向こうには書き手がいるのであり、僕たちが本当に相手にすべきなのはその書き手たちだ、ということだ。
書かれた文章の背後には常にそれを書いた書き手、生徒がいる。僕たちは、その作品を通して、向こう側にいる生徒の側に立たなくてはいけないのだ。
もちろん、結果的には、良い書き手は良い作品を書くことが多いだろう。しかし常にそういうわけでもない。例えば、ある一つの作品が良いからと言って、それを書いた生徒が良い書き手であるとは言えない。逆に、その作品の出来があまり良くないからと言って、その書き手が良くない書き手だということも言えない。どんな書き手でも、新しいジャンルや表現技法に挑戦するときは、うまく書けなくて当然なのだから。
書き手の「プロセス」を見ること
作品単体で勝負するプロの書き手であればともかく、まだ若く、これから表現主体として成長する書き手にとって大切なのは、ひとつひとつの作品のレベルが高いか低いかではない。その生徒が、書き手として何をしようとして、どんなプロセスでその作品に取り組み、何ができて、何ができなかったかということなのだ。そこのプロセスを支援して、彼が次により良いプロセスで臨めるようにすること。それこそが、彼らが長い人生を表現主体として生きていくための準備期間では、大事なことである。
それを支援するためには、僕たち教師は一つ一つの作品を点として捉えるのではなく、生徒の成長のプロセスを線として見なくてはいけない。極端な話、全く同じ作品が二つ目の前にあったとしても、書き手が異なっていれば、その作品に対して教師が異なるコメントをすることも、十分にあり得る。これは作品単体だけを見る姿勢からすればとても不公平なことだが、書き手に対してアプローチしようとすれば、自然なことでもある。
カンファランスを通じて、生徒を知り、教える
こういう指導ができるためには、僕たちは一つ一つの作品を評価する基準を持つだけではなく、それぞれの書き手がどういう書き手なのか、何が得意で何が苦手で、どんなことに挑戦しようとして、何をしたいと思っているのか、そして、今どんな知識を彼に与えるべきなのか。そういうことを知る必要がある。
ライティング・ワークショップでそれを可能にするのが、「書く時間」における個別指導・カンファランスである。カンファランスは、生徒を教えるだけでなく、書き手としての生徒のことを知る時間でもある。ライティング・ワークショップにとって決定的に大事な時間だ。この実践が、カンファランス・アプローチとも呼ばれるのには十分な理由がある。
言葉の意味はわかって来たけれど、できるのはまだまだ
良い作品を書かせるのではなく、良い書き手を育てる。
この言葉にはおそらく正解というものはない。この言葉は、作文教育の教師が考えていることを映し出す鏡のようなものだろう。だから、僕もこの言葉の意味がこうだという風に決めつけるつもりはない。今の僕はこのように考えているということだけである。
そして、今の僕はこの言葉の意味を前よりはわかってきたように思うけれども、自分がそれを実践できている気はまるでしていない。この言葉はとても奥の深い言葉。今の僕は、この言葉に接近しつつある、というところだ。
[ad#ad_inside]