これはすごい本だ。名前だけは聞いていて読んでいなかった「悪童日記」。生徒が読んでいたのをきっかけに手にとったのだけど、一気に引き込まれた。賢すぎる少年たちのサバイバル。そっけない文体。そこから浮かび上がってくる「動物」としての人間の姿。どれもがひどく力強くて、圧倒されるほどの迫力を感じて読みおえた。まぎれもない傑作だと思う。
[ad#ad_inside]事実だけを描写する「作文日記」
この「悪童日記」、原題はLe Grand Cahier。「大きなノートブック」という意味らしい。その名の通り、この小説は、戦争で大きな町から小さな町に疎開してきた男の子たちが、ノートブックに書きつけた記録という体裁をとっている。
このノートブックの文体が面白い。彼らは、書いた作文をお互いに点検しあってから、「良」の評価の作文をこのノートブックに清書するのだが、そこには次のようなルールがあるのだ。
「良」か「不可」かを判定する基準として、ぼくらには、きわめて単純なルールがある。作文の内容は真実でなければならない、というルールだ。ぼくらが記述するのは、あるがままの事物、ぼくらが見たこと、ぼくらが聞いたこと、ぼくらが実行したこと、でなければならない。
感情を定義する言葉は非常に漠然としている。その種の言葉の使用は避け、物象や人間や自分自身の描写、つまり事実の忠実な描写だけにとどめたほうがよい。
だから、この日記は、少年たちの感情を交えずに、起きた出来事だけを淡々と描写していく。この文体が「悪童日記」の大きな魅力の一つである。この文体だからこそできること、伝わるものがある。それを、僕はこの物語に引き込まれるというとてもラッキーな形で知ることができた。
淡々描かれる「動物」としての人間たち
彼らの日記で描かれるのは、小さな町にいる多くの人々の姿。「魔女」と呼ばれる「おばあちゃん」、兎唇の近所の女の子<兎っ子>、その子に執心の司祭、司祭館の女中、外国人将校…。自分を「おばあちゃん」に預けた母親、そして何年も連絡をとっていない父親…。彼らをとりまく人びとの生態が、そっけない文体で明るみに出されていく。少年たちによって表面をとりつくろっているヴェールを剥がされてしまえば、そこにあるのは自分の欲にまみれて生きようとする人たちの姿だ。人を騙して得をしようとする。なんとか自分がいい目を見ようとする。嫉妬する。性欲にまみれる。小児性愛をはじめとした変態的な話もたくさん出てくるのだが、感情をまじえず突き放すような描き方のおかげか、さほど気持ち悪くなく、むしろ「動物」としての人間たちに、いとおしささえ覚える。
賢すぎる少年たちのサバイバル日記
このような人びとのなかを、少年たちは賢すぎるほどの判断力で生き抜いていく。自分が生きるためなら、あるいは依頼があれば動物や人をためらいもなく殺す。どこまでも淡々と冷静に「仕事をしていく」。なかでもラストシーンの、少年たちの一人が町を脱出するためにとった方法は圧巻だ。痛快ですらある。
少年たちのふるまいには、いま日本にいる僕たちからすると「非人間的」とも見えるものも多い。しかし、そこにはたしかな知恵があり、彼らなりの倫理も感じる。彼らは、自分が共感を寄せる人物(たとえば「おばあちゃん」)とそうでない人物を、彼らなりの倫理観で区別しているし、前者には思いやりを抱く。そして、彼らは何よりも生きることに正直だ。もし「生きる力」というものがあるのなら、この少年たちほどそれをもちあわせている子どもは、他に思いつかない。非人間的であることが、ここでは人間的であることに直結している。
淡々とした文体で人間の姿を描いた、賢すぎる少年たちのサバイバル日記。面白くて痛快。ありがたいことに、続編の「ふたりの証拠」「第三の嘘」もあるそうだ。読まねば!
[ad#ad_inside]





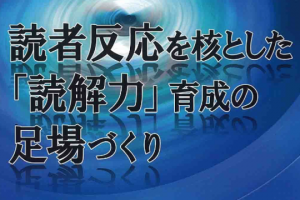



![[読書]星野文子『ヨネ・ノグチ: 夢を追いかけた国際詩人』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/515MNKTTiAL._SL160_-50x50.jpg)

![[ITM]ナンシー・アトウェル、Global Teacher Prizeを受賞!](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/aecc6745-s-50x50.png)