今年の9月はしんどかった。夏休みの短さを引きずった(=国語の勉強仲間が夏休みの勉強会をやっている時にこちらはもう仕事で行けなかったのが地味に悲しかった)のと、仕事で心身ともに余裕がなく、肝心の国語の準備が不十分なまま授業に臨むことが増えて落ち込み…が重なって、読まない、読めない日が続いた。もしかして一冊も本を読まずに9月を終えるのかな、もしそうなったらどうなってしまうんだろう、と思ったほど。後半になって、ようやく読書のリハビリができて立ち直ってきた。
前半、少しずつ読んだ向坂くじら『夫婦間における愛の適温』
そんな苦しい月の前半を支えてくれたのが、向坂くじら『夫婦間における愛の適温』。詩集『とても小さな理解のための』や、ライブ活動、詩人が教える国語塾「ことぱ舎」などで活躍中の詩人のエッセイ集である(メディア取材での情報はこちらに)。毎日本を開く気力もなく、断続的に、少しずつ読んだ。
まあ読んでいただけるとわかるのだが、面白い。最初の「オッケー、愛情だけ受け取るね」は抜群に引き込まれる書き出しから結末まで一気読みする傑作だし、結婚相手への愛や人間関係について、そこを考える?という微妙なラインをけっこう執拗に、論理的に考えている。とても気を遣って、かつ明晰な人なんだろうと思う。でも、そうやって論理でどうにもならないようなものを論理で考えている滑稽さも、どこかほのかに感じられるのも好きだ。
また、このエッセイには筆者が塾で国語を教えているシーンがときどき出てくるが、これもいい。「『言葉なんて自由なんだから好きに書けばいい』とも『正しい言葉で書かなきゃダメだよ』ともいうのは楽だが、そうしないように踏ん張っている」(p32)という自己分析は印象的だし、学習を勧めることが暴力に転化しないように気を使いつつ、必要以上に寛容に振る舞っている自分が気になるところ(p86)など、「教える」という行為の背後にある規範性(「正しさ」)から逃げずに向き合おうとしている姿勢に共感できる。
とまあ、向坂さんのエッセイを読み終えたのが9月20日。これでようやく今月の一冊目だった。
軽井沢ブックフェスティバルで出会った絵本たち
浮上のきっかけは、下記エントリにも書いた軽井沢ブックフェスティバル。ここで編集者や出版社、デザイナーなど、本に関わるいろんな人たちと出会えて元気をもらったし、とりわけ、澤美代子さんによる焚き火を囲んでの絵本読み聞かせが自分の心に染みた。詳しくは下記エントリに書いたが、『ハルばあちゃんの手』と『いのちのふね』は、ここにも書いておきたい。
この絵本の読み聞かせがとてもいい時間だったので、9月下旬は、ブックフェスティバルで出会ったおすすめの絵本から読み始めた。
いせひでこ『ルリユールおじさん』は、本の製本や修繕をするルリユールおじさんと、そこに大好きな木の図鑑を持ち込んだ少女ソフィーの物語。淡いタッチの色彩の美しい絵も、父の魔法の手に憧れたルリユールおじさんの過去も、最後のページで明らかになる少女の未来も、どれもいい。
軽井沢に美術館があるのに初めて手にとった千住博の作品、千住博『星のふる夜に』も美しい作品だ。子鹿が親から離れて池のほとりから町に出て帰ってくるストーリーの、文字のない絵本。凛とした輪郭の絵は、躍動感というよりは時間を閉じ込めたような印象がある。とりわけ、夜がだんだん明けてきて朝焼けになる色調が素晴らしく、全編が静かな雰囲気に満ちている。千住博美術館にも行ってみようかな。
ふしみみさを・作、ポール・コックス・絵『ちらかしさんとおかたしさん』、ちょっととぼけたタッチの絵と、なんでも散らかしてしまう「ちらかしさん」、それを楽しく片づけていく「おかたしさん」の生活がほのぼのしていて、読んで楽しい一冊。おかたしさんて、問題を解決するんじゃなくて、問題を問題じゃなくしちゃうタイプなのがすごい。ちなみに僕は誰がどう見ても「ちらかしさん」タイプなので、我が家の「おかたしさん」にこの絵本を見せたら「これは欺瞞。おかたしさんがいつか気づいて家を出ていくやつ」と言っておりました….笑
ベアトリーチェ・アレマーニャ『なんにもおきないまほうのいちにち』もまた、読んで楽しい一冊。退屈のあまりゲーム機を持って雨の森に出た少年「ぼく」が、ゲーム機を落としてしまって、でもそこから、自分の周りの自然の豊かさに気づいていくストーリーで、ともすると教訓臭くなりがちなところ、本当に楽しそうなのがいい。例えば、地面が、その下に広がる秘密の世界の入り口だという発想とか、めっちゃ素敵。ちなみに、「〜みたいに」のような比喩表現が多く使われてて、小学校国語のミニレッスンにも使える絵本です。
また、絵本ではないが、ブックフェスティバルに出展していた冒険研究所書店・荻田泰永さんの荻田泰永『書店と冒険』も薄くて面白い本だった。「北極冒険家のあなたが、なんで本屋を開いたの?」と聞かれることがとても多くて、それに答えるために書いた本だそうだ。荻田さんが書店運営のキーワードにしている、内山節が唱える「機能と祈り」が興味深い。代替可能な存在としての「機能」と、代替不可能な存在としての「祈り」のバランスを模索する姿は、授業とちょっと似ている。「歴史の一端を担う機能としての自分と、他ならぬ私としての祈りの自分のバランスを取ることが、私であることだ」(p24)の言葉も、国語教育史の中での自分の立ち位置を探ったり、でも、もう一方で個人性を求めたりもする自分にちょっと共通点も感じた。
双子池で小川糸「ツバキ文具店」を読む
軽井沢ブックフェスティバルで出会った本のおかげで、日々、本のページをめくる感覚が、9月も終わりになってやっと戻ってきた。そして、9月29日(金)、本格的な読書のリハビリをしたくて、北八ヶ岳へ。最近は麦草峠から高見石小屋方面に行く機会が多かったけど、この日は大河原峠から双子山を経由して双子池へ向かった。雌池の湖畔のキャンプサイトで木陰を見つけてビニールシートを敷いて、楽な姿勢で本を読む。奥まった場所を選べば滅多に人は通らないし、聴こえるのは風に揺れる熊笹の音と、蜂の羽音だけ。電波は完全に「圏外」なので、ついスマホをいじることもない(これ、「いしりょく byがまくん」の弱い僕には大事…!)。ちょっと気分転換をしたくなったら、お湯を沸かしてカフェオレを飲んだり、双子池ヒュッテでクリームブリュレを頼んだり。久しぶりに来たけど、双子池は本当に読書に最適の地だ。
双子池のほとりで読了したのは、小川糸『ツバキ文具店』。鎌倉で文具店を開く傍ら、代々続く代書屋稼業を営んでいる女性・鳩子(ポッポ)が、客のさまざまな依頼に応えて手紙を書いていく。離婚をお知らせする手紙、借金の申込みを断る手紙、絶縁状、介護中の老いた未亡人に送る、死んだ夫からの手紙…さまざまな手紙を通して、いろいろな人生の一コマを見せてくれる作品だ。そうした仕事の軸になるのは、鳩子の先代の代書屋である祖母との関係。読むことや書くことが、こんなふうに人間のいろいろな感情を浄化させ、落ち着かせるものなんだな。手紙の文字や内容だけでなく、筆記具の細部まで丁寧な配慮を重ねた手紙がたくさん出てきて、手紙を書きたくなる作品でもある。
少しゆったりした時間がとれると、我が身を振り返る余裕もできる。今月は本当に余裕がなかった。仕事でも家庭でも、特に最後の1週間は色々な人に支えられてきたのに、感謝の気持ちをちゃんと表してこられなかったな。いつも忙しくしてしまって、別れる同僚と何も話せなかったのも心残りだ。『ツバキ文具店』を読んだのだし、手紙を書いてみようか。
今月は、これが僕の読んだ本の全て。最後の双子池での読書がよくって、また読書キャンプにこようと思った。けど、10月はもう少し本を読みたい。リーディング・ワークショップ(読書家の時間)をしていれば仕事上も本は当然読むべきものなのだけど、忙しくて疲れて本が読めなくなるなんて、僕の望む生活じゃないもの。そんな日々が訪れますように。
[ad#ad_inside]






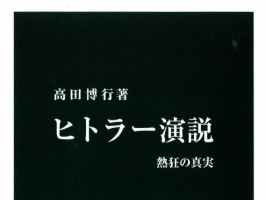

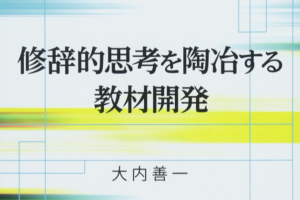
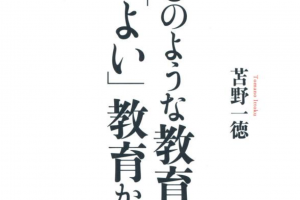


![[読書]ナタリー・バビット『時をさまようタック』&ラファエル他『言語力を育てるブッククラブ』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/11/11691e9459c307832d0a7070a74bff72-50x50.jpg)
