あすこま家の大黒柱である妻が「これを読まずに死んではいけない」とすすめる隆慶一郎「影武者徳川家康」を、結婚14年目にしてやっと読みました。これが何かのフラグにならないといいけど…というのは、さておき、むっちゃ面白い。僕は隆慶一郎全集で読んだのだけど、厚さ850ページ超を3日間くらいで読んでしまった。普通の方には文庫本を薦めます(笑)
[ad#ad_inside]とても面白い歴史のIFストーリー
この小説の魅力の源泉は、何よりも「もし関ヶ原で徳川家康が死んでいたとしたら…」というIFの発想にある。こういう歴史IFストーリーの発想、光栄の「信長の野望」や「三国志」シリーズで育った僕にはたまらないんですね。関ヶ原の戦いで、家康が忍びの「甲斐の六郎」に暗殺され、全軍の崩壊を案じた本多忠勝の判断で影武者役だった世良田二郎三郎が家康としてふるまう…という設定だ。突然天下人にされてしまう世良田二郎三郎が、戸惑いながらも覚悟を決めてその役割を受け入れる。それから、関ヶ原をどう勝利に導くか、合戦後は家康と寝所をともにしていた婦人たちをどう味方にするか…という膨大な難題と向き合うことになる。
とはいえ、面白いのが、別に世良田が「家康の代理として徳川家を支える」決心をしたわけではないということだ。生来の自由人・いくさ人であった彼にとっては、自分が生き延びることこそが第一であるので、この家康は豊臣家の崩壊や徳川家の天下統一を望まないのである。というのも、もし豊臣が滅亡し、徳川の天下統一がなれば、用済みとなった世良田は二代目の秀忠に家督を譲った後に、病死を装って口封じに殺されるのは確実だからだ。というわけで、徳川家康となった彼は、自らが生き延びるために、徳川家に早急な天下統一をさせてはいけないのである。ここに、影武者徳川家康と、早く権力を掌握したい二代目・徳川秀忠との間の暗闘が始まる。
この小説では、家康(二郎三郎)と秀忠の暗闘が軸の一つとなってストーリーが展開していく。島左近が生きているなどのIF設定が他にもあるものの、多くは、歴史資料が残っているものはそれに基づき、資料がないものは作家の想像力をふくらませて書いてあり、そのバランスがとても良い。読んでいるうちに、「確かに関ヶ原後の家康は替え玉だったのではないか。そうすればうまく説明がつくことが多い」という気になってくる。
行きのびる男のしたたかさが魅力
二郎三郎は、やがて経験をつみ、風魔の忍びを味方に加え、天下人・徳川家康としての自らの器量をも高めていく。自分ひとりだけでなく天下の平和と安定も視野に入れるようになり、一時は性格が暗く戦争の経験も浅い秀忠を圧倒するほどになる。しかし、若い秀忠も柳生の忍びを味方につけ、早く自分に征夷大将軍の座を譲るよう、そして早く豊臣家を滅ぼすよう画策し、ついには大阪の陣にいたることに成功する。史実の通り、豊臣家は滅びるのである。
これだけをみると二郎三郎はゆっくりと敗北していくのであるが、自ら大阪の陣を指揮するにいたるこの敗北の過程が、丁寧に、共感とともに書かれているので、敗北しているという感じがしない。そして何よりも、史実が語るように、徳川家康である二郎三郎は1616年に73歳で死ぬまで、関ヶ原の戦い後の16年間を見事に生き抜くのだ。そして、生き抜いた彼が、妻であるお梶の方や生き抜いた仲間たちとともに桜の木の下に立つラストシーンは、屈指の美しさ。このラストシーンを見るために、戦国末期を生き抜いた「いくさ人」世良田二郎三郎の「歴史では語られなかった戦い」を読む価値がある。
[ad#ad_inside]





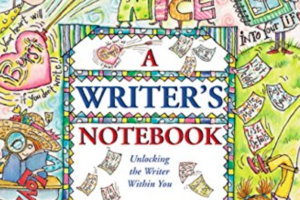
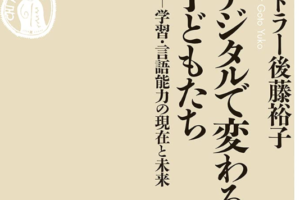



![[読書]初等・中等教育と大学の書くことの教育を架橋する本。松下佳代・川地亜弥子・森本和寿・石田智敬『ライティング教育の可能性』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2025/10/674cdde72c68b69ebe226eaebc96cce4-50x50.png)
