ピーター・エルボウ(岩谷聡徳・監訳、月谷真紀・訳)『自分の「声」で書く技術』は、「書くことがない」状態から、仲間の力も借りながら自分で書くことを見つけ、よい表現をさぐりあてるための指南書だ。「指南書」といっても、正しい文章の書き方や上手な表現テクニックを教えてくれる本ではない。代わりに、誰もが自分なりのライティング・プロセスをつくることを支援する本である。原著は1973年に初版が刊行された Writing without Teachers(本書は1998年の第二版の邦訳)。僕のブログを読むような教員の人には、この英題のほうが興味をそそるかもしれない。このエントリでは、本の紹介というよりも、自分の体験や考えも交えながら、自分にとってのこの本の意味を書いていく。そのため、「レビュー」と呼ぶにはかなり個人的な内容であるをお断りしておきたい。
[ad#ad_inside]僕とこの本の関わり
僕は、この本は読んだことがなかったけど、知っていた。原著はそのくらい有名な本だ。僕が私淑し、翻訳も手がけたナンシー・アトウェルは、1980年代のアメリカの「ライティング・プロセス・ムーブメント」(それまでの伝統的文章教育と異なり、書くプロセスを教えることを重視する運動)の中にいた実践者だが、エルボウもまた、ドナルド・マレーやドナルド・グレイブスらとともに、そのムーブメントを牽引した一人だと思う。ライティング・ワークショップを普及させたグレイブスらとはやや異なるが、大きな目で見れば、彼もまた、プロセス・アプローチを唱えた人と言っていい。
というわけで、プロセス・アプローチの実践者として、この本はかねがね読みたいと思っていた。そんなところに、僕のブログを読んでくださった本書の編集者の方から連絡があり、刊行前のゲラを用いたワークショップを体験する幸運に恵まれた。だから、僕はこの本を読みながら、ひととおりはこの本に書いてあることをやっている。以下、このエントリはそういう前提で読んでほしい。
「書く」プロセスをつくる本
最初に本書の概要から。本書はいわゆる文章技術術の本ではあるが、「わかりやすい文章の書き方」「印象的な文章の書き方」を日本語のテクニックとして具体的に教える本ではない(その方面の本が欲しければ、最近では石黒圭『ていねいな文章大全』が圧巻である)。
代わりに、本書が提示する技術・知識は、文章を書くプロセスに関するものだ。本書の特徴の第一は、「書くプロセス」の具体的なモデルを提案したことにある。そのモデルが、「フリーライティング」「グローイング」「クッキング」という3つの段階を踏んだプロセスである。それぞれ、次のような段階だ。
- フリーライティング…自己検閲をはずして、書きたいことを書きちらす段階。
- グローイング…書いたものの中から「重心」を見つけて育てる段階。
- クッキング…書いたものの中にある、さまざまな要素に相互作用を起こし、内容や表現を豊かにする段階。
これだけだと「?」となるはず。詳細は本書を読んでいただきたい。一番の特徴は、書き手が勝手に自分の書いたものに批判的になってしまう「自己検閲」をふせぐためのフリーライティングから出発することだろう。
ただ、ライティングのプロセスは、実際にやってみないとわからない(実感できない)ことも多い。ざっと読んでまずはやってみて、やりながらこの本を再読するくらいをお薦めする。実際、僕はまだこの「クッキング」の段階が腑に落ちていない。何回かやってみたけど効果的にクッキングを起こせた実感がなくて、まだつかめていないな、と思っている。
また、そもそも本書のように、ライティングに「規範的プロセス」が存在するかというと、僕はやや懐疑的な立場である。ライティング・プロセスは人によって千差万別で、混沌としたものだ。「取材」「下書き」「執筆」「推敲」のようにきれいにわかれないのと同様、「フリーライティング」「グローイング」「クッキング」のようにもスパッと分かれないだろう。だから、本書の提案も「自分なりのライティング・プロセスをつくる雛形の一つ」程度に僕は捉えている。
「改善点の指摘」や「評価」ではないフィードバック
本書のもう一つの特徴が、こうやって個人作業で書いた文章を共有する「ティーチャーレス・ライティング・クラス」というフィードバック・グループの存在である。「先生のいない教室」という言葉からわかる通り、このグループには「先生」、つまり指導的役割を果たす人はいない。また、読み手は(よくある作文授業のピア・フィードバックのように)長所や改善点を指摘したり、評価したりすることが求められているのではない。ただ、文章を読んだ自分の「反応」を伝えることが求められる。また、書き手の側も、別に読み手の助言に従うことが求められているわけではない。読み手の反応を確認した上で、自分がどうしたいかを考えれば、それで良い。
これはとても面白いシステムだ。一言で言えば、ティーチャーレス・ライティング・クラスにおける読み手とは、書き手が新たな判断をするための「観察対象」なのである。書き手は、別に読み手のAさんやBさんの言うことに従う必要はない(従いたければ、従ってもいい)。それぞれの「反応」に対して、たとえば「なるほど、Aさんのような読み手には、この文章はこう読まれるのか。Bさんのタイプの人には、違う反応をされるのか。でも、Bさんはいつもこういう文章にはこういう反応するからな…」と、発言内容を発言主とセットで受け取って、それを脇に眺めつつ、「次に自分はどうしたいのかな」と考える。だから、発言内容はもちろんのことながら、それを誰が発言したか、どう発言したかも、場合によっては重要な判断材料になる。
実は、これが僕が他の人に原稿を事前に読んでもらったときに、しようとしていることでもある。「していること」と書かなかったのは、かくいう僕も「褒められるかどうか」(より正確に言うと「批判されないかどうか」)が気になってしまうからだ。でも、読み手の反応に一喜一憂せずに、研究室で化学反応の実験をするように、「この文章は、このタイプの読者とはこういう化学反応をおこすのか」と一つ一つの反応を受け取りながら、「じゃあ次はこうしてみようかな」と考えることができたら、どんなに良いだろう。その時、文章を書くという研究のイニシアチブは、間違いなく僕の手にあるのだから。
実際のところ、このティーチャーレス・クラスを十分に機能させるのはそう簡単ではない。誰かの発言が権威を持たないようにするにはどうしたらいいのか。相手からの評価がつい気になってしまうのはどうしたらいいか…。そこで、本書には、このティーチャーレス・クラスの中で読み手や書き手がどうふるまうべきかが、丁寧に、こと細かく述べられている。ここは、僕の個人的なライティング経験や指導経験からもうなずけることが多い。とても面白く、本書の個人的お薦めの章だ。また、ティーチャーレス・クラスルームの活用に関しては、エルボウの原著だけでなく、p257の「付録」やp261からの「監訳者解説」も、大きな助けになる。こうした補足によって、読者はティーチャーレス・クラスルームのイメージを十分に持てるだろう。とはいえ、実際に本書を使ったワークショップに参加してみると、これも「読むだけ」では実践も実感もできないことだらけである。やりながら読み直すくらいでちょうど良いはずだ。
ダウティング・ゲームとビリービング・ゲーム
さて、ここまでで、本書の「書く技術」本としての本書の紹介には十分だろう。しかし、実は何を隠そう、僕が本書を読んで一番刺激を受けたのは、「補遺」として収録されている「ダウティング・ゲームとビリービング・ゲーム」の章だった。これは、筆者が1973年の初版刊行以来寄せられてきた本書への批判への応答とも言える章であり、やや大げさに書けば、ティーチャーレス・クラスルームの寄って立つ思想的基盤を表明した章である。
筆者はこの章で、人間の知的営為を「ダウティング・ゲーム」と「ビリービング・ゲーム」の二つの営みの相補的な円環だと主張する。(以下のまとめは僕によるものなので、若干ニュアンスに差が出ているかもしれない。ちゃんと知りたい人は本書を読んでほしい)
- ダウティング・ゲーム…アイデアに対して言葉を用いて批判的に検討し、議論し、論理的に結論を出そうとする知的モード。
- ビリービング・ゲーム…アイデアに対して耳を傾け、是認し、価値を賞味し、体験しようとする知的モード。
つまり、ティーチャーレス・クラスルームは、厳しい論理的検討や批判といったダウティング・ゲームを用いず、ビリービング・ゲームによって共同的な知的生産をすることを目指しているのだ。
大学における知的営為がダウティング・ゲームに偏っているため(おそらく1973年当時は今よりもずっとその色が強かっただろう)、どうしてもエルボウはダウティング・ゲームに対して批判的論調だが、彼はこの両者のどちらかが優れているのではなく、補う関係にあることを明言している。
2つのゲームを使い分ける
このアイデアが僕にとって面白かったのは、文章を書くことに限らず、さまざまな営みをこの2つのゲームの比喩で捉えることができる、と思ったからである。例えば、クライアントを中心に置く心理カウンセリングは、完全にビリービング・ゲームの営みだ。実際、本書ではカール・ロジャースの名前が、エルボウが「ビリービング・ゲームの種をたくさんもらった」(p47)人物として登場する。
教員にも、ダウティング・ゲームのモードが強い人と、逆にビリービング・ゲームのモードが強い人がいる。僕はおそらく論理モードのダウティング・ゲームの色彩が強い人だ。わりと客観的にその子を評価して、今がどういう状態でどうなるといいのかを考えてしまう。逆に、ビリービング・モードで、ひたすらその子の世界の中に入り込もうとする同僚もいる。彼は、あの子にとって、この時間はどういう時間なのか。あの子にとって、どういう意味があるのかを探究し、その子からの世界を追及しようとする。
どちらが優れているというわけではなく、それらは相補的な関係なのだろう。風越学園の同僚のあっきー(木村彰宏さん)は、カウンセリングやコーチングの手法を教育分野で用いる人だが、彼が以前に僕の質問に対して、「いつもコーチングのモードというわけではなく、ティーチングとコーチングのモードを時と場合で使い分ける」と語っていたことがある。あっきーの言う「ティーチングとコーチングの使い分け」は、おそらく、「ダウティング・ゲームとビリービング・ゲームの使い分け」に近い。
自分の場合はもともとダウティング・ゲームの訓練を受けてきて(学術的な基礎訓練の多くはダウティング・ゲームであるように思う)、おそらくはその適性も比較的高い人間だ。だから、放っておくとダウティング・ゲームが発動してしまい、これまで「非学術的な」(と見える)ビリービング・ゲームには好意的にはなれなかった。しかし、両者が相補的な関係なのだとすれば、いまの自分に必要なのは、逆にビリービング・ゲームで世界をとらえる練習なのだと思う。
このことに関して、面白い発見があった。僕がPA(プロジェクト・アドベンチャー)と並んで初見の拒否感が強かったものにNVC(Non Violence Communication)がある。だが、お正月に、本書を読んで「NVCはビリービング・ゲームなのだ」と気づいたのだ(その時に自分が書いた文章を、本エントリの最後に「おまけ」として掲げておく)。そう気づくと、苦手なNVCも、「ビリービング・ゲームで世界を解釈する練習」と思うことでその拒否感が弱まり、2月には、風越校内のNVCの自主研修に出席さえしてしまった。これも、本書との出会いがもたらしてくれた、ささやかな変化である。
本書を使って僕がしたいこと
ここまで書いたように、本書は、ライティングの本でありながら、それだけにとどまらない可能性を持っている(だからこそ、巻末の「監訳者解説」でも、書くことに限定されない応用事例が紹介されている)。ただ、やはりまずは作文教育に応用したい。個人的には、この本に興味がある学校教員を集めて、ティーチャーレス・クラスを結成し、この本を参考にしたライティング・グループを継続してやってみたいな、という気持ちがある。たぶん、実際に書きながら、フィードバックしあいながらこの本を読むことで、この本の内容がより実感できるはずだ。
また、もう一つしたいのが、ダウティング・ゲームとビリービング・ゲームというメタファーを使って、自分の教育実践を観察すること。自分はもともと言語を用いた論理実証的なダウティング・ゲームが優位な人なので、油断すると客観的に観察したり、これからどうすると良いか対策を考えたりしてしまう。そうではなくて、ビリービング・ゲームを意識的に発動して、子どもの話の中に没入するとか、意見を言わずにただ受け取るとか、そういう機会を増やすこと。
風越学園に来てから、いろいろなスタッフや子どもと接する中で、自分はうすうす、ビリービング・ゲームの中に自己を投入する必要性を感じていたはずだ。おそらくはそれもあって今年度開いたPAの勉強会でも、人が受け取る体験がいかに多様で、それぞれに偏っているのか、実感を積み重ねてきた(下記エントリ参照)。
そんな中、ライティングという自分の専門分野で、実際にティーチャーレス・クラスルームを体験しつつ、「ビリービング・ゲーム」という言葉に出会えたことはラッキーだったな、と正直思う。自分に遠いものは、自分に近いものと結びつけることで、身近になる。本書との出会いを通して、今年は、このビリービング・ゲームがより身近になる一年になればいい。僕にとって本書は、ライティングに限らず、そういう大きな指針も与えてくれる本だった。ぜひ、一読をおすすめする。
おまけ)24年1月8日のフリーライティング
先週末、ビリービング・ゲームとダウティング・ゲームについて面白い発見があったのでメモしておきたい。6日、東京に出て、東京在住時代からの国語教師仲間の勉強会に出席したのだが、そこで勉強仲間の一人が、NVC(Non Violence Communication)の考え方に基づいた話を聞くトレーニングについて紹介してくれたのだ。そのトレーニングでは、話し手が自分のことについて話した後で、聞き手が、その話を聞いて自分の頭に思い浮かんだfeeling(感情)をリストに書かれた言葉から選ぶ。そして、自分の心に浮かんだことについて話す。決して、話し手の話に対するアドバイスや原因の推測や、話し手の話の分析をしない、というのがルールなのだそうである。
相手の話を論理的に分析して原因を究明したり対策をたてたりするのを「ダウティング・ゲームの聞き方」とすれば、このNVCの聞き方は、自分の頭に思い浮かんだ感情のリストの言葉を話すだけ。これは、ティーチャーレス・クラスルームにおける、助言をせず、自分の頭に思い浮かんだことを話すという関わり方と、とても似ているな、と思った。つまり、NVCでは、聞き手がダウティングモードを発動して話し手に関わって正解を示すのではなく、話し手が、聞き手のあくまで断片的な反応(単語一語のみの場合もある)から、自分にとっての意味を作り出すことを重視している。聞き手のフィードバックは、あくまで話し手が意味を作り出すための断片的な材料に過ぎず、話し手はその材料をもとに自分なりの意味を構築していく。そこで構築された意味は、聞き手が伝えたかったことではない。
この日の勉強会では、俳句の実践の報告もあったのだが、考えてみると、俳句もビリービング・ゲームの文学だと言える。俳句に書かれた十七音は、それ自体が明確な唯一の意味を構築したりしない。あくまでその十七音を材料に、季語のイメージ喚起力にも頼って、読み手が意味を構築していく。これが連句や連歌になると、自分の前の人の句のイメージに乗っかったり、またはそこをあえてずらしたりして、前の句との饗応を楽しんでいく。ダウティング・ゲームでは連句は成立しない。
こういう自分の発見について「実はいま読書会で読んでいる本にこんなことが書いてあって…」と伝えたら、この日に出席していた漢文が専門の先生が、ビリービング・ゲームとダウティング・ゲームについて、「それは荘子の思想と儒家や法家の思想の違いに似ている」と言っていたのも印象的だった。秩序の論理的構築をめざす儒家や法家の思想(ダウティング・ゲームの論理)に対して、荘子の思想はそういう秩序の根本をひっくりかえして、混沌に価値を見出す。その両者の違いが、ビリービング・ゲームとダウティング・ゲームの思想の違いに似ているというのだ。
こういう話が、ただのメタファーにすぎないのか、それこそどこまで正確なのか、ダウティング・ゲームで疑ったら、きっといくらでも疑えるのだろう。でも、自分のなかで、この読書会の本の話と、国語の勉強会の話がつながったのがとても面白かった。ビリービング・ゲームは、NVC、俳句、荘子。こういうメタファーでとらえてみよう。
[ad#ad_inside]

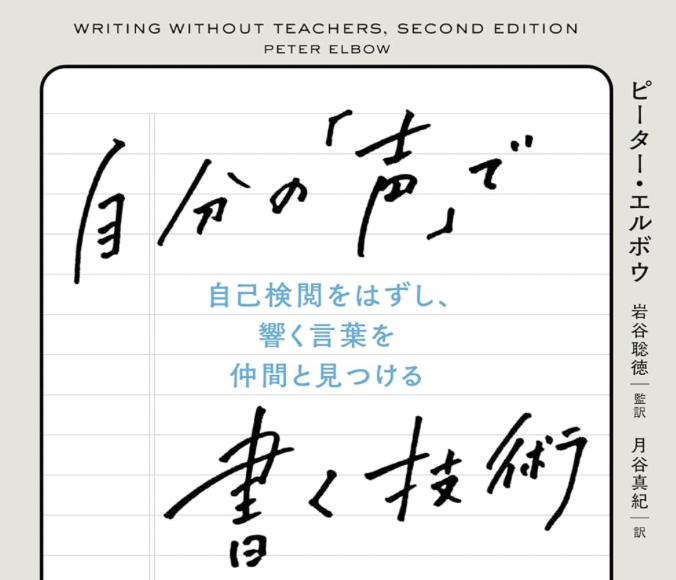


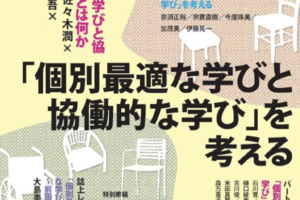



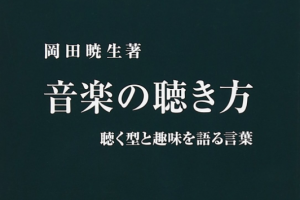


![[読書]優れた図工教師としての顔に感嘆。岡田淳『図工準備室の窓から』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2025/01/57f40b6600c9e09eefd646ec7c1fcc6a-50x50.png)
![[読書]いかにして虐殺者になったのか。クリストファー・ブラウニング『普通の人びと』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/11/スクリーンショット-2016-11-15-22.57.15-50x50.png)
![[紹介]参考になる!『イン・ザ・ミドル』にもとづくリーディング・ワークショップの実践記録](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/04/c382b91dc00dc06f5c867c0d33a758bf-50x50.png)
ティーチャーレス·クラス、大阪からも参加可能であればぜひやってみたいです!難しければ、本校の教員に声をかけてやってみようかと思います。
見落としていてごめんなさい! 最初は対面で考えようかなと思っているのですが、オンライン実施になった場合はよろしくお願いします!