作文教育史をたどると、時々、「いやあ、いつの時代も同じだあ」と思う記述に出会う。たとえば、滑川道夫『日本作文綴方教育史[明治篇]』によると、1906(明治39)年『中学世界』に掲載された「現今の学生と文章」という記事には、次のような当時の生徒の姿が描かれているそうだ。
▼
処が中には「題を出してくれ」と請求する生徒がある。「題のある方が楽だ」といふ。かういふ生徒に限って文章が下手だ。否、分になってをらぬ。つまり真実を書くつもりなく、何でも題によつて、出鱈目と、「作文資料」などの文句の綴ぎ合はせでごまかして了はうとするからだ。猶立入つて言へば、これはお役目に作文をやるのだ。
たしかに、題のある方が楽。題を見つけるまでが大変だから。でもそうやって与えられた題で、自分で書きたいと思う題じゃないと、作文はただの「(出来るだけ省エネで)処理すべきタスク」になってしまうんだよね。そうやって「処理」された「お役目」的な作文、たくさん読んできたなあ…(遠い目)。これだと、課題を書く側もそれを読む側も苦痛だし、力にならない。
▼
教師の方へ出す作文は全くお役目的にやつてゐながら、仲間同士の肉筆雑誌へは一生懸命に書く。この例は何処の学校にも沢山ある。一方はどうせ教師が見るだけで、やがてポツリと返してよこすだけと思ふが、一方は大勢の仲間同士に回覧され批評されると思ふので、張合が出て気乗りがするのだ。
そういう生徒も、こんなふうに生徒同士に見せ合ったりするものや、他に発表のあるものについては驚くくらい熱心に、真剣に書く。文化祭のステージやコントの台本とか…。要は、そういう「本当に他に人に読んで貰う機会」「真剣になれる機会」を作れるかどうか、なんだろうなあ、作文教育って。
▼
作文の時間に見てゐると、教場で例の如く着席して了ふと、すぐに毛筆を採つて書き始める人がある――即ち草稿もせず、考へもせずに――かういふ人に限つて必ず下手だ。それは一人位は予て腹案を立てて来てすらすらと書いて了ふというものもあるが、其の他は皆漫然筆を採るのだ。そして、切れ切れに浮んで来る事を、書き足し書き足ししてお終ひにする。で、大概印象不明瞭なものにして了ふ。
ああ、こういう生徒もいるいる。いきなり書き始めて、考えながら適当にまとめようとするんだけど、それができないで後半がグダグダになるパターン。本当におなじみですね。
▼
こうやって書くと、まさに今自分が直面している現象ばかりで、本当に時代を感じさせない。1906年も、2014年も、人はあまり変わらないようだ。それに対応する作文教育のほうはどうだろう?
[ad#ad_inside]

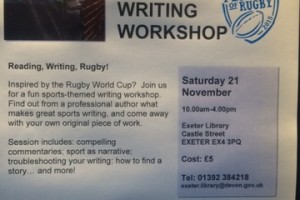







![[告知]軽井沢町周辺の方へ。4/27(木)から、KAIさん&あっきーのPA連続講座やります。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2023/04/5df48e579e14dda5b2e4f5fb2bb33528-50x50.png)
