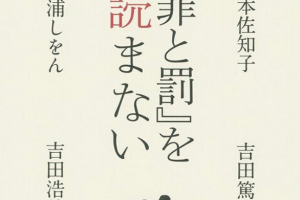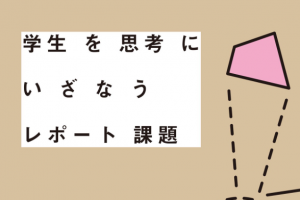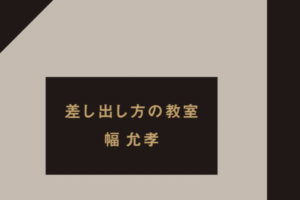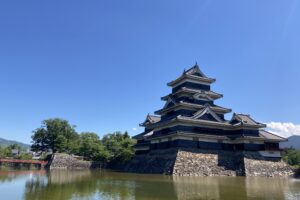しばらく前に、Twitter(X)で、読書研究がご専門のある先生が内田義彦『読書と社会科学』を読んで激賞していらした。初版はちょうど40年前の1985年。いわゆる「黄版」の岩波新書である。実は僕も20年前にこの本を読んでいたので、懐かしさもあって「どんなこと書いていたっけな」と久しぶりに手に取ったら、これがまあ、実に教えられるところの多い本だった…。こういう本を古典というのだろう。読書メモとしてここに残しておきたい。
自分の「概念装置」をつくりあげる読書論
思い起こせば、僕が前にこの本を手にとったのは20年前。ちょうど筑駒に着任したての頃に、公民が専門で部活顧問をご一緒したY先生に、おすすめいただいたのがきっかけだ。その際にY先生が「この本の『概念装置』の話を、必ず生徒にはするんです」ともおっしゃっていたので、読む時も自然とその言葉を探すような感じて読んだと思う。で、それ以降、内田義彦『読書と社会科学』といえば「あー、はいはい。概念装置の話ね」と勝手に要約してとらえていた。ただ今回、20年ぶりに本書を読んだら、それはかなり浅い理解だったようだ。
20年前の僕の本書理解はこうである。「本書が述べているのは、概念装置を自分の中に持って世界を見ると、世界の見え方が変わって見えるということだ。そして、社会科学こそその概念装置を作り出す学問なのだ」というものだ。これ自体は間違いではないだろうし、大学や大学院で学んで「理論」というものの強力さ、それを通すと時に世界の見え方が変わってしまう「知的メガネ」の魅力を知った人なら、誰でも共感できることだろう。そして、著者の主張もそういった内容も含んではいる。
ただ、本書では「読書を通して色々な概念装置を手に入れよう」みたいなことは一切言っていない。「自然法」とか「語り」とか「フェミニズム」とか…なんでもいいけど、読書を通してそれらの概念をアイテムのように収集すれば、それだけ世界の見え方が多様になるよとか、そういう話は全くしていない。おそらく筆者は、それはむしろ「本に読まれている」状態に過ぎないと言うはずだ。
そうではなくて、「真に自由な存在になるべく人間は自分の眼で世界を見るのだが、その眼を補佐する存在としての自前の概念装置をつくりあげる必要がある。そのためにこそ本を心して読め」と、そう言っているのだ。既存の概念装置をメガネのようにとっかえひっかえするのではなく、自分の概念装置を自ら「つくりあげる」ことの大切さ。何度も強調されるその点を看過して「あー、はいはい。概念装置」と、自分の狭い経験や知見に矮小化して誤読していたかつての自分は、いったい何を読んでいたんだろう、と恥ずかしくなる話だった。
書き手を信じる、自分も信じる。
では、その「自前の概念装置のつくりかた」について、筆者はどう論じているのだろう。そのための根本姿勢が、本を「情報として」読むのではなく「古典として」読む姿勢なのだと思う。古典を読むのではない。私の古典「として」読むのだ。
この「古典として読む」ための具体的な読み方は、本書前半で語られている。一言でいえば「信じて疑え」。順序としては「信じてかかれ」(p35)ということだ。例えば、読んでいて疑問に思えた箇所が出てきたときに、著者に距離をとって「客観的に」読んだり、まして底の浅い批判意識にとらわれて疑問をすぐに持ったりせず、まずはその著者に全面的に「信」を置く。一方で、それとは矛盾するようだが「それでも自分にはこう読める」と、自分にも「信」を置く。この2つの「信」に支えられて、念入りに注意深く物事を見る行為があって、初めて「疑い」は創造的営みとしての探求に結びつく。筆者はおおよそこう語っているのだ(p38〜p42あたり)。これはとても刺激的な主張で、しかも、読んでいて納得できるものだった。「読む」という営みは、たしかにどこかで書き手に自分を全面的に預け、にもかかわらず自分の足で立つ、そんな決断がないところでは成り立たないのではないか。
あえて「書きにくく」読む
この文脈に関連して、「書きにくく」読むという話も面白かった。筆者は「みだりに感想文を書くな」と言う。例えば僕がブログを書くように、読んですぐに感想文を書く読み方を戒める。それはなぜかというと、すぐにアウトプットしようとすると、「書きやすい」(もっと言えば「読者にウケやすい」)内容に理解がすり替わってしまうからだ。だから本は「書きにくく読む」ことが大事だと筆者は述べる。
読み手としては、どこまで書きにくく読むかーー書きにくいところを書きにくいまま受け取ることーーが勝負であります。他方書き手としては、読み手である自分が書きにくく受け取ってきたその感想を、如何に明確に書きとめてみせるかが勝負といっていい。読者は、この矛盾した両者を一身のなかでともに育て上げ、競い合わせる。そのせめぎ合いのなかで真に正確で個性的な確かな読みが出てくるんで、そこに、読書の意味と妙味があるのです。(p60-61)
これはしびれる。すごい一節ではないですか? 本書は一般向けに書かれた(なんならもとは講演の内容を多分に含んでいる)入門書なので、口調はやさしいのだけど、過去の自分はこの本を全く読めていなかったし、今も十分に読めた感じがしない。「書き手と自分にともに『信』を置く」も「書きにくく読む」も、なにやら禅問答めいていて、読んでうむむと唸ることはあっても、自分でそれを実践できるかとなったら自信はない。
しかし、こうやって、自己と書き手のぎりぎりの交渉の中で本を読み、それを通して自分なりの概念装置を手に入れることができたら、それは本当に素晴らしい経験のはずだ。40年以上前の本だけど、「一読して読みやすく書け」「情報として読め」が幅をきかせる現代において、めちゃくちゃ新しくてクリエイティブな読書論なのである。ぜひ一読をおすすめしたい。