授業はある程度事前の計画どおりに進まければならない。しかし、その都度の生徒の発言や動きを拾い上げて授業をつくれば、おのずと授業は即興的展開になる。この計画と即興のバランスをどうとるか。ある程度経験を積んだ教師なら誰もが直面するこのティーチング・パラドックスを話題にした興味深い本が、キース・ソーヤー『クリエイティブ・クラスルーム』である。著者のキース・ソーヤーは「創造性を教える」創造性教育を研究する研究者で、自身がジャズ・ピアニストという経歴の持ち主でもある。
[ad#ad_inside]計画と即興という、魅力的なパラドックス
僕がこの本を手にとった大きな理由が、「即興」「計画」という言葉に惹かれたからだ。もともと一斉授業形式で授業をしていた時、一度に複数クラスを受け持っていた時から、僕は各クラスで授業展開が変わるのが好きだった。そもそも、授業は他ならぬ僕自身と生徒たちによって作られるものである。たとえエゴだとわかっていても、他の誰でもできることを僕がやる、つまり自分が交換可能な存在になるのは面白くないし、それと同じで、誰が生徒でも同じ授業になるのも面白くない。少しでも多くの生徒に「自分のおかげで今回の授業は成り立っているんだ」という感覚を持ってほしい。そんなふうに、クラスによって生徒の発言も展開も全く違うのに、全体としてはゆるやかにひとつの方向性になって、期末試験で共通のことを問えるように授業をもっていく。こういうティーチング・パラドックスは、教える仕事の難しさでもあり、楽しみでもあった。それが話題の本かちお思ったのだ。
実際に読んでみると、この本は別に一般的な授業における「即興」と「計画」について書かれているわけではない。でも、「ガイドつき即興法」と呼ばれる、事前の計画と即興のバランスをとった方法によって創造性を育てる教育について書かれており、どの科目のどの校種の教員にも、興味深い本だと思う。
創造的知識のネットワークが創造性を生む
この本を読んで、まずその大切さを改めて教えられるのが、「深い知識のネットワークこそが創造性の源泉となる」ことである。創造性は、天才のみに許された思いつきでも、知識がない素人だからこそできる新たな発想でもない。ソーヤーはそういう神話を否定し、「どんな分野でも、創造性はその分野に関する豊富な知識を土台に発揮されます」と述べる。ただし、そこでの「知識」とは、年号や元素記号の暗記にとどまる「浅い知識」であってはいけない。ソーヤーは、浅い知識の土台にあって文脈を支えている、その科目の基本原理と理論についての概念的な理解を「創造的な知識」と呼ぶ。この創造的な知識があってこそ、知識は他の知識とネットワークを形成し、新しい状況にも柔軟に転移し、行動変容をうながすこともできる。
創造的学習の基盤となる教師の態度とは?
では、そういう創造的知識を学ぶ創造的学習を生み出すには、どういう手法が良いのだろうか。それが即興と計画のバランスをとる「ガイドつき即興法」である。本書では、その基本方針や事例が紹介されているのだが、そこは本書を読んでもらうことにしよう(個人的には、ライティング・ワークショップのカンファランスのような手法も紹介されていて、言われるとたしかにあれも即興だよな、と改めて気づいた)。
本書の中で僕が一番興味を惹かれたのは、即興演劇のいくつかのルールで即興的な教師の態度が説明できる、という箇所だった。筆者は、即興演劇を例にして、創造的学習の基盤となる即興的なやりとりを大事にする教師の態度を以下の6点に整理する。これが色々と考えさせられて、面白かったのだ。
- イエス・アンド
- 否定しない
- 先導しない
- 押し付けない
- 質問しない
- 第四の壁を超える(メタ・コミュニケーションをしない)
個人的に興味深かったのは、ここでのルール、僕が破っていたものがいっぱいある、ということだった(汗)。というのも、これらの即興演劇のルールに反する行為は、逆から見ると、すべて「教師が教室の主導権を握るための行為」だからである。授業の流れのあるポイントでこういう即興ルール破りを意図的にすることで、教師は、子どもたちの発言で授業を作っているように子どもには思わせつつ、こっそりと、全体の流れを一つの方向性に収斂させていく。
したがって、どんなに即興的に見えても、それは即興演劇などでの意味の「即興」ではない。即興のふりをして教師が主導権を握っている。僕がやっている授業でもそうだったので、そのことへの批判は甘んじて受けないといけない。でも同時に、授業者の実感としては、これらがあることで、どのクラスでもある程度の即興を成り立たせることができたのだ、とも思う。現実問題として、複数クラスを教える中高の教員は、どんなに生徒の声を活かしたいと思っても、隣のクラスとの内容や進度調整が必要になってくる。だとしたら、上記のルールを熟知し、時にそれに意図的に違反することは、それを授業に織り込むことで他クラスとの調整を行い、「ある程度の幅の即興性」をクラスで成り立たせるために必要な技術なのではないか、とも思った。もちろん、複数クラスに対して共通のテストをすることがそもそも本質から外れているのだ、という意見もあるだろうが、現実の仕事としてクラスごとに異なる評価基準で異なるテストなどをするのは無理ですし…。
ただ、幸いなことに、風越学園にいる今の僕は、複数クラスに共通のテストをしなくても良い。だとしたら、風越学園での僕はもっと自分の即興の度合いを柔軟に変えられるはずだ。上記のルールをできるだけ守ることもできる。僕は即興演劇とかはとても苦手で距離を置いてきたのだけど、こういう授業のためのトレーニングと思うとちょっと見方が変わるし、オーケストレーション・スクリプト(p162)のような測定ソフトウェアを使って、授業で自分の即興性をどれだけ高められるかに挑戦するのも面白いな、と思う。
「科目」という枠組みをどう捉えるか?
この本には、他にも興味深いところがあった。何よりもっと知りたいなと思った点は、「科目」という枠組みを筆者がどう捉えているかだ。筆者は、創造力は領域固有的だとして、科目ごとに学ぶことの意義を繰り返し強調する。
どの授業も、創造的な学習成果をめざして行わなければなりません。なぜなら創造力は領域固有的だからです。ある科目で創造性を発揮するには、その科目の創造的な知識が必要になります。例えば、美術で創造性を学んでも、数学での創造性は伸びません。数学で創造性が身についても、生物学での創造性は伸びません。だから、全科目で創造的な授業を行わなければならないのです。(p25-26)
しかしここで疑問が生じる。第一に創造力が領域固有的だと認めたとして、なぜその領域は「科目」という領域であるのか?ということだ。もう一つ疑問なのは、ここでは「科目」という枠組みに肯定的な筆者が、一方で後半では、次のように科目の枠組みを超えることも肯定的に語っている点である。
創造的な知識とは、複数の分野に共通していることが多い概念的フレームワークなのです。創造性のための学校では、授業のスケジュールは科目別に編成されていない場合があります。一日の時限数が少なく、一つの授業は複数の科目を組み合わせた内容になっているかもしれません。(p187)
この2つの主張(特に太字の部分)がどのように整合するのか、今の自分にはまだよくわかっていない。科目ごとに創造的知識を教えつつ、科目を超える授業も用意するということだろうか?
こういうことが気になるのは、僕が完全に「教科の人間」で、教科固有の領域があると思っているからである。例えば、プロジェクト学習を推進しようとする人の中には、「国語は言語活動なのだからすべてプロジェクトの中でできる」と主張する人もいるけど、プロジェクトなどでの「言語活動」に回収できるのは、言語を伝達の道具として使うという、言語の性質の一側面にすぎない。言葉の組み合わせによって新たに自律的世界を作り出す言葉の創造的・修辞的働きは、決してプロジェクト学習の発表形態としてレポートを書いたり、スライドを書いたりすることで良く学べるものではない。だから、少なくとも国語には固有の領域があると考えている。ただ、その科目における創造性が、教科横断的なプロジェクトとどう関係するのか、他の科目にはどんな固有の領域があるのか、それは僕にはよくわかっていない。この問題は、風越学園でも、教科を中心とした「土台の学び」と「テーマプロジェクト」の関係の捉え方にもつながるので、ソーヤーがこの問題についてどう考えているのかは気になった。
他の研究との関係は?
また、もう一つ気になるのは、ソーヤーの主張と、たとえばデイジー・クリストドゥールーやジョン・ハッティの議論との関係をどう捉えればよいのだろう、ということだ。ジョン・ハッティの研究は、ソーヤーがたびたび批判する教師による直接教授(direct instruction)の効果の高さを示している。また、クリストドゥールーは、そのハッティも引用しながら、教師による直接教授とドリルを組み合わせて長期記憶に記憶を定着させることが学習にいかに大事かを力説する。いずれもソーヤーとは相容れないように思えるのだが、こうした齟齬は、結局これらの研究が何を目指しているのかの、背景となるビジョンや研究フィールドの違いに由来するのだろうか。このあたりも、誰かの助けを借りて整理したいところである。
Clubhouseの公開読書会もあるそうです
今回は、本の内容紹介というよりも、個人的に気になったところを中心に書いてみた。なお、新年1月5日の正午から、東京学芸大学の渡辺貴裕さんと名古屋柳城女子大学の豊田明子さんが、Clubhouseで公開二人読書会を行うそうです。僕はその読書会を聞く前に一度読んでおこうと大急ぎで読んだのだけど、お二人の話を聞いてまた本をめくるのが楽しみ。もしこの本に興味のある人は、ぜひこちらのClubhouseもどうぞ。
[ad#ad_inside]
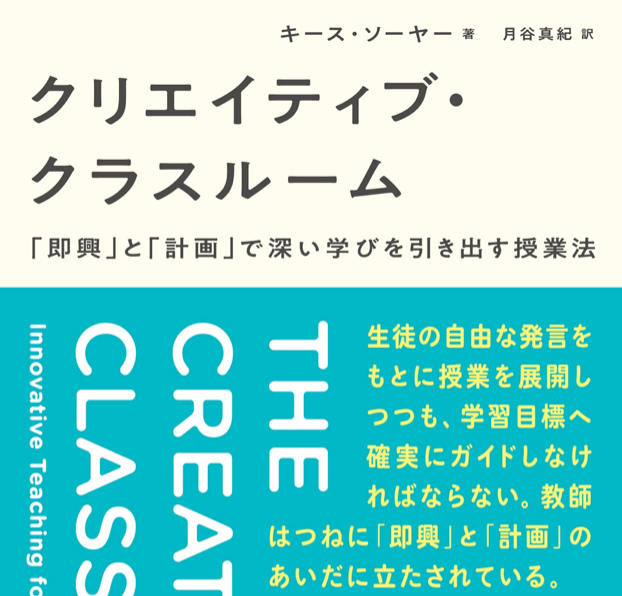



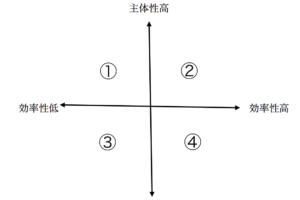





![[読書] 公教育をゼロから考える本。苫野一徳『どのような教育が「よい」教育か』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/12/スクリーンショット-2016-12-30-15.07.26-50x50.png)
![[読書]「教師の成長」に関わる人におすすめ!渡辺貴裕『小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ授業づくりの考え方』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2025/11/b5e8b178146dc4a484b286b7de03f5ad-50x50.png)