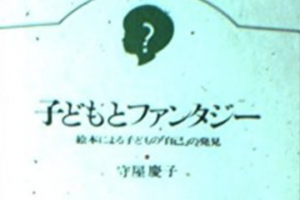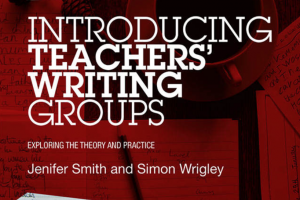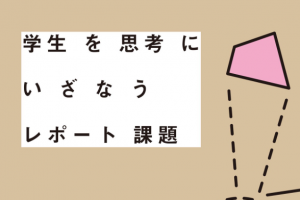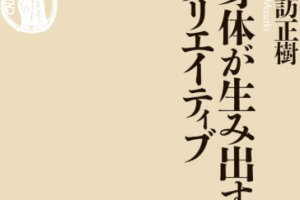先日、『社会科ワークショップ』の読書会に参加した。『社会科ワークショップ』は、ライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップと同じワークショップスタイルでの社会科の授業を提案する本で、著者の一人・冨田明広さんは2014年に刊行された『読書家の時間』の著者でもある。そこから5年たって刊行されたのが、どんな教科の教員であっても読むと得る点が多い、この間の実践の充実ぶりを物語る本もである。必然的に、この本の読書会も面白かった。
[ad#ad_inside]活き活きと描かれる子どもと大人たち
僕はこの本をすでに読んでいるのだが(下記エントリ参照)、この読書会のために再読して、やはり面白かった。
この本は何より、読み物として面白い。まず、本書に登場する子どもたち。どのクラスにもいる「先生の意図から外れて自分の興味を優先する子」「ぎくしゃくするペア」….これらの子たちが社会科ワークショップの中でどう学び、教員がそれにどうアプローチしたか、授業での子どもたちの姿がとても活き活きと描かれる。今年、小学5・6年生を持っている僕は、「いるいる、こんな子」の連発だった。そして、先生たちの姿についても同様だ。著者の一人である西田さんの初任の時からの歩み、社会科ワークショップをやって感じる手応えや迷い、そして同僚との対話。いずれもつい自分と重ねながら読んでしまう。研究論文ではない本書は、そのストーリー性によって読者を惹きつけるものになっている。
どの教科でも応用がききそうな考え方・指導法
また、本書の大きな特徴が、副題「自立した学び手を育てる教え方・学び方」のとおり、どの教科でも応用がききそうな考え方・学び方が満載なことだ。小学生には、自分の知的好奇心を満たすために学ぶ子よりも、「むしろ、『誰かのために』という思考で学習の主体性が強くなる子どものほうが多い」という子ども観(p134)は、僕も小学校に勤めるようになって感じることが多くなってきた。また、「今、目の前の子どもたちが何を認めているのかを見極めること」が最も大切だと主張するカンファランスの基本理念(p205)も、最近、大事だなと思っていることだ。他にも、段階的に支援を減らして子どもが自分でテーマをつくる力を育てる方法(p271)、「調べ学習」で終わらずに意見を生み出すためのミニレッスン(p280)など、どの教科でも参考になる情報がたくさんあった。
ユニット=遊び場という比喩が印象的
なかでも今回僕の興味を惹いたのは、ワークショップの設計図である「ユニット」についての説明だった。ユニットは、学習指導要領、目の前の子どもたちの実態、教師自身の強みや経験の三者のバランスで作られる学習活動のまとまりのことで(p149)、子どもたちは決してただ自由に探究するのではなく、このユニットに沿って活動する。だからこそ、学習指導要領にも触れて、一条校としての責任も果たすことができる、というわけだ。学習範囲・条件・学習のゴールなどは、このユニットという形で子どもたちに手渡される。
読書会では、このユニットをやや窮屈に感じている方もいたようだ。また、著者の冨田さんや西田さん自身も「教科書どおりやらないと不安な人のため」「自分にはまだこれが必要」という消極的採用のニュアンスをこめた言い方をしていた。でも僕は、このユニットという学習単位は「学ぶべきこと」と「子どもたちが学びたいこと」のバランスをとる上で、とても重要だと考える。そして、このユニットを「遊び場」に例える、次の文章がとても良かった。
たとえば、果てしなく広がる草原で子どもたちを遊ばせたとします。そこで子どもたちは、最初は無限に広がる草原にワクワクして歓喜の声を上げるでしょう。しかし、ある子どもは興奮して教師の助言が届かない遠いところまで走り去ってしまい、また、別の子どもは、何で遊んでよいか分からず、途方に暮れてしまうかもしれません。
ユニットの設計ができていない学習に子どもたちを放り込んでしまうことは、遊び場の範囲を決める安全策も遊び方を提案する遊具もない場所に子どもたちを放置してしまうようなものです。(p152)
僕は最近、「どういう制限が子どもたちを自由にするか」について考えているが、このユニット=遊び場は、そのような「子どもたちを自由にする制限」なのだ。単になにもない原っぱに子どもたちを解放すれば、そこに豊かな学びが生まれるわけではない。こういう遊具やしかけがあると子どもたちの遊びが触発され、自然とやってみたくなる。おのずと、教師の側の指導目標も達成できてしまう。子どもたちが自分たちでも独自のルールを定めたり、遊び方を生み出していける。ただの無限に広い野原ではなく、一定程度制限された「遊び場」だからこそ、子どもたちの創造力が刺激される。もちろん、作り込み過ぎてはいけない。これで遊ぶといいですよ、という提案性が高すぎるものは、かえって子どもたちの自律性を奪ってしまうだろう。そうならないように、遊び場をどう設計し、そこにどんな遊具を置くかに、教師の専門性が端的に表れるのだ。この遊び場という比喩は、僕には非常に示唆的だった。
ワークショップはなんのため?
先日の読書会では、「そもそもなぜワークショップなのか?」という冨田さんの話がもっとも興味深かった。いまは特別支援教育に関わっている冨田さんは、「探究の力を育てる」事自体はワークショップの目的としては枝葉であり、一人ひとりの存在を認めることが幹である、という言い方をされていた。「認める」と「育てる」の比率が7:3くらい、とも言っていた気がする。
その後のやり取りの中で、冨田さんがそのように「認める」ことにワークショップの軸足を置く理由も語ってくれた。それは、色々なもの(テストの点数、SNSのフォロワー数や「いいね」の数…)で他者との比較の軸にさらされ、他者より劣っている自意識に襲われることの多い現代の子どもたちの中で、意欲の格差が増大していることを感じているからだという。ワークショップは子ども一人ひとり多様な関わりができ、お互いを承認できる、その土壌を提供するものだと冨田さんは考えている。
「認める」と「育てる」の関係は?
この話はちょっと面白かった。そもそも10年以上前の僕にとって、ライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップは「書く力や読む力を育てるために」始まったからだ。たくさん書き、たくさん読むことが読み書きの力を伸ばす上では欠かせない(これは今でもそう思う)。それで、僕はこの実践をはじめた。その後、僕も経験をつみ、また教える環境も変わって、「育てる」ための土壌として「その子のいまの姿を認める」が必要になることは感じてきたけれど、現時点の関心の中核はあくまで「育てる・力をつける」ことにある。「認める」「育てる」比率も冨田さんの逆でせいぜい3:7くらいだろう。
こういう意識の違いが何に由来するのかは考えたいところだ。もともと僕は教養主義の傾向が強い学校に育ち、前世代の人類の知識を次の世代に伝えることが教育の重要な役割だと考える人間である。「今のあなたにはまだわからないかもしれないが、いったん受け取りなさい」とは、僕が言われ、また僕が自分の子どもに言ってきた言葉だ。こういう僕の教育観が作用している可能性もある。また、近代の公教育が社会化(社会に求められることができる人間を育てる)の装置であることも、好きであろうとなかろうと教員として引き受けなくては筋が通らないという、ある種の潔癖さもあるかもしれない。
一方で、では完全に力がつくことだけを考えてワークショップをやっているのかというと、そんなこともない。特に、ライティング・ワークショップをやっていて嬉しく面白いのは、作品の中にその子の個性が現れてくるのを見る時だ。例えば、アトウェルが『イン・ザ・ミドル』の最後に書いた次の言葉は、僕にもすんなりと受け止められる。
私の自宅の机には、大好きな小説Alone in the Classroomの一節の引用が、すぐ見えるところに貼ってあります。「子どもは、浜辺に転がっている灰色の小石のようなものだ。一人の教師がその小石を手にとって海水にひたす。すると、くすんだ色の小石に、鮮やかな色と模様が浮かび上がる。それは奇跡のようなことなのだ、その小石にとっても、その教師にとっても」。
ライティング/リーディング・ワークショップは、この海の水のような環境です。私たち教師はこの環境を生徒のために整えます。生徒たちを、多様な物語や自己表現のあり方にひたすと、一人ひとりから鮮やかな色と模様が現れます。すべての子どもたちを一律に灰色の石として教えるやり方やプログラムとは正反対です。ワークショップでは、すべての生徒を本物の中にひたすことで、書くこと、読むこと、教師、そして子どもたちの今の時間を、限りなく大切にしているのです。(p343)
「認める」だけでも、「力をつける」だけでもない。「力をつけるために認めるのだ」とすっきり優先順位を語れるわけでもない。直感的には、「認める」と「力をつける」の2つの間で行ったり来たりすることが大事で、もしもどちらか一方に振り切ったとき、僕は教員として大きな可能性を失うように感じる。こういう、僕自身にもまだよくわからない僕の考え方の根っこは、冨田さんのような人と話すことで、共感なり違和感なりの形で少しずつ明らかになる。そして、話すこと、実践することで変化もするだろう。そういう可能性を感じられる、面白い読書会だった。そしてこれこそが、読書会の楽しさでもある。そんな読書会の触媒になった本書は、どんな教科の人が読んでも得るところがあるはずだ。改めて、オススメします。
[ad#ad_inside]