冨田明広・西田雅史・吉田新一郎『社会科ワークショップ』を読んだ。僕は社会科教員ではないけど、素晴らしい本だ。「子どもの姿で語る」とは、まさにこの本のためにある言葉だと思う。自分のライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップを考える上でも参考になることがたくさんあって、付箋をたくさん貼り付ける読書になった。
[ad#ad_inside]シリーズ「ワークショップで学ぶ」の1冊
この本はシリーズ「ワークショップで学ぶ」の1冊。著者の冨田さん(トミー)は元々このシリーズの『読書家の時間』の著者の一人であり、僕もかねてより存じ上げている方。
「作家の時間」でもこんなカンファランスができてしまう、尊敬に値する実践家だ。
5・6年生、こんなにできるんだ!
この本を読んで一番印象に残ったのは、「小学5・6年生ってこんなにできるんだ!」という思い。条例づくり、ガイドツアーキャスト、ニュースの解説者など、この本には多くの実践例が登場するが、その多くが高学年のもの。奇しくも、僕がいま風越学園で受け持つ学年と同じだ。この本の5・6年生の姿からは、学びのコントローラーを徐々に手渡された子供達がいかに躍動するかが見えてくる。ひるがえって、自分がまだまだ学びのコントローラーを子供達に手渡していないのだ。やっているようで、やっていない。本の中身の話でなくて申し訳ないけど、この「あ、自分は仕事サボってるな」という感覚、忘れないようにしたい。
「徐々に責任をゆずりわたす」按配がキモ
もちろん、そういう5・6年生の姿は一気にできるわけではない。筆者たちはフレッシャー&フレイの「責任の段階的移行モデル」(詳しくは下記の本を参照)に基づき、徐々に子供達にコントローラーを手渡していく。
一つのユニットの中に、①教師のモデルを見る、②教師と一緒に学習する、③友達と一緒に学習する、④一人で学習する、の4つの場面を割合を変えつつ織り込み、徐々に子どもの主体性を高めていく。とりわけ、最初は質よりも探究のサイクルをまわすこと自体に注力する。
教師自身が考えているような探究の姿にならず、社会科ワークショップや探究をやめてしまう教師が多いように感じます。初期段階において稚拙な探究になってしまうのは、ある意味では仕方のないことです。大人の行うような探究を教師が見たいがために、はじめた途端に子どもたちの頑張りを否定することがないようにしたいものです。(p101-102)
という言葉は、社会科にも限らず、ライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップをしている自分自身にも向けたい言葉だ。一学期に僕が感じていたなんとなくの手応えのなさ。それは、「教師自身が考えているような探究の姿」を性急に求めていたのかもしれない。
また、この4つの要素のうちの「④一人で学習する」についての次の記述も印象的だった。ほんとその通り。ワークショップスタイルの授業をやる者として、忘れないようにしたい。
個人で学習するということは、一人で黙々と学習することでは決してなく、より自分の責任で行動し、学習の方向性を自分で決められるようにすることです。
こういう姿を目指して、筆者たちは徐々に責任を譲り渡していく。その按配がキモなのが、率直なところ、僕たちに取ってはそれが難しい。でも、この本の大きな価値の一つは、その「譲り渡し」の過程を、第10章や第11章で一年間の流れとして記している点にある。これが大変具体的で良い。例えば、テーマ作り(問い作り)一つを取っても、最初は教師の用意したテーマから選ぶ段階から、すぐにテーマを決めずに、探究しながらテーマを作っていく段階まで、6段階を想定するなど(p271)、決して放任にならない工夫がある。筆者たちの高い力量がうかがえる。
コミュニティーをどう成熟させるか?
上の引用にもあるように、子どもが「個人で学習できるようになる」とは、「ただ一人で学べるようになる」ことではない。コミュニティーの中で、必要に応じて支え合いながら学ぶには、コミュニティーの成熟が不可欠だ。個人的に印象深かったのは、その成熟の段階を書いた「第8章:学習コミュニティーを育てる」だった。ここでは、コミュニティーの成熟が、「発表してファンレターをもらう→ペアで探究する→相手に伝わるように発表を工夫する→コミュニティーに問いかける→発表を参加型にしてディスカッションをする」という5段階で書かれている。おそらくは、背景の理論があるというよりは、筆者たちの経験則に基づいているのだろう。その点はやや残念とはいえ、かなり構成的にペアを組んでいる様子など、コミュニティー作りに苦労している自分にとっては、とても参考になる章だった。ここに登場する子は、様々な特性や課題を持っている。でも、その特性を大事にしながら、より豊かな学びになるようにコミュニティー作りに腐心している著者たちの姿がとても素敵だ。
オンライン公開の章も合わせて読むべき
この本、あまりの充実ゆえに350ページを超えてしまい、やむなく一部をオンラインまわさざるを得なかったようである。第9章「もう一人の教師 教室環境」と、第13章「生活科ワークショップで学習をつくりだす子どもたち」だ。この2つの章は、著者のトミーさんのブログで読むことができる。とりわけ、第9章の下記の書き出しは秀逸だ。ここだけも読む価値がある。
教師があくせくと動き回ってグループごとにカンファランスしている一方で、学習環境という教師は一人ひとり子どもたちを迎え入れ、子どもたちのニーズに応じて、必要な支援が得られるように取り計らってくれます。しかも、お節介な教師のように、丁寧すぎる対応や嫌味を含んだ助言はしません。
環境は大事。僕もようやくこのことが分かってきたので、二学期前に環境構成をもう少し工夫したいな、と改めて思わされる章だった。
学びのコントローラーを手渡す実践記憶
とまあ、実践が充実していて、読み応えのある本だった。教師の関わりと、コミュニティーと、環境の力によって、子どもたちがどんなふうに自分でテーマを持ち、探究するようになっていくか。本書は、学びのコントローラーを子どもたちに手渡す実践記録である。もちろん念のため書いておくと、子どもたちは決してただ自由に学びたいことを学んでいるわけではない。学習指導要領から外れないよう、学習の単位であるユニット(単元)はわりあい狭い範囲で設定されている。ユニットの最初に教師が「テーマの卵」を示し、子どもがそこから自分の探究テーマを選択できるようにするので、学習指導要領を外れるわけではない(そういう方向づけは、カンファランスを通じても行われている)。また、教科書の内容についてのロングレッスン(一斉授業)もある。こういう点も、学習指導要領という制約のある学校で働く読者の背を押してくれるだろう。何よりも、僕が背中を押された。ちょうど風越でも、どうやって学びのコントローラーを子供達にもっと手渡していくかが話題になていたのだ。そのタイミングでこの本を読めたことは、本当にラッキーだった。社会科教師でなくても、オススメの一冊です!
[ad#ad_inside]


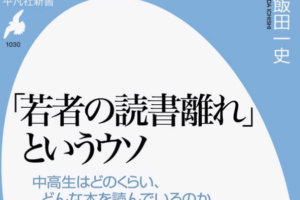






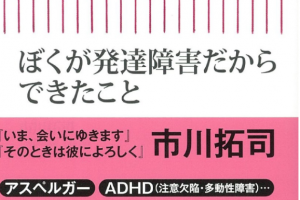
![[読書] 2018年1月に読んだ本。ベストは2冊の新書。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2018/02/still-life-3097682_640-50x50.jpg)

![[読書]待ちに待った読書教育の基本文献!日本読書学会「読書教育の未来」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2019/09/スクリーンショット-2019-09-04-19.31.02-50x50.png)