とにかく名著だった。ちくまプリマー新書の鳥羽和久『君は君の人生の主役になれ』は、10代の青少年に向けて、大人からの抑圧に負けずに生きることを説く本で、僕たち大人に対して、自身が「善良な抑圧者」になっていることを気づかせる本でもある。でもそれだけではない。自分が抑圧される社会構造の中で生きてきた僕たちにも、赦しとエールを送っている。そんなパワーを持った本だ。僕が個人的につけてる読書記録でも10点満点。今年のベスト本候補かも!
[ad#ad_inside]子どもたちへの洞察と愛情にあふれた本
この著者に対してまず感じるのは、子どもたちが生きる社会の構造への洞察の深さと、その洞察を支える愛情の深さである。例えば第1章「学校に支配されないためのメソッド」では、「繊細すぎる」と周囲に見られ、その言葉も本人も内面化した高1の「亜美さん」が、どういうクラスの人間関係の中で抑圧されてきたかを考える。そして、休みの日にBTSの動画ばかり見ているという彼女に、「テテと繋がってるなら、世界と繋がってるということだよ」と声がけする(p44)。なんと美しい語りだろうと思う。
また、第2章「自分独特の世界を生きる」では、「ワンチャン」という若者言葉の背景にある彼らの気分を「レジスタンス」と呼び、次のように意味づける。
そんな時代(引用者注:「スタートラインにみんなが平等に立っている」前提の虚構性が明るみになった時代)に生きているみんなは、偶然性を「ワンチャン」の一言でみずからの味方に変え、それと戯れることで大人の設定を揺さぶり、嘘を暴いてしまいます。「誰でもがんばれば成果が出る」よりも「オレでもワンチャンいけるんじゃね」のほうがリアリティもあるし希望もある。大人の嘘よりもずっと響きがよくて、頼もしい感じがします。(p77)
こういう「ワンチャン」という言葉の持つ時代性への洞察、そしてそれを支える子どもへの愛情。これが、本書の全体の基調をなしている。他でも、この第2章では最近の学校で「正しさ」を獲得している「LGBTへの配慮」をめぐる言説の中に、マイノリティを差別する構造が潜んでいることを暴露する。そして、「自分を善良の立場に置くことがいつも差別の構造の根本にある」(p90)こと無自覚で、いつも「差別がないという装いだけが整えられた世界」(p95)の中で生きる子どもたちに、次のように呼びかける。
あなたはこれからも、善き人を追い求めながら、そのたびに悪どい自分を見出して絶望しながら、生き抜いてください(p106)。
この言葉に、子どもという存在へのとても深い愛を感じるのは僕だけではないはずだ。
全ての親を刺し、そして赦しもする第3章
第3章「親からの逃走線を確保する」は、親としてとても考えさせられる章だった。僕には、いま高校生の娘と中学生の息子がいる。もちろん子どもは僕自身ではないし、娘と息子も違う個性を持つ人格だ。それなのに、勝手に娘に自分を投影してみたり、息子に「姉だったら」と娘を投影してみたりする。
例えば、勉強について。子どもたちはどちらも中学受験もしていないし塾にも行っていない(行かせていない)。少なくとも、我が家は表面的には「子どもに勉強させる教育熱心な親」ではない。でも一方で、僕も妻も勉強が得意だった高学校歴(どちらも東大卒)の人でもある。となると家庭の中に、「学校の勉強はちゃんとやろうね」「本をたくさん読もうね」「色々広く学んで知識を身につけると楽しいよ」という雰囲気は、どうしてもにじみ出てしまう。
そして僕の場合は、「放っておいても中学校くらいまでの勉強なら普通にできるんじゃないか」「普通はこういうものに興味を持つんじゃないか(持ってくれたらいいな)」という「普通」のラインを、ごく自然に自分基準で設定してしまうところがあった。こういう、自分では特に「期待」している自覚のない、「普通」という名の暴力が、子どもへの抑圧としてどれほど強く働き、僕たちの親子関係に影響しているだろう。章は変わるのだが、第5章「勉強という名のレジスタンス」でも、子どもを高く見積もる親が出てきて、次のように批判されていた。ほんと、その通りですよね…。
いつも子どもを高く見積もろうとする親が「うちの子は自信がない」「自己肯定感が足りない」と言うのを聞くと、自分が地獄の脚本を書いてることにまず気づけよと、私なんかは思うわけです。(p208)
いま中2の息子が、中1の時のことだ。こうした僕らの無自覚な抑圧に、彼が勇気を出して反抗してきたことがきっかけで、僕は自分の「期待」との落差で子どもを見ることをやめようと決意するのだが、今もなお、それはそう簡単ではない。「親は子どもに何ができるって、彼らの人生の邪魔さえしなければ及第点なのですが、それがなかなか難しい」(p123)と、筆者が書いている通りだ。
自分のことを長く書きすぎた。本書では、親が巧妙なロジックを駆使して子どもに自分の「期待」を押し付けてくる様子が、具体的に書かれている。この本の本来の宛先である中高生の読者は、この章を読んで自分を守ってほしい。親は、自分の振る舞いを振り返って、きっと色々と思うところがあるはずだ。
ところで、このブログのような教育系のブログの読者には、僕とは違って親の期待を無自覚に子どもに押し付けず、子どもを否定せず、主体性を尊重する理解のある「良き親」たらんとする方もたくさんいると思う。では、その人たちは「合格」なのだろうか。それが違うのである。次のような文章を読めば明らかだ。
そうやってあなたに理解を示し続ける「いい親」こそが、結果的にあなたをいつまでも「いい子」に縛りつけてしまい、あなたの抵抗力を根こそぎ奪ってしまうのです。それは最も優しい子育てのようで最も残酷な子育てなのに、親もあなたもそこのことに気づきません。(p143-144)
また、子どもの自己肯定感を育てる子育てとしてしばしば言及されるリフレーミング(否定語をポジティブな言葉に変換すること)にはもっと辛辣だ(が、これはまあ僕も以前から同じように思っていたのではあるけど)。
リフレーミングを意識する親は、「私が子どもにこう働きかければ子どもはそうなる」というコントロールの欲望をむき出しにしていますよね。子どもをコントロールしたいからこそ、狡猾なやり口に惹かれるわけです。(p145)
さらに、第5章でも、「宿題が嫌ならやらなくていい」という「物分かりのいい大人」が出てきて、そういう大人を信用してはいけないと痛烈に批判している。
「勉強が苦しいならやらなくていい」と子どもに言う大人は、実は子どもの人生を一つの作品のようにきれいに仕上げたいと思っているのかもしれません。こういう自分の理想の生き方をあなたに肩代わりしてもらおうとする人は要注意です。(p202)
著者は、こういう大人、特に親の本質を「自分が傷つくことがない安全地帯から、子どもを気遣うことを通して自分を守っているだけ」(p144)と看破する。そして、子どもの主体性の形成には親の持つ「否定」の力が不可欠であることもあわせて説くのである。
ここまで読むと、「ではどうすればいいのか?」と思いたくなる読者もいるかもしれない。でも、そうではないのだ。良い悪いではなくて、親子関係とはそういうものなのだ。筆者が第3章で言っているのは、おそらくそれに尽きる。親はどうしても子どもを自分のストーリーに巻き込んでしまう。どうあってもそうしてしまう。子どもはそれに抗わねばならない。その双方の力で、子どもの自己は形成されていく。そのことに自覚的でありたい。その意味で、この章で親は単に批判されているわけではない。親は刺されもするし、赦されもする。「人間ってそういうものだ」という筆者の深い愛情を、子どもだけでもなく、親に対しても感じる章である。
洞察に溢れ、力のある言葉たち
僕自身は、親子関係のところが一番印象に残ったので、本エントリでもそこを中心に書いてきた。でも、第2章にある差別の構造の話、第4章「お金で回る世界」にある資本主義と人間性の話、どちらも対話形式で書かれたこの2つの章も、とても読み応えがあるのだ。特に第4章の「教育にかかわらずあらゆるサービス業の人はいとも簡単に詐欺行為の片棒を担ぐことになる可能性に気付いてないと、資本主義の誘惑に抵抗できない」(p187)という言葉は、僕にも苦い思いがある。だから、ぜひ他の章も手に取って読んでほしい。
このエントリで、いくつもの筆者の言葉を引用してきた。それは、筆者の言葉にとても力があり、文章が魅力的だからだ。「ワンチャン」のような言葉の背後に想いを巡らせる筆者の力量が、彼自身の文章の中でも存分に発揮されている。もしこの本が『中高生のための文章読本』の編集時期に間に合っていたら、僕は間違いなく絶対に推していたし、おそらく収録されていたと思う。
自分の子どもたち用にも買って手渡したい。でも、親の勧めだと読んでくれないかなあ。彼らが信頼している他の誰かから、手渡してもらいたいくらいだ。また、同じ筆者の『おやときどきこども』も読んでみたい。こっちは親向けかな?風越の保護者と読書会してみたいなあ。
とまあ、とても良い読書体験だった。この本を咀嚼できるのは読書力のある中高生かもしれないが、10代以上の全ての人におすすめ。私たちは、みんな矛盾を抱えていて、それに苦しみながらもなお生きていく。中高生以上、全年齢の人に向けた、グサッと知的に刺さる人生のエールだ。
[ad#ad_inside]

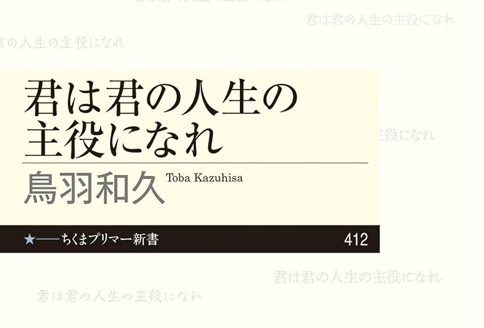
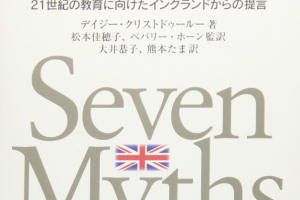

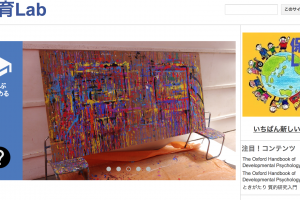





![[資料] 便利な表形式で読んでみよう!新学習指導要領・国語](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/06/スクリーンショット-2017-06-22-0.11.14-50x50.png)
