青山新吾『エピソード語りで見えてくるインクルーシブ教育の視点』を読んだ。今回この本を読んだきっかけは、僕も参加させてもらっている、横浜の『読書家の時間』の編著者の先生方を運営の中心とする「大人のブッククラブ」である。著者の青山さん自身がゲストで、ご本人に色々と質問ができたのも良かった。ほ本書は「エピソード語り」を通してインクルーシブ教育について必要な視点を考えていく。読んでみると、どの子をみる時にも大切な構えを書いた本である。
[ad#ad_inside]
「エピソード語り」という手法
まずは、本書の鍵となる手法「エピソード語り」という提案が面白かった。「エピソード」というと教室での出来事を物語風に時系列に沿って語るイメージをしてしまうが、本書では、エピソード語りが次のように説明されている。
エピソードを綴るといっても、それは単に体験談を記述するのとは違います。エピソード綴りの中には、知識であったり、技術であったり、そして、登場する人物の内面であったり、もしくは、語っている自分自身の内面であったり、そして、登場する人たち同士の関係性であったり、登場人物と自身との関係性であったりとさまざまな様子を落とし込んで表現をしていきます。ただ単にあったことを順番に記述しているものとは違うわけです。(p22)
また、本書の後半にももう一度同じ話が出てくる。
ここで言っているエピソード綴りというのは、単なる体験の言語化とは違います。エピソードの中に知識や技術、また内面、それも相手の、例えば登場人物が子どもであれば子どもの内面、と同時に語り手である自分自身の内面について、そして例えば自身と子どもの関係性であったり、登場する大人と子どもの関係性であったり、子ども同士の関係性であったり。そういったことをエピソードの中に落とし込んで表現していくものなのです。(p75)
どちらでも強調されているのは、エピソード語りが単なる体験の言語化・物語化ではないということだ。僕たち教師は、目の前の現実を、例えば「子どもの成長」のような美しいフレームで、あるいは自己正当化のフレームで、物語化しがちである。それらはたいてい自己慰撫のための物語で、現状を肯定こそすれ、それを変える力は持っていない。そこに登場する「子ども」は、あくまで教師の語りの中で対象化され語られる、要するに語り手の教師に都合の良い存在になってしまっている。
しかし、本書の「エピソード語り」とは、こういう形で安易に物語化されがちな子どものストーリーに、子どもの内面や自身と子どもとの関係性などの視点を入れることで、安易な物語化を防ぐフレームワークとなっている。そして、青山さんは、このフレームワークを使いながら教師とやりとりをしていく。
例えば、生まれてから人の言うことを一度も聞いたようなことがない子が、自動販売機に職場体験に行きたいと言い出した時、「どう支援をするか」の前に、その子にとって自動販売機がどのような存在かを考える(p27)。また、ボール当て鬼に参加できなかった子が参加できるようになった時には、その子にボールを当てた子の存在を聞く(p82)。こうやって、教師が最初に作る単一の物語をさまざまな視点から検討して、複数の声が響く物語に改編するのが、エピソード語りの手法である。この際、この物語が「正しい」かどうかはどうでもいい。それよりも、この作業の中で、登場人物だった「支援を要する子」がどういう子なのか、教師とどういう関係性なのかが見えてきたり、他の登場人物を登場させることで子ども同士の関係性の中で解決する糸口を探ったりできるところに価値があるのだ。これが、教師一人の視点から見たナラティブではないことは、何度でも書いておきたい。原理的にも、一人ではなく学校の複数人で行う方が良いはずで、子どものケース会議などで使うにはぴったりだと思う。
インクルーシブ教育の鍵となる視点
そういうエピソード語りを通して、「支援の前に人づきあい」や「やさしいどうして?の発想」など、インクルーシブ教育の鍵となる視点がいくつも提案されるのが、本書の第二の特徴である。「大人のブッククラブ」での青木先生の発言によると、ここに書かれた視点はサッカーで言う「オシム・ジャパンの戦術」、つまりは、日本サッカー国際化初期のオシム監督が、当時の選手に教えたように、本当の基礎基本の部分だけを徹底して書いたものなのだそうだ。(と書きつつ、僕はドーハの悲劇でさえ名前は聞いたことあるぞ程度の人間なので、よくわかっていない笑)。
苦手です…「やさしいどうして?」の発想
この「やさしいどうして?の発想」とは、要するに、例えば子どもが問題行動を起こしたときに、教師が自分の想像する文脈をいったん脇に置いて、どうして子どもがその行動をとるのか、彼の背後の文脈をあれやこれやと考えてみること、である。
こういう「その子の文脈を考えること」、実は自分で苦手だなあという自覚がある。僕が子どもの頃から大量の読書をした結果、他者への想像力が養われれば良かったのだけど、どうも現実はそうではないらしい。僕には特に非文字コミュニケーションにおいて、思い込みが強かったり、偏った解釈をしたり、他者の行為の文脈を自分で決めつけて間違えたりすることが、ままあるのだ。
これはきっと僕の性格が真面目であること(=自分で必要性を感じた文脈に対してはきちんと力を尽くすこと)や、雑談が苦手なこと(=文脈がつかめないコミュニケーションが苦手なこと。全ての会話で議題が決まっていてほしい)、そしてユーモアのセンスがないこと(=笑いとは、日常のコミュニケーションの文脈からの逸脱である)などともつながる、根が深い問題だと思っている。僕は自分で自分を本質的には小学校教員には向いてないなあと感じているが、それも、学年が下がると教科専門性よりも個人としてのコミュニケーション力がけっこう重要になってくるから。このへんは、生まれ持った性質として今更どうにもできない部分もあるだろうが、でも、ちょっとでもトレーニングでカバーできたらいいなあと思う。
また、相手の物語を想像する上では、やはり知識が必要だとも感じる。たとえば本書に出てくるお弁当のエピソード(p46)は、仮に僕にどんなに考える時間があっても、「彼は本当はこうだったのかな?」を想像するには、知識が決定的に足りていない。今さら特別支援教育の専門家のような知識を身に付けるのは現実的でもないし僕の希望でもないのだが、最低限の知識ってどういうものだろう?
フィードバックをもらいつつ…
とまあ、課題は多いけど、何か起きた時にすぐに自分一人の物語で判断しないで、「やさしいどうして?」で色々と考えてみること、そして面白がってみること、できるように頑張りたい。幸いというか、風越は学校全体としてこういう個々の子どもの物語を見ようとする人も多く、実際に特別支援教育出身スタッフも何人もいる。フィードバックをもらいつつ学ぶには良い環境のはずだ。
ちなみにこの本、「インクルーシブ発想の教育シリーズ」4巻目で、第2巻は風越学園校長のゴリさん(岩瀬直樹さん)との共著だった。こちらも手に取ってみよう。
[ad#ad_inside]
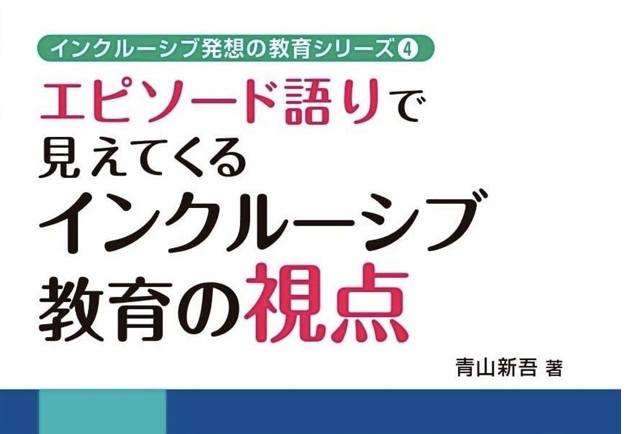
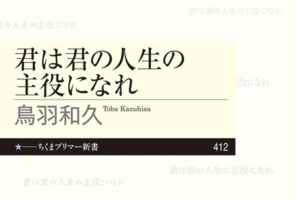



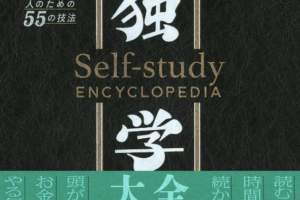




![[告知]12月3日(日)、軽井沢町中央公民館で子どもの本のイベント「本日和」が開催されます!風越の「マイプロ」発のイベントです、来てね。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2023/11/5ebe669fce8614466135521bf884585e-50x50.png)
