『君は君の人生の主役になれ』で知った鳥羽和久さんの前著にあたる、鳥羽和久『おやときどきこども』を読んだ。『君は君の人生の主役になれ』で感じた筆者の子ども(そして、いまだに未成熟な親自身)への視線の温かさなどは、本書でも共通している。このエントリでは、本の感想ではなく、本を読んで触発されたことについて書いた。具体的には、本書に出てきた「遊びと企て」「意志と責任」というトピックから、軽井沢風越学園での出来事や、そこでの自分の関わりについて考えたことだ。本一冊全体のレビューではないのだが、自分なりの読書の記録としてここに残しておきたい。
[ad#ad_inside]学校教育における「遊び」と「企て」
学校教員の仕事は矛盾の塊だ。同じ口から「勉強は大事だよ、頑張ろう」も言えば、「勉強なんかどうでもいいよ。それより大事なことはいっぱいあるよ」も言うのだから。そのことを改めて考えたのが、第二章「大人の葛藤の中身」の「遊びと企て」という文章だった。ここで、筆者は西村清和『電脳遊戯の少年少女たち』(懐かしい! 本書は現代文教員のふた昔前の定番書だった)を引用しながら、私達の生活には「企て」(目的を持ってその実現に向かっていく行為)と「遊び」(それ自体は目的をともなわない行為)の2つがあると説明する。
私たちは「企て」と「遊び」の両方を享受しなければ満たされません。日々の生活にメリハリをつける目標や動機付けは欠かせませんし、勉強や仕事などの生活のために必要な行為は、広い意味ではすべてが「企て」と言えるものです。一方で、精神の緊張が伴う「企て」の狭間には、心をほどく「遊び」の時間が必要になるでしょう。「遊び」はいま生きていると言う実感に直結するものなので、それを通して初めて私たちは誰のためでもなく自分のために生きるという喜びを知ることになるのです。(p150)
そして、筆者も指摘する通り、学校とは基本的に「いかに子どもたちの『企て』を加速させるかということが最優先課題とされるような場所」であり、教師は「子どもを『企て』に駆り立てることを生業にしている」存在である(p154)。これは、学校が国家プロジェクトとして行われている以上、不可避の性質だ。
一方で、でも学校が「企て」的な意図に満ちた空間になると、それは多くの子にとって(特に優劣の劣位に置かれる子にとって)地獄となる。だから教師は意図的にそうした序列を崩したり、目的のない「遊び」的時間を演出したりすることで、一種のガス抜きを図る。全体としては「企て」に子どもを向かわせつつ、「遊び」も取り込んでいく。ここで教師は2つの原理に向き合うことになる。
2つの矛盾した原理に向き合う
この場合、「企て」か「遊び」のどちらか一方の原理に逃げ込む方が楽なのだが、矛盾をきちんと抱え込み、どちらも手放さないことが大事だ。筆者は別の場所で、別の話題についてだが、次のようにも言っている。
私たちは、自分の中に生じた矛盾を頭ごなしに否定し、それを無理にでも排除してしまおうと考えがちです。でも、そうやって一貫性を求めすぎることが間違いのもとなのでしょう。白黒つけることより矛盾のほうがほんとうならば、その矛盾ととことん付き合ってみよう、それをよく噛んで味わってみようと最近は考えるようになりました(p147)
僕自身も、授業作りの上で、一見矛盾した要素を授業に入れること(一つの原理で授業を統一しないこと)が大事だと思っている。だから「企て」的な、明確な目的で子どもたちを一つの方向に向かわせる場面と、逆に彼らが自由に思い思いに楽しくできる「遊び」的場面という、2つ場面を授業に取り込んでいて、その最適なバランスを探っている。どちらも手放したくないのだ。
もちろん、最終的には学校は「企て」に子どもたちを向かわせる場所なので、ここでの「どちらも手放さない」とは、要するに方法的欺瞞なのだ。しかし、その欺瞞を知って実行する強さ、そんな自分から目を逸らさない誠実さも、教師には必要だ。好むと好まざるとに関わらず、教師とはそういう仕事なのだと思う。
「わたしをつくる時間」をどうする…?
さて、軽井沢風越学園には、「わたしをつくる時間」と呼ばれる時間がある。子どもが自分でやりたいことをやる、特徴的な時間だ。この時間の狙いを僕の言葉でひとことで言うと、「自分を好きになる時間」。国語や算数やテーマプロジェクトや、基本的にスタッフから出会って欲しいものを手渡される子どもたちが、ここでは自分からやりたいことを選ぶ。それだけ「楽しい!」と思える機会も、「自分っていいじゃん!」と思える機会も多いはずだ。そして、そういう手応えが、彼らが色々な学びに向かうエネルギーになる。
しかし、そうは言っても実際の子どもたちの姿を見ると「これでいいのかな」と思ってしまうことも少なくない。僕たちスタッフから見るとのんびりと休み時間と区別がつかないような感じで過ごす子も少なくないし、なんとなくネットを見て過ごす子も正直言っているからだ。勉強している子も、友達と一緒におしゃべりしながらだったりで、大人の目から見ると明らかに効率が悪い。
そこが物足りずに、もっとこの時間を充実させたくて、僕のいる5・6年生では「味見の会」という、自分がこの時間にしていることをクラスメートや保護者に共有する発表会を作ることにした。
しかし、本書『おやときどきこども』を読むと、要するにこういう対応が、子どもたちの「遊び」の時間を、「企て」の時間に変換してしまう危険性に思い至る。そしてその根っこにあるのは、目的的に動きたいという大人(要するに僕)の欲求だったり、自分の理想通りに子どもたちが動かないことへの大人(要するに僕)の不安だったりするのだ。問題に見える現象は、僕という観察者のフィルターを通すことで初めて生起する。そして、その現象に対応して、マイプロジェクトを「やらせよう」としてしまう。
こうして「遊び」を侵食する形で、ある目的を達成するための「企て」が子どもの生活の大半を占めていくことになります(p152)
軽井沢風越学園は、ほんらい幼児期からの「遊び」の時間を大切にしようと生まれた学校だった。だとしたら、子どもたちにとっては公的に承認された「遊び」の時間でもある「わたしをつくる時間」を、教員目線でプロジェクトとして充実させようとすること、つまり「企て」の時間へと転換を図ることは、果たして良いことなのだろうか。「遊び」と「企て」のバランスを、風越学園ではどう考えているのか。「わたしをつくる時間」をどう評価し、どうしたいのかは、風越学園にとってかなり大きな問いである気がした。
子どもの主体性を尊重するという罠
同様に考えさせられたのが、第3章「子どもと意志」の中の「意志と責任」。これも、僕も現代文教員時代によく読んだ自由意志論や意志と責任の哲学をベースにした文章で、子どもの主体性を尊重する態度の罠について書いてある。親も教員も耳の痛い文章だ。例えば、次の文章を読んで我が身を顧みない人はいるのだろうか。
子どもに対して「がんばる意志(=やる気)を見せなさい。目標を持ちなさい」と迫る親は、子どもが意志や目標をなんとか無理やりに絞り出したとたんに、「自分でがんばるって言ったんでしょ!」とそれを表明した「責任」を子に取らせようと血眼になります。
このように、意志や目標というのはたびたび大人が子どもに「責任」を取らせるための罠として使われます。だから、言質を取られることに気づいた子どもは決まって無口になります。(p197)
また、小中学校受験をする子の親はもちろん、「教育熱心で」「良心的な」保護者には、我が子に対して無意識に次のように接してしまった親も少なくないのではないか。僕はまさにそうであった。
小中学校受験をする子どもの親の中には、「子どもの意志を尊重して」受験させたことをやたら強弁する人たちがいます。その親たちは、受験が大人の押し付けではなく本人の意志なのだと主張することで、自身が本人の自主性を尊重する親であるとアピールしたいのでしょう。……(中略)……
しかし問題は、このような親がたびたび子どもの「意志」を言質にとって子どもにがんばる責任と義務を押し付けることです。親は自分の欲望を叶えようと執拗に子どもを責め続けます。「あなたが頑張ると言ったから応援してるのよ。」「自分で受験すると言ったんだから、最後まで全力でやりなさいよ。」親は意志を表明した子どもに対して、自分でやると言ったんだから責任を取れと、苛烈に責め立てます。こうやって責めを負い続けた子どもはいったいどうなってしまうのでしょうか。意志を示すと責められることを知った子どもが、次なる意志を持つことが果たしてできるのでしょうか。(p198-199)
「あなたはどうしたいの?」という問いかけ
ことは、家庭だけの話ではない。軽井沢風越学園のスタッフは、子どもの意志をとにかくよく聞く。「あなたはどう思ったの?」「あなたはこれからどうしたいの?」「あなたは何をやりたいの?」。こうしたやりとりは、子どもの意志を無視して「これをやりなさい」と言うよりは一見柔らかだし、好ましい。
だが、下手をすれば、その結果に子ども自身をコミットさせる、そうせざるを得ない状況に子ども自身を巻き込む点においては、ただの命令よりも一層苛烈である。「あなたはどうしたいの?」が常に「そう言ったんだからやりなさい」とセットになっていたら、そりゃあ子どももたまらないだろう。そうならないように、細心の注意が必要なわけだ。
「作家の時間」の目標と振り返り
これに関して僕が思い出すのは「作家の時間」の評価の話である。僕は去年まで、半年に一度の面談(評価カンファランス)で、次の半年の目標を設定していた(下記エントリ参照)。
これは僕が共訳した『イン・ザ・ミドル』のナンシー・アトウェルの評価カンファランスに倣ったもので、「目標→実行→振り返り→次の目標」というサイクルを回そうとしたものだ。
ただ、二年間このやり方でやってみると、目標を立てるのはよくても、その目標を実際にやるかやらないかは本人次第にして、間違っても「やらせよう」としないほうがいいと思った。そうでないと、当人にはもうその気がないのに、こちらが「自分の立てた目標なんだから達成しなさい」と言い続けるハメになってしまうからだ。「あなたはどうしたいの?」の答えは、話した本人も忘れてしまうくらいでもいい。言ったこととは違っていても、その子が実際にやっていることが、やりたいことの全てなのだ。
「目標設定とその遂行」という、子どもがきちんと「企て」るための網の目を、授業の中で細かく張りめぐらせると、子どもたちはどんどん息苦しくなってしまう。学校が学ぶ場所である以上、網の目を張ることは必要なのだが、その目の間から、子ども自身がすり抜けられるくらいがちょうど良い。
「意志と責任のスパイラル」から子どもを守る
僕たちは、どうしたら「意志と責任のスパイラル」に子どもを巻き込まずに済むのだろう。本書では、具体的なテクニックとして、リフレクティングの手法が紹介されている。これは、三者面談の場などで、決して子どもに「あなたはどうしたいの?」と聞くのではなく、直接的アドバイスをするのでもなく、大人(筆者と保護者)同士の会話を媒介に本人の意志が浮かび上がってくるのを待つ方法だ(p209)。質問も助言もしないで自然と本人の意思決定を誘うやり方なので、自分でも心がけてみようと思う。
自分の現場の鏡となるエピソードたち
そういえば、本書の書き方自体も、このリフレクティングを想起させるところがある。決して読者である僕たち自身について語ることはなく、塾の生徒や保護者とのエピソードを中心に綴られている。にもかかわらず、そこに書かれている(聞かされている)エピソードを鏡にして、僕たち読者は自然と自分ならどう考えるかに誘われる。
今回の読書では、「遊びと企て」「意志と責任」の2つの文章がとりわけ今の自分を照らす鏡になった。この2つはどちらも「子どもの意志(主体性)をどうしたら大人が潰さずに済むか」「どうしたら目の前の子どもを大人である自分自身から守るか」という問題意識の共通点があって、今の自分はそこに引っ掛かりがあるのかもしれない。
ただ、他にも線を引きたくなる箇所はたくさんあった。この本を保護者と一緒に読んでみたい。読んで、子どもを理解するのではなく、子どもと自分との関係性を理解し、自分達の不完全さを知り、でもそのままを受け入れるしかないことも、語り合ってみたい。
[ad#ad_inside]

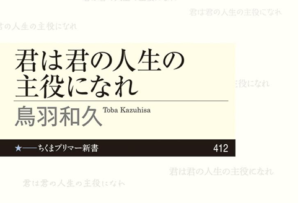



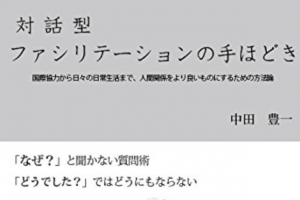
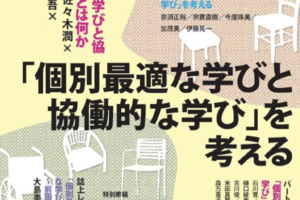
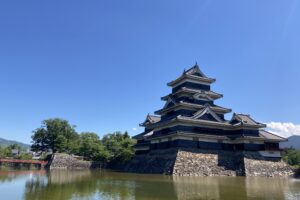



![[読書] ちょっともったいないかも? リヒテルズ直子・苫野一徳『公教育をイチから考えよう』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/12/スクリーンショット-2016-12-29-21.14.49-50x50.png)

