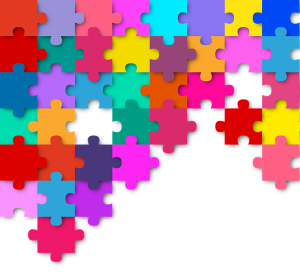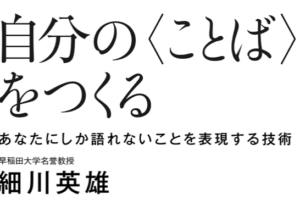この本、ちょっと煽りっぽいタイトル&帯(「脳科学に基づく授業改善!」「世界が驚愕した教育書ついに上陸」)なのですが、おすすめです。原題はWhy Don’t Students Like School?。ここ30年ほどの認知心理学の研究成果から、学習に関する基本的な原理を選びあげ、そこから実際の教育への応用を考える本です。そういう意味で「教師の勝算」という邦題もあながち間違ってはいません。
9つの認知原理
まず誤解ないように書いておくと、「勉強嫌いを好きにする魔法のような9つの方法」は書いていません。その代わり、認知心理学の見地から、学習する上で大切な9つの認知原則を上げ、それに基づく具体的な授業改善が書かれています。ここにその原則を上げておきましょう。
- 人間は生まれながら好奇心が強い生き物だが、もともと考えることが得意なわけではない。認知的な条件が整わなければ、考えることを避けようとする。
- 技能より先に事実的な知識が必要
- 記憶は思考の残渣である。
- 私たちは、すでに知っている事柄に結びつけて新しい事柄を理解するが、私たちが知っていることの大部分は具体的なことである。
- 十分な練習なくして知的活動をマスターすることはできない。
- 初心者と熟達者の認知能力は根本的に異なる。
- 子どもの思考方法と学習スタイルには、相違点より共通点の方が多い。
- 子どもの知能には違いがあるが、たゆまず努力を重ねることで知能に変化を及ぼすことができる。
- 教えることも、他の複雑な認知的原理と同様、上達するには練習が必要である。
1〜8までは具体的な授業改善につながる原理、そして最後の9に教師自身の成長について書いてあるのがユニークです。
どうしたらよく「記憶」できるのか?
ここでは、この9つの原理について網羅的に書くことはしません(興味のある方は本をお読みください)が、総じて「学びに王道なし」という印象です。ざっくり書くと、根本にあるのは、学習するとは知識を記憶すること(=長期記憶に入れて無意識化できるようになること)。したがって、教師の仕事はいかに子どもたちによく記憶してもらうかだ、という姿勢です。
記憶すると言っても、別に単語帳を用いた「丸暗記」を推奨しているのでもありません。関連性のない事柄の記憶は、人を退屈で苦痛にさせるからです(p97)。筆者は、知識定着に効果的な様々な方略を説明してくれます。
例えば、問いかけて興味を持ってもらうこと、生徒に覚えて欲しいことについて考える時間を多く提供すること(考えることで記憶できるから)、生徒に題材の持つ意味について考えてもらうこと(これは「子供が好きな事柄と関連づけること」とは違います。子どもの好みに寄せるとむしろそっちに意識が行くので批判的です。p118)、物語の形式を使って説明すること、間隔をあけて練習を繰り返すこと…こういう工夫によって、知識はワーキングメモリから長期記憶に蓄えられやすくなります。そしてその知識を無意識に再生・実行できるようになった時、僕たちはそのことに熟達した=学んだと言えるわけです。
以下、僕の観点からいくつか興味をひいた話題について、感想とともに書いていきます。
好奇心を過信しないことが大事
「人間はもともと好奇心が強い」けれど、同時に「考えるのを面倒臭がる」生き物(原理1)。だからその好奇心は長続きせず、できるだけ考えるのを避ける傾向がある。したがって、その好奇心を長続きさせるには、「簡単ではないが解けそうな問題」を与えて、喜びや満足を与える必要があるそうです。好奇心は「飽きやすい」ので、その力を過大評価しない方が良さそう。
この原理からは、生徒の好奇心に任せず、能力相応の個別課題を用意する大切さがわかります。一人一人のワーキングメモリには個人差があり、負荷の重すぎる問題に向き合い続けると、人はそれを避けようとします。したがって、一人一人に「挑戦しがいのあるちょうどいい課題」を用意することが、好奇心を維持する上でも、学習では大事になってくる。学びの個別化の意義はそこにあるわけですね。また、生徒の好奇心はあくまできっかけにはなるけれど移ろいやすいものなので、そこを重視しすぎる必要もなさそうです。
読解における知識の大切さ、そして読書の大切さ
この本では、「認知スキル」に関することでも知識の役割が重要であることも強調されています(原理2)。下記の本でも、この本を参考文献にして同じことが書かれていました。
読解力の上で背景知識が重要な理由
- 語彙を提供してくれる
- 書き手が残す論理的なギャップを埋めてくれる
- チャンク化(ばらばらの要素をまとまりとして捉えること)が可能となるため、ワーキングメモリの余裕が増え、概念同士を結びつけるのが容易になる
- 曖昧な文の解釈を誘導してくれる
これは、読解における知識の効用のわかりやすいまとめになっています。そして同時に、こうした背景知識や語彙を手にいれる有力な手段が読書でもあるので、自分に合ったレベルの本を読むことも大事(p95)。この主張は、猪原敬介さんの『読書と言語能力』とも一致します。やはり、読書は大事なのだ!ということ。
どうやって知識の転移を生むのか?
「知識の転移は起きにくい」という有名な話題も、この本では丁寧に説明されています。僕たちはある知識を生徒に学習させると、それを別の問題にも使ってもらう(知識が転移する)ことを期待してしまいますが、実際にはこれはなかなか起きません。ちょっとシチュエーションが変わると似たような文章題の問題でも解けなくなります。知識の転移は本来非常に起きにくく、それが学習の阻害になっています。
この本によると、転移が起きにくいのは、僕たちの理解がその問題の表層的な構造にばかり目がいく「浅い知識」に止まっているからです。表層的な構造が似ている2つの問題ならそれでも転移は起きますが、「表面上は似ていないが深層構造は同じ」問題だと、その深層構造の共通性に目がいかず、転移は起きない。
ここで重要なのがやはり「練習」。十分な練習は、作業を自動化してワーキングメモリーの負担を軽減する他、学習が新しい状況に転移する可能性も高めてくれます(p215)。同様に、ある物事に熟達している人は、深い知識に達して深層構造に目がいくようになるので、転移しやすくなることもあります(p236)。
ドリル的とも見られる反復練習と、一つのものごとを深く探究する探究学習。一見正反対の2つの学習ですが、どちらも知識の転移を促す大事な役割があるわけですね。「あれかこれか」に陥らないようにしないといけない、と思いました。
とはいえ、探究学習については「覚えて欲しいことを子どもが深く考えるという点で効果的だが、考える内容をコントロールできない(誤った発見にも意味があると思って記憶してしまう)」として、問題について正しく考えているかどうか子どもが迅速なフィードバックを得られる環境があれば効果的と、全体的に慎重な立場でした(p150)。
「本物アプローチ」の限界
また、下記エントリでも触れた「本物アプローチ」(真正な文脈を設定した学習)の限界についても、この本ではより詳しく書かれています。
初心者には、熟達者が持っている膨大な背景知識がないため、問題の表面的な構造しか認知することができません。熟達者は、問題を機能的な深いレベルで見ることができ、またルーティーン作業を長期記憶に基づいて無意識にできるからこそ、熟達者なのです。したがって、初心者が熟達者のように振る舞うのは難しい。それができるようになるには、俗に「10年ルール」と言われる膨大な訓練が必要になります(熟達には10年かかる…というアレです)。
筆者もこうした「本物アプローチ」が学習者のやる気を高める点については認めていますが、このアプローチによって学習者の能力そのものが高まることはないと言います。トッププロのテニスプレイヤーは戦略を考えてプレーするが、初心者は戦略を考える前に足の運びやストロークの基本を学ばないといけない、というのが筆者の立場です。
この批判については、実践者として僕もしっかり答えていかないといけません。大切なのは、ライティング・ワークショップという枠組みだけで子どもたちの書く力が伸びるわけではない、ということでしょう。こうした枠組みは、あくまで生徒の力を伸ばすための環境の設定に過ぎません。その中で、一人一人の力や課題を見つけて、そこで教師の知識を授ける。その知識を書く中で実際に使ってもらい、定着を図る。アトウェルの学校のようにそれがしっかりとできていれば、ただの「やる気を高めるごっこ遊び」には終わらないはず。
ライティング・ワークショップもリーディング・ワークショップも、究極的には「読み書きの力を伸ばすためのトレーニング環境」です。筆者は、学習には徹底した練習が欠かせない(原理4)ことも指摘していますが、文脈を欠いたただの練習は退屈なので、こういう真正に近い場で練習する、それがワークショップ型の授業の強みです。であればこそ、そこできちんとトレーニングする必要があるのですね。単に「自由にのびのび楽しく読み書きすれば自然に力がつく」わけではないということ、しっかり気を引き締めたいと思います。
認知心理学の成果をわかりやすく紹介
この本では、他にも「学習スタイル」神話への批判(下記エントリ参照)や、遺伝要因と環境要因のバランス、キャロル・ドゥエックのマインドセット論など、教育と認知心理学に関連する基本的なトピックが紹介されていて、こういった話題への導入としても大変有益かと思います。
[ad#ad_inside]