昨年から読みたいと思っていた『サピエンス全史』をやっと読み終わりました。とてもとても面白かった! ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・鉄』を思い出させるスケールの大きな歴史の本。文字通りサピエンスの歴史で、読んでて楽しいですな。
文字通り「サピエンスの全ての歴史」を概観する本
「認知革命」からはじまる上巻
この『サピエンス全史』は文字通り「人類の歴史」を概観する歴史の本。上巻はさまざまな種の人類の中から「認知革命」を成しとげたホモ・サピエンスが他の人類や動物たちを圧倒していく第一部「認知革命」、狩猟採集社会から農耕社会に移行することで、生活水準を落としつつも爆発的に人口を増やしていく第二部「農業革命」、そして多種多様な民族・文化を持っていた人間社会が、貨幣の流通や帝国的支配のあり方を通して次第にグローバル的規模で統一されていく第三部「人類の統一」からなる。
「科学革命」にいたる下巻
下巻は、第三部を引き継ぎつつ、宗教とイデオロギーをどちらも同一の視座で捉え、これらが人類の統一に果たした役割をさぐる。ついで、第四部ではいよいよ?近代の科学革命。科学の特性を「無知であること」を認めるがゆえの進歩だと捉えて、これが技術と結びつき、さらに帝国が科学を支援するにいたって、科学がヨーロッパの世界支配の原動力として機能したことを説明する。さらに、「進歩」の理念が浸透して将来の富の総量が増えることが信じられることで、資本主義の発展が急速に進んでいく。最後には、ついに生命自体を操作するようになったホモ・サピエンスが、ネアンデルタール人を蘇らせたり、超ホモ・サピエンスすら現実的に可能になるだろうこれからの話。果たして僕たちはどこに進みたいのか?という問いをなげかけて本書は終わる。
全体として、話題がヨーロッパ世界中心かなという印象はある。でも、十分に楽しめる「サピエンス」の全史だ。
どんな「虚構」が私達を幸福にするか?
虚構によって生きるホモ・サピエンス
このうち、個人的なこの本のハイライトは「虚構」をめぐる話だった。
まずは、上巻の認知革命だ。虚構を扱えるようになったホモ・サピエンスが、噂話など以前よりも大量の情報を扱えるようになり、集団での計画的な行動をたてられるようになったこと、宗教や神話や国民、人権など、現実には存在しないものを存在するように扱えるようになったことの影響の大きさを、この本はとてもわかりやすく教えてくれる。虚構を扱うことによってサピエンスが獲得したのは、多様な想像上の現実と、それが生み出す多様な行動パターン。それこそが人類の「歴史」を作っていくのだという。なるほど!
また、こうした「虚構」は、後の「キリスト教」「民主主義」「自由」などの想像上の秩序を生み、男女差に見られる社会的ヒエラルキーをも生んでいく。こうしてみると、僕たちの身の回りは虚構だらけで、良くも悪くも虚構によって安定した秩序を形成しているのだなあと実感させられる。
人類は本当に幸福になったのか?
下巻の後半では、科学革命と資本主義と国家によって、富の総量は格段に増え、暴力も減ったのだけど、にもかかわらず、私達は過去の人類に比べて幸福になったのだろうか?という話題が扱われる。
この問題、そんなに単純な話ではなさそうだ。例えば、(これは上巻の話題なのだけど)農業革命を果たした人類が以前より豊かな生活が遅れるようになったかというと、決してそんなことはない。むしろ狩猟社会よりも爆発的に人口が増えていくので、個人単位で見れば生活水準を維持していくのが大変だったそうなのだ。つまり、農業革命はたしかに「種」としては成功だったが、個人単位で幸福をもたらしたかというと怪しい。しかももう戻れない変化なのである。今だって、インターネットで簡単にメールが遅れるようになって全体として生産性は高まったけど、個人の生活はどんどん慌ただしく忙しくなっている。果たして人類は幸福になったのか?
こうした疑問に関連して、下巻の幸福をめぐる議論では、そもそも、幸福とは何か?という話が展開される。そして、ここでも「虚構」が関わってくるのだ。
筆者によると、幸福とは客観的な条件と主観的な期待の関数によって決まる。一定程度の富は幸福に必要な条件だけれども、それを越えると幸福感には寄与しない。
では、個人的な幸福感は何によって決まるのか?もし幸福が快感を覚えることに基づくなら、僕たちの社会はハックスリーの「すばらしい新世界」に至るしかない。
また、もし幸福が「人生を生きる意義」などの「主観的な妄想」(これも虚構と読んで良いと思う)に基づくなら、個人の物語をその時代の主要な虚構の形式に沿わせることで、人は自分の人生に意義を感じて幸福度が高まるかもしれない。
筆者はこれらのいずれの道も「気の滅入る結論」としてしりぞける。そして、これらの見方に共通する点が「幸福が主観的感情であるとする自由主義」(これもまた人類の発明した虚構の一つだ)だとして、仏教の考え方にその突破口を探していくのだ。
サピエンスの歴史は「虚構」の歴史
筆者のこの議論をざっと振り返るとき、僕たちが生きるのに際して、宗教、国家、自由主義、資本主義などの「虚構」の果たす役割が非常に大きいということに、あらためて思いいたる。こうした虚構に自覚的になることが、虚構の虚構性を自覚した上で適切につきあえるようにすることが、僕たちが幸福に生きる上では大事なのかもしれない。これは、千野帽子『人はなぜ物語を求めるのか』を読んで印象深かったことなのだけど、僕の中ではこの2つの本がはからずもリンクしてしまった。
そんなわけで、どちらもおすすめできる本です。ぜひご一読を!
[ad#ad_inside]

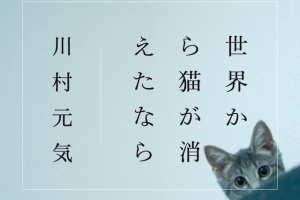





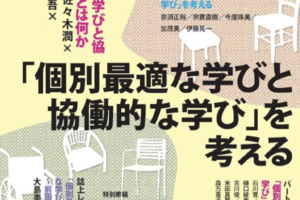

![[読書]冊数は少なめながらも、本屋大賞のあの本はやはり面白かった!2022年4月の読書の記録。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/05/reading-book-1500650_1280-50x50.jpg)
![募集締め切りました→[告知]先着6名。2/23(土)午後、広瀬友紀先生と「言語学と教育」について語る会。申し込みはコメント欄から。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/06/スクリーンショット-2017-06-06-7.21.57-50x50.png)
![[ITM]回想録を書く前に(1) モデルを見る、トピックを探す](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/511NgcY9IsL._SL160_-17-50x50.jpg)
面白そうな本ですね。図書館で探してみます。
同じ時代でも地域によってはまったく違った段階であったと思うので、そのあたりはどこのサピエンスなのかなと思ったり、南北問題などを考えると「もうひとつのサピエンス史」なんかもありそうですが、大きく俯瞰して「ひとつの物語」が語られていそうで興味がわきます。
人類が虚構を生んで世界が広がったのはわかる気がします。言語における「仮定法」なんかも大変人間くさいし、動物世界を飛び出るような大きな飛躍があったと思います。
また、個人的には、人間は幸福にはなろうとしても妄想が先行して、とても「それ」になれそうもない種であるかも。そこで、たぶん幸福になろうとするよりも、不幸にならないようにすることがより有効なように思います。それで仏教的な考え方になるのかな?