世の中には「身体感覚」を総動員する仕事がある。たとえばスポーツ・職人・芸術などの分野がそれだ。そういう分野での熟達過程は、しばしば「言葉にはできない」「言葉にすると嘘になってしまう」「身体で覚えるしかない」と言語化が拒絶されてしまう。では、そのような「感覚を通して学ぶ」分野の熟達過程では、言葉はどのように関わっているのだろう? 生田久美子・北村勝朗(編著)『わざ言語 感覚の共有を通しての「学び」へ』は、その問いを探究するとても面白い本だ。保育士や教員養成の分野にも参考になる一冊だと思うので、界隈の人におすすめです。
[ad#ad_inside]様々な職業の「教える-学ぶ」関係における言葉の役割
この分野、僕はもともと諏訪正樹さんの本を読んで興味を持った。身体感覚の熟達の上でも、自分の身体感覚を言葉によってメタ認知することで上達するという視点は、「身体」と「言語」をつい対極のものとして捉えがちな自分にとって、教わるところが多かった。
諏訪さんの本と比べての本書の特徴は、2つ。第一に、スピードスケート、宮大工、陸上競技、歌舞伎、創作和太鼓、看護師、助産師など、様々な「身体感覚が重要な仕事」が登場し、その道のプロフェッショナルが熟達し「わざ」を身につける過程で、言葉が果たす役割を、理論と該当者へのインタビューをもとに考察していること。有名どころでは、北京オリンピックで活躍した陸上競技の朝原宣治さん、清水宏保選手や小平奈緒選手などのメダリストを育てたスピースケート・コーチの結城匡啓さんなどがいる。第二に、選手とコーチ、師匠と弟子、先輩看護師と新人看護師のように、「教えるもの」と「教わるもの」の関係にフォーカスされていることだ。ある分野の熟達者と彼に学ぶ学習者が、どのように感覚を共有していくか。そこに言葉がどのような役割を果たしているか。そこが本書の中心となる問いである。それは、それぞれの分野の人によってかなり違っている。
「文字知」の陥穽をどう乗り越えるか?
中でも読んでいて興味深かったのは、感覚の共有が大事な分野における、文字による知識伝達の限界に、どう向き合うかという問題だ。こういう分野では、伝統的に「わざ」の伝承は文字にできないという信念も根強い。それはなぜなのか。
宮大工の場合
宮大工・西岡常一さんとその内弟子・小川三夫さんは、文字にして技術を伝達することを否定する。文字による知識伝達は、目の前の現実をその文字に合わせて見てしまう(文字知識の確認作業にさせてしまう)弊害があり、それでは丸暗記で思考しない人を育てるからである。その代わりに、ただお手本だけを見せて、「師匠の思考」を考えさせようとする。そして、「先人の思考を遡及的に読み取る「見る目」の体得」(p107)をさせるのだ。
しかし、言葉を全く使わないのではない。興味深いことに、西岡自身は相当な読書家であり、何冊もの書物を聞き書きという形で記した。また、小川は、ある程度熟達し、言葉を手放す(経験と知識が対立した時に知識を手放せる)ことができるようになった弟子に対しては、「飛鳥の線」「平安の線」など、教科書的な知識を勉強することを認めた。自分の感覚による学習が先にあり、それを言葉で名付けることはあと。小川によると、この「経験と知識の順序性」こそが大事なのだ。
歌舞伎・創作和太鼓の場合
歌舞伎役者の五代目中村時蔵さんは、伝統的に歌舞伎の世界では「書く」ことがなされなかったことを踏まえた上で、それが「書かなくても覚えられる歌舞伎漬けの環境」の恩恵だったことを認め、時代の変わった今に生きるご自身は「書いて伝える」選択をしている。しかし、「書いて伝える」が有効なのは「形」を教える場面に限ってのことで、感覚が密接に関連する「演じる」段階になると文字で伝えない。これは結局伝えられるものではなく、「役に入り込む」感覚を自分で掴むしかないのだという。そして、文字で伝達できないことが、役者や時代による変化の可能性も生んでいるのだそうだ。
これと似たことを創作和太鼓の佐藤三昭さんも述べている。「標準的な正確さ」を学ぶ段階ではマニュアル化が有効だし、「へそを真下に落とすように打て」のように、ある行為が発現することを狙って語りかける。しかし、やがて基礎的な技術を身につけて演奏表現を磨く段階に進むと、マニュアル化ができないのだという。語りかける言葉も「太鼓で歌う」「太鼓打ちから太鼓弾きへ」などと、より感覚的になっていくらしい。
歌舞伎と和太鼓、どちらも「基礎的な技術を学ぶ段階では文字によるマニュアル的な指導が可能だが、それ以上の段階になると、演者が自分の感覚を追求していくしかなく、その段階では言語にできることは限られている」という点では共通している。
スピードスケートの場合
僕が一番興味を持ったのは、清水宏保選手や小平奈緒選手を育てたスピースケート・コーチの結城匡啓さんである。彼の場合、まず言葉から入るのが特徴的だ。徹底して自身の理論を学習者に教えて、学習者にも「技術カルテ」を書いて文字化してもらう。自分の感覚を、自分の中で再現性を確保できるように書けること。それが、結城さんがコーチとして選手に求めていることなのだ。そして、選手自身が自覚する感覚と、コーチから見えるその選手の感覚をすり合わせて、高みを目指していくのである。
結城コーチは、この本に登場する他のプロフェッショナルと比べても、言語を非常に重視している。というのも、スポーツでもある技に熟練すればするとは言語を介さずに無意識にできるようになると思われがちなのに、結城コーチはそれを明確に否定し、「無意識にさせない」術としての言語の利用を重視しているからだ。
結城コーチ曰く、コーチの仕事とは「選手の中に生じる自動化との戦い」(p320)である。選手はある技に熟練するに連れて、それを無意識に、自動的にできるようになってしまう。しかし、トレーニングによる筋力の変化や体調の変化は必ずあるから、技は必ず狂う。ここで、もし無意識なままだと、狂った時に調整できない。だからこそ、「技術カルテ」を用いて、言語の形で自分の感覚を残しておくのである。こういう言語の積極的利用は、他のプロフェッショナルには見られないものだった。
しかし結城コーチも言語万能論ではない。オリンピックのメダリストのように熟達のレベルが高くなればなるほど、その感覚は一般の人とは共有できなくなる。例えば、メディアから「どんな感覚でしたか」と聞かれて答えようとしても、それは自分の本当の感覚ではなく、かえって自分の感覚の狂いにつながってしまうというのだ。だから、結城コーチは、清水選手や小平選手には「(メディア向けに)自分の感覚を言葉にしようとするな」とも伝えていたのだそうだ。ここは非常に面白かった。
こんな風に、本書では、様々な分野のプロフェッショナルが言語や文字とどう付き合ってきたかが、インタビューとその分析を通して語られている。共通しているのは、どの人も言語(特に文字)による伝達の限界を自覚しつつ、感覚を共有するために言語を使っていること。言語化しにくい分野の熟達過程で言語がどのように機能しているのか、非常に興味深い。
教師教育の観点でも面白そう….!!
さて、本書が僕にとってさらに興味深いのは、この話が教師の熟達についてもヒントをくれそうだからだ。教育の仕事は、本書に登場する職業では看護師が一番近いが、人間という生き物を相手にする対人援助職なだけに、マニュアル化できない暗黙知が多い。立派な「感覚を通して熟達する仕事」なのだ。したがって、教育の分野では、名人教師の暗黙知がいくら本(文字)にしても伝わりにくく、その暗黙知の断片がしばしば「箴言」的に残されたりする。これはもう立派な「わざ言語」である。「わざ言語」という観点で教師の熟達を見ると、どんなことが見えてくるだろう。ぜひ本書の研究者の方々に研究してほしい…!!
必要なのは「わざ言語」に「誘われる」姿勢
最後に、本書で扱われる「わざ言語」には、まとめると大きく3つの機能がある。第一には、例えば、スケートの刃を斜めに接地する感覚を「貼りつけ」という比喩で表すような、熟達者が持つ具体的技術・スキルを学習者に「伝達する」言葉である。しかしそれだけでなく、「お客さんが見えなくなる」(歌舞伎)、「太鼓がメロディを弾き始める」(和太鼓)のような、熟達者が到達したある感覚・状態を学習者に「共有する」言葉でもあり、熟達者が持つ感覚を学習者自らが探っていくように「誘う」言葉でもある。
このうち、僕が一番興味を持ったのは「誘う」言葉としてのわざ言語だ。というのも、先述の通り、身の回りでも、そういう「誘う」わざ言語はたくさんあると思うから。
例えば、風越で保育の女性ベテランスタッフに僕が「何を見ているんですか」と聞いた時、彼女は「子供同士の関係性の育ちを見る」と言った。では、何を見たら「関係性の育ちを見る」ことになるのだろう。きっと、個々の要素をあげて合計しても「関係性の育ちを見る」ことにはならない。あれはきっと「関係性の育ちを見るとはどういうことか」という自問自答に誘うための「わざ言語」なのだろうと思う。
また、国語スタッフのりんちゃん(甲斐利恵子先生)が風越の生徒について「まだ子供が心を開く構えになっていない」と言ったことがあった。あの「心を開く構え」というのも「わざ言語」の一種だろう。色々な分野の一流と呼ばれる人は、おそらく無意識に「わざ言語」を発している。だとしたら、学習者が熟達者になる上で必要なのは、それらの「わざ言語」を発見し、そこに能動的に意味を読み込む能力のはずだ。
佐伯胖は本書の「人が「わざキン」に感染するとき」で、
「わざ言語」を「わざ言語」として受け止めることも、一種の「わざ」なのかもしれない。(P204)
と書いていたが、僕たち学習者に必要なのは「周囲の熟達者の発する言葉を「わざ言語」として受け止める姿勢」である。おそらく、優れた学習者は皆その姿勢を持って学んでいるのだから。
そして、ここにおいて、学習者はただの受動的な「熟達者から伝達される人」ではなく、熟達者の振る舞いを解釈する「解釈者」であり、熟達者の言語や振る舞いの意味を「作り出す人」ともなる。「熟達者-学習者」のそのような双方向的な関係性が、ベテラン教師と熟達過程にある教師の間の理想的な関係なのかもしれない。
というわけで、教師の熟達についてはもちろん、身体や感覚を使った学びと言語の関係について考える上で、とても示唆の多い本書。ちょっと値段は高めだけれど、おすすめです!
[ad#ad_inside]

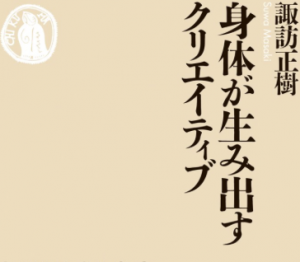









![[読書]祝・ちくまQブックス創刊! 岩波ジュニスタとともに「中学生以上の新・王道」になるか?](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/09/IMG_6134-scaled-50x50.jpg)

