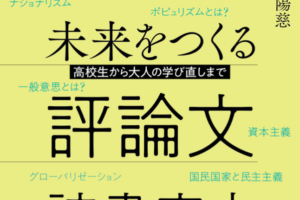岩下修『イラスト図解:AさせたいならBと言え』を読んだ。1988年刊の同著者による『AさせたいならBと言え』にイラスト図解を加えて具体例を大幅に書き換えた令和版とのことである。1988年版については、SNSで何度かその名前を目にしたことがある。今回、たまたま書店でイラスト図解版を目にして、ちょっと気になったので読んだのだが、定評に違わぬ素晴らしい著作だった。すでにご存知の方も多い本だが、自分の教員としての力量形成のことも含めて色々と考えるところがあったので、それも含めてブログにも書き記しておく。なお、僕は88年版は現時点で未読であり、二つの版の比較などは一切できない。
[ad#ad_inside]白眉は前半の「解説編」
読む前、この『AさせたいならBと言え』というタイトルから、「こういうケースではこう言う」事例集を想像していたのだが、それは良い方向に裏切られた。本書は「AさせたいならBと言う」行為がどういうものなのかを前半の解説編で書いていて、僕に取っては、断然その部分が面白かった。
「Aさせたい」時に、なぜAそのものを言わず、Bという別の表現を使うのか。それは、そのBという表現によって、「子どもが知的に動き出す」ことを期待するからである。静かにしてほしい時に「静かにしてください」ではなく、別のどんな表現を使うと、子どもたちが自分で頭を働かせて静かにしようとするか。それを考えるのが、「AさせたいならBと言え」の原則である。本書では、この原則を「解説編」で説明し、子どもに届く言葉の原則として、「物・人・場所・数・音・色」といった「ゆれのないモノ」を提示することが提案されている。その後には、さまざまなケースにおける具体例が書かれた「活用編」に続く。
話し言葉にも修辞意識を持つ
本書の中でも印象的だったのが、筆者がAとBの言葉の関係を、背景となる<地>と、そこから浮かび上がる<図>の関係に置き換えて説明していることだ(p68)。つまり、Aという表現は、子どもにとってありきたりだったり、よくわからなかったりして、明確な像を結ばず、意識の背景に追いやられてしまう。でも、子どもに清新な印象を与える別の表現Bを考えつくことができれば、それは<地>とは一線を画して浮かび上がる<図>となり、その言葉の力で子どもは知的に動き出すのである。
これは、詩の言葉と同じだなあと思った。手垢にまみれた表現では、人の心は動かない。だから、詩人はそれを<図>として浮かび上がらせるような別の表現を模索し、その表現が人の心を動かす。その構図と全く同じなのだ。だから筆者は「AさせたいならBと言え」の本質を「話し言葉にも修辞意識をもとうという主張」(p36)であると述べている。言われてみると、本当にシンプルなことである。
従って、この本には「より良い表現を導くための原則」はあるけれど、「正解」がない。Aさせたい時にBという表現を使って上手くいったところで、次にはそのBという表現が手垢にまみれて背景の<地>になってしまうからである。だから、本書を読んで、「なるほど、静かにさせたいときは「静かという音があるのです」と言えばいいのだな」とそれを何度も実行する人は、本書を読んだとはとうてい言えないだろう(もちろん、最初の一歩としてはそれでいい。特に若い先生は)。自分や子どもたちが作り出す教室という文脈の中で、常に最善の表現となるレトリックを考え、更新し続けなさい、という本なのだから。
自分のこれまでと、今の課題意識
ここからは長い自分語りになってしまうけれど、この本が僕にとって「響く」本だったのは、まさに今の自分の課題と重なるからである。それは、元々中高国語科教員、しかもどちらかというと高校向きである自分が、小学5・6年生を一斉に相手にするときに、彼らに通じる言葉をあまり持ち合わせていない、という課題だ。
僕は元々、教員としてはかなり凸凹のある人間だ。それは生まれつきもあるし、教員としても生徒としてもお世話になった母校・筑波大学附属駒場中高のやや特殊な環境の影響もあった。とにかく生徒の知的レベルが高く、また、「面白くないと思った授業はサボる」点で素直な子たちなので、彼らに「面白い」と思わせる教材や機会に出会わせられるかどうかが授業の成否のかなりを占めた。だからとにかく教材研究(素材研究)が命だったし、僕も先輩教員の遠い背中を見ながら自分なりに頑張って予習をした。新しい教材に取り組むときは、大学図書館で学術論文や教育実践論文を集めて読んでから授業を考えるのが日常で、それにはだいぶ鍛えられた。
もう一つ、僕は母校に勤務する卒業生教員でもあった。卒業生である以上、生徒の気質や学力との共通点も結構あるし、使う語彙にもあまり差がない。僕が面白いと思ったことをぶつけると、彼らも面白いと思ってくれる可能性も高い。「どう話したら指示が通じるのか、この面白さが通じるのか」ということを、今思うと、あまり考える必要がなかったのである。
こういう環境の中で、僕は指導技術や言葉がけの工夫をあまり考えずに「コンテンツの勉強」に注力できる幸運に、長いこと浸かっていた。僕自身、教えることよりも学ぶことの方が好きなので、授業をすること自体よりも、この予習の段階が一番楽しい人間でもあった。そして、「教師はとにかく素材研究」という僕の考えが形成・強化され、それは同時に「指導技術」や「生徒指導」的なものの軽視につながっていった。
言うまでもないことだが、こういう環境だからこそ自分を伸ばしてくれた部分も当然大きく、母校には今も感謝しかない。しかし、その素晴らしい環境に甘えて、自分で見えていなかった現実もまた多かった。例えば公立の先生たちが、幅広い学力層の子たちを相手にする中で、また異動を繰り返す中で身につけてきたもののかなりの部分を、僕は身につけずにこの年齢になってしまったのだと思う。
僕が「身につけてこなかったもの」の一つが、「色々な年齢や学力レベルの子に届く話し方」である。抽象的な語彙がなく、集中するのも難しい小学生たちに話を聞いてもらう。それは決して、「論理的に、わかりやすく話す」のではない。論理的に話されること自体がむしろ苦痛な子たちも結構いる中で、どうすると子どもに話を聞いてもらえるのか。そういう悩みが、今回、書店でこの『イラスト図解:AさせたいならBと言え』を手に取った背景にあった。
これは詩を書くことと一緒
今、この本を読んで、大事なのはつまり「話し言葉に修辞意識を持つ」ことなのだとシンプルに言われると、なんで自分はそういう捉え方をしてこなかったのだろう、と思う。書き言葉については、「悲しい気持ちを表現したいときに、ただ悲しい悲しいと書いても読み手は悲しくならないよ。どう書くとその感情を読み手に体験してもらえる?」などと子どもたちに話すのに、それが日常の教室で、自分では実践できていなかったということなのだから。
そして、こちらの指示を聞いてくれない子どもたちに対して「どうして聞いてくれなんだろう」と思い悩むよりも、「これは詩の創作と一緒なんだ」と考えて、「どういう表現なら心を動かせるのか」という意識で模索する方が、はるかに前向きになれる作業である。すぐにはうまくいかないかもしれないけど、楽しくやっていけそうだ。こういう視点をこの本からもらえたのは、僕にとってとてもありがたかった。
「小学校の国語の専門家」から学べることが多そう
今回、幸運だったのは、この岩下さんが小学校でも国語の専門としてやってこられた方だったことだ。例えば岩下さんの「子どもが知的に動き出す」という表現がただの「子どもを動かす」というそっけない表現だったら、あるいは、多くの国語教師が慣れ親しんできた佐藤信夫の『レトリック認識』が本書で引用されていなかったら。いずれの場合も、本書の主張の僕に取っての説得力は、大幅に減っていただろう。それは、僕もまた国語科教員であり、岩下さんが説得のために使うレトリックが、あるいはレトリックを通して読者を説得しようとする姿勢そのものが、僕に親和的で、受け入れやすいものだからである。
僕はやはり気質的にも能力的にも、良い小学校の先生には程遠くて(子どもより教材が好きだし、自分の専門教科の範囲外では、自分の熱量が下がってしまう)、今さらオールラウンダー的な「優れた小学校の先生」になれるはずがない。そういう僕が、それでも風越学園で小学56年生を相手にする力量を形成する上で、いちばん耳を傾け、学びやすいのは、この岩下さんや、他には例えば土居正博さんや白坂洋一さんといった、「小学校で国語を専門としている人たち」なのだと思う。「小学校の国語の専門家」たちの著作や言葉には、今回の岩下さんの本と同様に、僕に響くレトリックや、僕がやってみたいと思える実践がある可能性が高い。それらから学ぶことで、自分の強みやこれまでの経験を活かした、ややいびつではあっても自分なりの「小学校の先生」像を作っていくしかないのだろう。そう考えさせられ点でも、とてもありがたい一冊だった。
[ad#ad_inside]