岡田暁生さんの本は以前に「西洋音楽史 クラシックの黄昏」を「勉強になるなあ」と読んだことがあって、それ以来の読書。音楽の本なのだけど、読書や国語の授業にも通じるところがたくさんあって、面白い本だった。ここでも、そういう観点でひっかかったところをメモしていくので、そのつもりでお読みいただきたい。
[ad#ad_inside]人は音楽を自由には聴けない
筆者が早々に宣言しているのは、人は音楽それ自体を聴いているわけではない、ということだ。
音楽は決してそれ自体で存在しているわけではなく、常に特定の歴史/社会から生み出され、そして特定の歴史/社会の中で聴かれる。どんなに自由に音楽を聴いているつもりでも、私たちは必ず何らかの文化文脈によって規定された聴き方をしている。(p.xi)
そして、そうした「歴史/社会の文脈は、一般にそう思われているほど個人的なものではなく、むしろ集団的なものである、とも言う。
生理的かつ個人的な相性や嗜好と見えるものの多くは、実はその人の履歴であり、しかも集団的に規定されている。そして集団が違えば、価値体系は全く異なってくる。(p.19)
つまり、僕たちは、自分で思っているほど「自分の好みで」「自由に」聴いているわけではない、ということだ。
この前提にもとづいて、筆者は「音楽の聴き方」を学ぶことの意義について、次のように説明する。
「ある音楽が分からない」というケースの大半は、対象となる音楽とこちら側の「聴く枠」との食い違いに起因しているように思う。私たちは皆、特定の歴史/社会の中で生きている以上、音楽の聴き方もまた、それらからバイアスをかけられるのはいかんともしがたい。自由に音楽を聴くなど、誰にもできない。ただし、自分自身の聴き方の偏差について幾分自覚的になることによって、もっと楽しく音楽とつきあうことが出来るのではないか――これが本書における最も私が言いたいことである。(p.xi)
これ、「読書」でも同じだろう。自分の好みも、何らかの時代や集団の枠の中で形成されたものだから、それを絶対視するのはよくない。自分の好みを持ちつつも、自分の好みとは別の評価軸をきちんと認めて、自分の好みを客観的に捉えられるようになること。自分でもそうありたいし、生徒にもそうなってほしいなあ。
音楽についての言葉を持つことの大切さ
そうなるための方法として、筆者は「音楽についての言葉」に注目する。「音楽の良さは言葉にできない」という言説がよくあるが、筆者はそのような「思い込み」がどのように生まれてきたのかを押さえつつ、音楽文化ではもともと「すること」と「語ること」がセットであった/あることを指摘していくのだ。
そうして、筆者が薦めるのは、音楽文化についての「語り」を学ぶことで、自分にとって未知の「音」を意味のある「音楽」として受容すること、それによって、当初は異文化であった「わけのわからない音楽」に徐々に接近していく鑑賞法である。
この話も、文学作品の鑑賞と似ている。これまでの自分をとりまく文脈によって形成された「好み」は、文学作品にはある。その「好み」と遠い文脈の中で形成された文学作品(たとえば、中高生にとってそれは伝統的な日本文学だったりする)の良さは、すぐにはわからない。文学についてのさまざまな「語り口」を学ぶことによって、「そういう観点で見ると、この作品にもこういう良さがあるのか」とわかっていくものだ。そのためには、まず「語り手」「視点」「時間」などの注目点を知ったり、日本語の特徴について知ったり、その作品をとりまく文脈を知ったりしないといけない。それは、一人でやるのはなかなか難しいことだろうから、そこに授業をすることの意味があるのだと思う。
たとえば、高校1年生の定番教材、芥川龍之介「羅生門」。この小説、読者がのめりこんで感情移入するタイプの小説ではないので、初読では「一体これのどこがいいの?」と疑問に思う生徒は少なくない。でも、「語り手」という概念を身につけてこの小説を読むと、「作者」と自称する語り手が、時には過去の歴史を解説するように、時にはその場で実況中継するようにと、自在に語りの視点を移動させながら、下人と距離をとって批評的に語っていることがわかる。どちらかというと、読者が下人に感情移入しにくい語り方になっている。「語り手」や「視点」という概念を導入することで、こういう発見があり、「羅生門」が好きではない生徒も「なぜ自分はこの小説があまり好きではないのか」を語る言葉が生まれる。
演奏者/聴衆/批評家の分裂
もう一つ、この本で面白いなあと思ったのは、近代に入って、それまで不可分だった「演奏者」「聴衆」「批評家」が分裂してしまったという話。筆者はこのことには批判的なスタンスをとっていて、アマチュアが自分で音楽を「する」ことの価値を力説している。これが、ライティング・ワークショップととても似ていて、そうそう!と思ってしまった。
結局のところ人は、自分でしたことがないものについては、よく分からない。本書では「音楽の聴き方」とは「音楽の語り方」を知ることにほかならないと述べてきたが、おそらく自分で音楽を「して」みれば、いくらでも語ることは出てくるはずである。もちろん私が考えているのは、例えばカラオケにおいてしばしば起こるような、「やりっぱなし」の
する」ではない。少々古めかしい表現になるが、それは習い事の復権とでも言うべきものだ。ある音楽文化のさまざまな約束事を、身をもって知るためのイニシエーションとしての、「学び」である。(p202)
この「よりよく味わうためにこそ自分でもそれをしてみる」というのは、僕の思うライティング・ワークショップの考え方ととても近い所がある。ライティング・ワークショップも、別にプロの書き手を育てたいわけではない(そんなことができるなら、僕はとっくにこの仕事をやめて自分がプロを目指してます)。実際に書くという作業を通じて、日本語の様々なジャンルの文章の特徴について理解し、考え、書くことについて考えてほしいのである。ライティング・ワークショップを通じて「書き手の眼」を獲得して、目の前の本を読み直し、自分がこれまで読んでいた作家の色々なテクニックに気づいてほしいのだ。
いくら「人は読みたいように読む」とはいえ、今回はちょっと我田引水的な読み方だったかなあ。ちょっと反省もするのだけど、岡田暁生「音楽の聴き方」、面白い本でした。国語の先生に限らず、どうぞ。

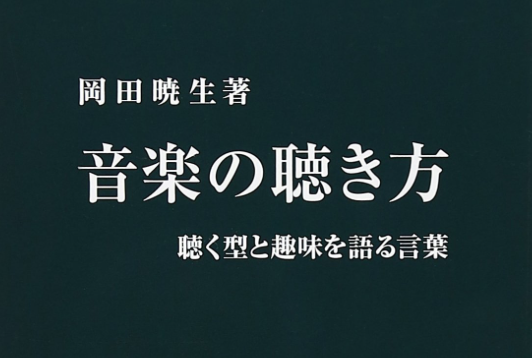









![[お知らせ]ひつじ書房ウェブマガジンに寄稿しました。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/05/IMG_4840-scaled-50x50.jpg)
![[読書]「教師の成長」に関わる人におすすめ!渡辺貴裕『小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ授業づくりの考え方』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2025/11/b5e8b178146dc4a484b286b7de03f5ad-50x50.png)