勤務校の行事で余力がなく、更新が滞ってました。今日は代休でようやく一息。来週からまたリーディング・ワークショップの授業がはじまるので、アトウェルのIn the Middleをふたたび読み直しつつ、自分の授業について考えないとな、というところ。というわけで、自分が考えるためのエントリを書きます。僕のリーディング・ワークショップの課題の一つである「ミニ・レッスン」について書いてみたい。「そもそもミニ・レッスンとは何を教えるべき場なのか?」について、ナンシー・アトウェルの本を参照しつつ考えよう。
[ad#ad_inside]
最初の10分をどう使うのか?
リーディング・ワークショップでは、生徒の個別の読書に多くの時間を使う。数少ない「一斉授業」の場面がミニ・レッスンだ。時間はたった10分。その10分をどのように使うか、ということになる。
今年の僕のリーディング・ワークショップでは、こんな感じだ。まず、最初の5分くらいで、原則として「僕がいま読んでいる本」のブックトークをする。「いま読んでいる本」なので、必ずしも「お薦めの本」ではない。ここの時間の主眼は、「教師の僕も常に本を読んでいること」を示すことにある。モデリングです。ついでに、「名作と評判なんだけど、どうも入りこめない」みたいなあるある話もできるのが良いところ。
ブックトークのあとは、5分、プリントを配ってその日のトピックについて話をする。以下がその一覧。前半の5回は一学期、後半の5回は二学期のものだ。
- 目標をたてる/読者の権利10か条
- 点検読書
- 読むスピードを制御する
- 飛ばし読みのレッスン
- 記録をつける
- 選書のヒント
- 小説を読むことの価値
- リーディング・ワークショップでやっていること
- 関連づける
- 時間をつくる
今見直してみると、トピックの内容は、読みの方略についての話(2、3、4、6、9)、読書家としての読書習慣や態度についての話(1、5、10)、価値のインストラクション(6、7)に大別されている。一応、下記リンク先で紹介した本には目を通しているのだけど、教えることを事前に決めるというより、カンファランスの様子や記録用紙を見てミニ・レッスンでとりあげたいことを決めている。系統性のあるプランを事前にかっちり組むよりは良いかと思っているのだけど、はたしてこれで良いのだろうか…?
アトウェルのミニ・レッスンは文学とブックトーク重視
ここで考える材料として、アトウェルのミニ・レッスンを見よう。ナンシー・アトウェルのIn the Middle第3版の第五章によると、彼女のリーディング・ワークショップでは、「ワークショップの手順に関するミニ・レッスン」「実際に読むことについてのミニ・レッスン」「文学についてのミニ・レッスン」の3種類に大別されるようだ。そして、毎週4回のリーディング・ワークショップの授業が年間を通じてあるだけに、そもそもミニ・レッスンの回数も多い。
ワークショップの手順に関するミニ・レッスン
一年の最初の2週間に多くを占めるのが、ワークショップの手順に関するミニ・レッスン。これは教室内の説明、授業の進め方やその価値の説明をするものだ。これを最初に徹底することで、ワークショップにうまく乗れない生徒や助けが必要な生徒に注力できるのだという。
手順に関するミニ・レッスンの例
- リーディング・ワークショップで生徒たちに期待していること
- リーディング・ワークショップのルール
- 教室の図書コーナーに本がどのように配架されているか
- ジャンルの決め方、見わけ方
- 各自の図書カードを使っての本の借り方と返却の仕方
- 毎日の宿題について。
実際に読むことについてのミニ・レッスン
続いては、期待される読書家しての姿勢や読書習慣についてのミニ・レッスン。こういう「読書の方法」そのものを扱ったレッスンは、日本の国語教育にはすっぽり抜けているものが多い。
実際に読むことについてのミニ・レッスンの例
- 選書方法と、自分なりの選書の基準をつくること
- 合わない本をやめる自分なりの基準をつくる方法
- 優れた読み手ならではのいい読書計画について
- 「読みたい本リスト」をつくる理由とその方法
- ダニエル・ペナックの「読者の権利10箇条」
- 優れた読み手がなぜお気に入りの本を読み返すのか
ここでは、他にも読みの理論を紹介したり、文章の種類に応じて読み方を変えることも教える。アトウェルの授業の中では、後述する「方略を教える」のにもっとも近いのがこの部分だ。
文学に関するミニ・レッスン
でも、アトウェルのリーディング・ワークショップで一番大切なのはこれではない。ミニ・レッスンの大半が文学についてのものだという(p181)。ここでは、日本の学校であれば国語の文学の単元で一斉授業を通じて教えるような事項が並ぶ。アトウェルは特に詩を重視しているので(下記エントリ参照)、詩についてのミニ・レッスンが圧倒的に多い。
文学についてのミニ・レッスンの例
- 詩の読みときかた
- 詩の用語
- 暗喩、直喩、擬人化など比喩表現の種類
- 詩の形式
- 主だった詩人たちの人生、文体、技巧、題材、テーマ、そして詩
- 文学用語
なお、「文学に関するミニ・レッスン」には教師と生徒によるブックトークも入っている。Reading Zone初版では、Booktalkingという章が設けられているし、「読書に没頭するのに一番必要」と生徒が思っているのもブックトークとミニ・レッスン。アトウェルのリーディング・ワークショップでは、ブックトークはかなり大事なのである。
読みの方略を教えるミニ・レッスン
一方で、以前に下記エントリで触れたとおり、読みの研究者たちが推奨するのは、ミニ・レッスンで「読みの方略」を教えることだ。
こちらのスタンスでは、教師の仕事は読みの方略を教えて、それを生徒が個々の本を読む際にきちんと使えているかをカンファランスで看取ってフィードバックすることになる。
読みの方略を教えることに批判的なアトウェル
アトウェルは、少なくとも文学作品を読む時には、このような方略を教えることに批判的だ。ここは考えるべきポイントなので、ちょっと長くなるが、Reading Zone初版50ページ以降から、その経緯を書こう。
1990年代、ピアソンらの研究によって「優れた読み手が用いる方法」が整理された時、アトウェルはまずこれに飛びつく。当時、リーディング・ワークショップにおける教師の役割に苦しんでいたアトウェルは、これらの読みの方略を教えることが自分の仕事だと思ったのだ。彼女は、読みの方略についての本を読み漁り、これを教える。そして、生徒にも読む時に教えられた方略を使うことを求める。ところが、生徒は3週間この授業に付き合ったあとで、クラス会議を要求した。メタ認知活動も、付箋を使った読みも、生徒たちにとっては邪魔だったのだ。どの生徒もこの授業が良いとは言わず、結局、授業は元のスタイルに戻った。
こうしたエピソードを引用したあとで、アトウェルは、ローゼンブラッドの文学理論を引用しながら言う(p54)。読みには、情報を引き出す(efferentな)読みのモードと、詩や文学を味わう(aesthiticな)読みのモードがある。そして、少なくとも後者の読みでは、読んでいる世界を「生きる」ことが重要なのだ、と。ところが、「理解の方略」を教えると、テクストの種類に関係なく、生徒に常に「情報を引き出す」モードでの読みを求めることになる。これが、若い読者のストーリー体験をおびやかし、かえって生徒の理解を傷つけることを、彼女は批判するのである。
もっとも、彼女は理解の方略を全て否定しているわけではなく、自然科学や歴史のテクストを読む時には一定の有効性を認めている(p63)。しかし、彼女の関心の中心は、あくまで文学作品。そこでは、理解のための方略を教えることは有害なのである。
ミニ・レッスンの方向性をどうするか
以上のように、同じミニ・レッスンとはいっても、方向性の違いがある。ぼくの場合、モデリングという意味でも自分のブックトークは続けていこうと思うのだが、残りのミニレッスンのプランが問題。まずは、読みの方略を教えることを中心にするのか、それとも文学についてのトピックを盛り込んでいくのか。とりわけ、文学学作品の読みにおいて「方略を教える」ことをどう扱うのか、という問題は大きい。僕はこれまで「どっちつかず」の態度を意識的にとってきた面もあるのだけど、アトウェルと違って授業回数も少ないし、もう少し方向性を明確に定めた方が良いのかなあという気もしている。
僕はどうしてもアトウェルのほうに共感的だ。僕自身、「読み方」を教わらなくてもたくさん読むことで自然と読み方を学んできた経験があるからだろう。特に小説の読みについては、方略を使おうとすると常にテキストに対してメタな意識を持たないといけないので、小説の世界に入り込めない。実際の読者で、小説を読みながら表現の効果や語り手の語り口について意識しながら読む読者なんてどれほどいるだろうか?という思いがある。一方で、やや難解な評論文を読む時など、こうした読みの方略が有効な場面も目にしてきた。テクストのジャンルによっては、有効なのかなとも思う。
とすると、ジャンルによってすっぱりとスタンスを区別するのが良いのだろうか。例えば、論説文系を読む時にはミニ・レッスンで方略を教え、小説を読む時には、読書家の態度や文学について語る、というように。もしそうだとしたら、例えば一学期は小説限定、二学期は説明・論説文限定というふうに、ジャンルを縛ってしまうことになりそうだ。今年はもう難しいけれど、来年は、ライティング・ワークショップのジャンル・スタディよろしく、ジャンルを指定したリーディング・ワークショップを考えても良いのかもしれない。
[ad#ad_inside]




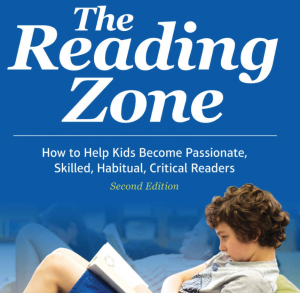
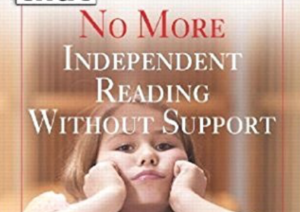
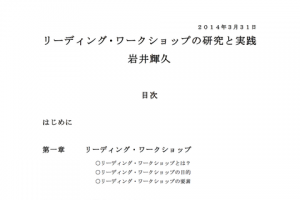



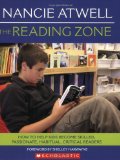



![[読書]オンライントークイベントに参加してきました。石井英真・編『流行に踊る日本の教育』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/02/f67a992cb759a5f85fe7ee8cf7c25157-50x50.png)
![[ITM]ブッククラブではなくラウンドテーブル](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/511NgcY9IsL._SL160_-11-50x50.jpg)
![[読書] 居場所をつくる人と、居場所に集う人。成田康子「高校図書館デイズ」「高校図書館」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/07/スクリーンショット-2017-07-02-21.47.51-50x50.png)