2023年最後の更新は、毎月恒例の読書まとめエントリ。これを年越すのはなんだか気持ちが落ち着かないので、頑張って今夜中に仕上げちゃおう。なんといっても今月は、良い出会いが目白押しの収穫の多い月だった。こういう月は、エントリを書くのもなんとなくわくわくするね。
[ad#ad_inside]全ての本好き、古本屋好きにささぐ、小説のような本当の話
そんな今月のベストは、ユン・ソングン『古本屋は奇談蒐集家』。これはいいですよお。本好きの人、古本屋好きの人は、絶対に好きだと思う。韓国に、ちょっと変な古本屋がある。古書を探す仕事を請けおうときに、代金をとるかわりに、依頼主がその本を探す事情を聞く古本屋だ。依頼しないと見つからないような希少な本を探している人には、それぞれに事情がある。昔の恋の思い出にまつわる本、どうしても後悔がつきまとう本、約束を忘れたままにしてしまった本…。そんな、本にまつわるさまざまな思い出を聞いた書店主は、手をつくしてその古本を探しにいく。さて、その本は見つかるのか?
ここまで読むと、きっとこれはよくできた小説だろうと思う。でも、古本屋は韓国に実在する書店で、ここに出てくるエピソードも全て実話なのだそうだ。途中でちょっと単調になるところがないではないけれど、店主のあたたかな人柄と、人生のちょっとした秘密にふれるエピソードの数々に、読んでいて嬉しくなる一冊。全ての本好き、古本屋好きの人に捧ぐ!という感じ。
やわらかな「進路」についての本、いいなあ。
イトウハジメ『美術の進路相談』は、妻のおすすめで読んだ一冊。ソフトなタッチの絵柄に惹かれて時間潰しのつもりで手にとったのだけど、ちょっと感動する一冊だった。著者は美術系の大学で教える美術教育の専門家。そんな彼が、「美術には興味あるけれど、美大に行くまでは…」というくらいの高校生をおそらく念頭に、好きな美術と今後も付き合っていくためのいろんな方法を提案している。
「美術の進路相談」といっても、「進路」の意味を広く捉えて、広い意味で絵を描くことや美術が好きな気持ちを将来に活かせる道を探っているのがいい。画家や編集者、イラストレーター、キュレーターなんかはもちろん、例えば、保育士さんも、人間が絵を描くことに最初に出会う仕事だったり、イラストを描くのが得意なのを活かせる仕事として入っている。こういうふうに広く仕事を捉えられるといいなあ。そして、学校を終えても、美術を好きでいて欲しいという気持ちに溢れている。柔らかなタッチなのは、絵柄だけではない。こういう文章を、自分も書きたいものだと思う。
この本を読んで、「いい本だなあ、こんな本を国語でも読んでみたいなあ」と思っていたら、Twitterで紹介していただいたのが、松井大介・漆原次郎『なるにはBOOKS 国語の時間』。これも、言葉の力を生かす仕事を広い意味で捉えていて、作家・司書・言語学研究者などの「いかにも」な仕事に加えて、声優、ウェデイングプランナー、裁判官、スポーツ選手、飼育係など、言葉を使う仕事を幅広く扱っているのがいい。それは、言葉というものの性質上当たり前のことかもしれないけど、「あ、自分もこうやって言葉を使ってるじゃん。言葉の使い手じゃん」と思える本というのはいいな。学校の図書館にも入れてほしい本だ。
少しずつ読んでいた2冊のお気に入り
12月、読書の合間に少しずつ眺めて楽しんでいたのが、吉田誠治『ものがたりの家』だ。見捨てられた駅の青年、几帳面な魔女の家、竜使いの郵便局、偏執的な植物学者の研究室、巨岩と暮らす家….など、ファンタジー映画の舞台になりそうな家ばかりを集めた美術設定集。本当にこのイラストから物語が動き出しそう。最初は「作家の時間の参考書にいいかな」と思って手にとったのだけど、いつのまにかそんなことを忘れて楽しんでしまった。
もう一冊、少しずつ読んでいたのが安房直子『ものいう動物たちのすみか』。月に1冊ずつ読んでいる、安房直子コレクションの3巻目だ。いずれも、動物たちが人間と自然に暮らしている世界を描いていて、読んでほのぼのするものが多い。個人的には、安房直子というとさびしいイメージがあったので、自分が狭い範囲の作品しか読まずに安房直子のイメージを語っていたこともわかる読書だった。
でも、「風のローラースケート」の中には、怖い思いをする表題作、人間がウサギになってしまう「よもぎが原の風」、谷間の宿に宿泊した恐怖を描いた異色の怪談「谷間の宿」、舞い落ちる桜に埋もれてしまいそうになる「花びらづくし」など、異界の動物と接することの恐ろしさを描く場面もある。自分はやはりこういうのに少し惹かれてしまうみたい。
どちらも参考になる、漢字指導の歴史と実践の本。
もうちょっと国語教育に関する本もあげておこう。別にエントリをたてて書いたとおり、阿辻哲次『戦後日本漢字史』は日本の戦後の漢字政策を批判的な視点から一望できる本。当用漢字が定められる時の国語「改革」は、小学校で習う教育配当漢字にも大きく影響している。自分としては、このくらいはちゃんと知って、必要があれば子供たちの質問に答えられる用意はしておきたいな。
同じ漢字指導がらみだと、小林一仁『バツをつけない漢字指導』も印象に残った。これはたしか、11月の全国大学国語教育学会で、登壇者の森田香緒里先生がおすすめしていた本だと思う。漢字学習の字体指導に対する指導基準を明確に示して、それを一つ一つ具体例をあげて論じているのがとても参考になる一冊だ。また、タイトルがらみでいうと、全ての漢字指導は形成的評価なのだから、バツをつけずに指導にとどめて、その場で書き直しをさせてマルをしてやれば良い、という立場を筆者はとっている。ただ、これ、理想はわかるのだが、それやると結局生徒がその場で直せば良いから事前に自宅で漢字を練習しなくなるのでは….という気もする。気もするというか、実際にそうなった現場も見ているので、ちょっと同意はしかねるなあ、という感じだ。でも、こういうのは比較研究できそうなので、してみるといいんじゃないかと思う。
モンゴルの民話ではなかった? 国民的教材の起源
そして、記念すべき(?)2023年最後に読んだ本は、ミンガド・ボラグ『「スーホの白い馬」の真実』である。いやあ、これもまた面白い本だった。余裕があったら別に一つエントリをたててもいいくらい。著者はモンゴル人の文学研究者。日本では光村の小学校教科書に長年乗り続け、「モンゴルの民話」として受容されている「スーホの白い馬」の成立史を記した一冊である。
まず驚いたのが、「スーホの白い馬」の話はもともとモンゴルには存在しなかったことだ。というよりも、そこに描かれている馬の習性や馬に対する扱いが、馬を熟知した人々の文化であるモンゴルではありえないことが多いようで、そこにびっくりした。たとえば、人が乗っていない馬を、馬の扱いに長けたモンゴルの馬乗りが集団で追いかけて追いつかないことや、それに矢を射掛けることは、モンゴルではちょっと考えられないことらしい。
なぜそんな齟齬が起きてしまったのか。それは、翻訳(というより創作)した大塚勇三が、モンゴルではなく中国語の「馬頭琴」をもとにお話をつくり、そこに絵を描いた赤羽末吉がモンゴルの自然のイメージを重ねたことによるところが大きい。本書では、もともとは男女の恋愛物語だったモンゴルでの馬頭琴伝説が、共産党支配下の中国でそれは資本家階級と無産階級の階級闘争を背景にした物語「馬頭琴」に姿をかえ、それがさらに大塚と赤羽によって「スーホの白い馬」に変化していく様子が丹念に追ってあり、国民的教材がこうやって「創られた」ことに新鮮な驚きを覚えた。また、そういった論証部分だけでなく、「モンゴル文化を日本人読者にも知ってほしい」という著者の思いが各所に溢れていて、そこもまた興味深い。
というわけで、よいお年を!
というわけで、大晦日になんとか更新した2023年12月の読書。本当は年間ベストもやりたかったけど、それは2024年の年明けにやりましょうか。でも、12月はけっこう好きな本と出会えて嬉しかったな。もう少し続く冬休みも、よい本に出会えますように。それでは、よいお年を!
[ad#ad_inside]








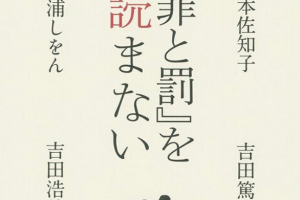
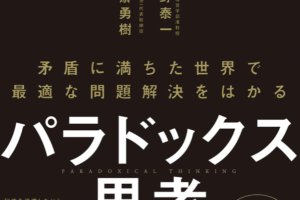

![[読書] 居場所をつくる人と、居場所に集う人。成田康子「高校図書館デイズ」「高校図書館」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/07/スクリーンショット-2017-07-02-21.47.51-50x50.png)
