阿部学・伊藤晃一『授業づくりをまなびほぐす』(静岡学術出版)は、初版2017年。現在はすでに絶版となっており、Amazonなどでも購入が難しい。しかし、このたび、ある方のご厚意でお譲りいただき読むことができたので、ここに個人的メモとして記録しておく。
動機は伊藤晃一さんへの関心でした
僕が本書を読みたいと思ったのは、率直に言うと伊藤晃一さんへの関心だった。例えば「授業づくりネットワーク」誌の最新号(48号『揃わない前提の授業を見る・感じる・考える』)でも、佐内信之さんが伊藤さんの授業を記録していて(佐内信之「揃わない前提の生徒たちが癒やされる「ケア」としての学び」)、それが非常に興味深かった。
また、第45号『「個別最適な学びと協働的な学び」を考える』で、伊藤さんは定時制高校勤務という立場から「個」という言葉がはらむ前提に鋭く切り込んでいて(伊藤晃一「定時制高校の授業は生徒の「個」にどう応じるのか 〜或いは「夜」という学習環境について」)、これも深く考えさせられた。それで、この方の授業実践をもう少し知りたいな、と思っていたのだ。
素晴らしい実践…なのだけど
本書は、その伊藤さんが執筆した第2部を、阿部学さんが担当する第1部・第3部がサンドイッチする形になっていて、目次を見ても阿部さんが理論編を、伊藤さんが実践編を担当したのだろうと思われる。伊藤さんの第二部は、読んでずっしり感銘を受けた。授業中にやるべきことが見つからず雑談をしていた苦しさの率直な吐露からはじまり、それでも「あの子は学校にきているから立派だ」という言葉に逃げずに、「じゃあ、授業はどうすれば?」と問い続けた人の授業の記録である。個人的な圧巻は、読書経験が乏しい生徒たちへの視写のトレーニングで、締め切りを厳密に守らせるところも含めて、学ぶ苦労と喜びを生徒たちに体感してほしいという筆者の覚悟が伝わってくる単元だ。他にも、中1の国語教科書の文章の「間違い」を発見させることをとおして、語句にこだわる読みを教える授業、ものづくりを通して古典の世界を体感し、テキストの読みの深さに向かわせる授業。どれも、伊藤さんが国語の授業で大事にしたいことに裏打ちされ、かつ、目の前の生徒たちが学びの楽しさを味わえる、素晴らしい実践だ。何より、国語という柱がすきっと力強く立っている点に感銘を受けた。なんだか、小学校に移って国語の力を育てることにこだわることがいいかげんになりつつある自分の目をさまされた気持ちで、本書を読み終える頃には、
人間関係による傷つきは人間関係によってしかケアできないように、学びによる傷つきは。学びによってしかケアできないはずだ(p140)
という言葉が、ずっしりと重いリアリティをもって伝わってくる(なお、自腹で教材を揃える話のリアリティもずっしりしている….)。
その枠組みで理解するでいいの?感もある
ただ、本書全体としてはちょっとちぐはぐというか、率直に言って阿部さんの章と伊藤さんの章がうまく噛み合ってない印象も受けた。阿部さんのゲーミフィケーションの話や、「教材発掘」に対してにとどまらない「教材デザイン」の話は、それはそれで有効な視点だろうし、子どものモチベーションを高めるための工夫として大いにありなのだけど、この理論の実例が伊藤さんの授業なのだろうか? なんだか対応していないように感じるのだけど…。(ちなみに、リアリティーとファンタジーの話も、子どもには子どもなりのリアリティーがある、という部分は首肯するものの、リアリティーとファンタジーの二項対立も、そんなに図式的で良いのかな、とは思った)
理論と実践のちぐはぐさという点では、実はそれは当の伊藤さんも同様で、例えば本書では、例の視写の授業をゲームという概念を使って伊藤さん自らも説明していたけど、本当にその言葉があの授業の迫力や魅力を説明するのにふさわしい理論的枠組みだっただろうか? 失礼ながら、せっかくの授業が、この用語をあてはめることでかえって色褪せてしまう感すらあった。
というわけで、ちょっともったいないな、というのが正直な読後感である。著者のお二人は本書をつくる過程できっとたくさんやりとりしてきて、そのどこかで分担執筆案と採用したのだろうが、それが悪いほうへ出てしまったのかもしれない。お二人の本づくりのプロセスの中に必ずあったはずの、お二人の思いが重なったところを本書にもう少し反映してもらえたら、にぶい読み手の僕にも、もっと得心がいったのかもしれない。あるいは、第3部は阿部さんと伊藤さんの対談とかでもよかったかもしれない。
そんなふうに、全体の構成や部ごとの関連については、ちぐはぐな印象が否めなかったものの、でも、伊藤さんの実践は素晴らしかった。もっと読みたいと思う。阿部さんによれば、続編にあたる『教材づくりをまなびほぐす』も構想中(2024年4月時点)とのことで、次のお二人の共著を楽しみに刊行を待ちたい。
追記)著者の伊藤さんより、「ゲーム」について補足
上記のような雑駁な感想を書いたところ、著者のおひとり・伊藤晃一さんがDMで「ゲーム」という概念で説明した意図を次のように教えてくださいました。こういうの、ブログをやっている「役得」ですね。本書を理解するのにとても有益な補足と思い、ご本人の許可をいただいた上で、こちらにもそのまま転載します。伊藤さん、どうもありがとうございました!
私がゲームという概念で考えようとした背景には、生徒が、授業という営みを、何かを学ぶ営みとしてではなく、単に単位を修得することをゴールとして必要最低限の努力でやり過ごすような営み(授業終了5分前に登校して出席点を稼ぐとか、授業は荒らさないけどスマホを隠し見しているような笑)として過ごしている、言わば「単位とりゲーム」をプレイしているように感じたことから来ています。このような状況は「内職」などの言葉で表現されることもあるのですが、つまらない授業より「塾の課題」に「好きなもの」に時間を当てたいとする「内職」とは、在り方が随分違うように思うのです。定時制高校の生徒たちが、そのようなことをするのは、学びによって傷つかないようにするための適応方略を採っているからではないだろうかと見える時があります。もしそうであるならば、とかく適応方略としての「単位とりゲーム」になりがちな授業を、もう一度、学びにつながる授業に戻すためにはどうしたらいいのか、どうすればこの状況を学びへつながる回路にもう一度繋げられるのか、と考えました。そして、(当時はそこまでは考えていなかったのですが)視写の授業は、ある意味では彼らのゲームに教師が「あえて」乗った実践だったのではないか、(もちろん視写はの実践はこれだけで語り尽くせぬものではあり、先生のご指摘にもご回答できていないのですが)、と考えました。

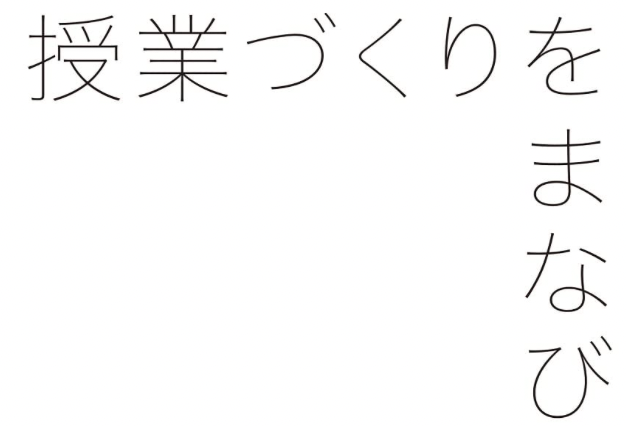





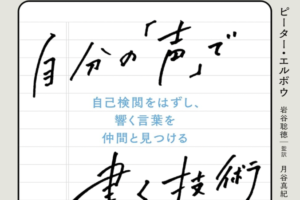


![[資料] 今あらためて読みたい、「体罰」がいけない理由](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/09/スクリーンショット-2017-09-04-20.05.06-50x50.png)
