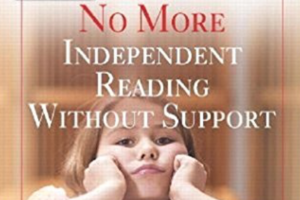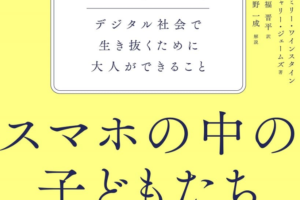阿辻哲次『戦後日本漢字史』は、明治以来の「漢字廃止論」「漢字簡略化論」の流れを背景として、戦後の「当用漢字」や「常用漢字」の制定がどのようになされ、それがどんな問題を生んでいるのか、また、ワープロのような技術革新が字体にどのような影響を与えているのかをまとめた本である。常用漢字、特に小学校で学ぶ「教育漢字」(学習配当漢字)の中にも、この戦後の漢字政策の影響を受けている漢字はたくさんある。漢字を授業で扱うものとして、予備知識として知っておきたいことがたくさんあり、面白い読書だった。通常の小学校の先生がここまで知識として持っておく必要はないけど、知っていれば漢字に対する見方の奥行きは深くなるはず。
日常で出会う「なんでこう書くの?」
今年の授業では、授業開始時に子どもたちが作った漢字クイズが軌道に乗って、子どもたちの漢字への関心や、「漢字がパーツからできている」ことへの意識が高まってきた。でも、そうすると、時々、子どもの一部から鋭い質問が出てくる。例えば、「広と廣は一緒の字?」「「辻」はしんにょうに点々が2つあるけど、正しいの?」という質問。特に、人名に使う「廣」「辻」のような旧漢字(康熙字典体)や、山「﨑」や「髙」橋のような異体字が、質問の対象になりやすい。名前はとても身近な学習材なので、ここから漢字への興味を広げられないかな、と思っている。
また、「漢字をパーツに分ける」意識を持たせようとすると、どうも説明しにくい漢字も出てきた。例えば、五感の一つの「嗅覚」の「嗅」。。「嗅」は「口に自に「犬」」なのに、「臭う」だと「自に「大」」になって、「犬」ではなくなってしまう。これ、なんで?
こういう身近な「なんでそう書くの?」に答えようとすると、しばしばぶつかるのが戦後の国語国字問題だ。旧字体(康熙字典体)から新字体に改めるときに、漢字が大幅に簡略化された。その影響で漢字の成り立ちがかえってわかりにくくなってしまう例が結構ある。(もちろん、「なんでそう書くの?」の全てに答えられるわけではないのだけど…)
戦後の漢字政策の流れを概観
というわけで、戦後の国語改革(特に当用漢字字体表の制定から常用漢字の成立)について改めておさらいしようと手に取ったのが本書、阿辻哲次『戦後日本漢字史』である。結論から言うと、これは国語教師なら一冊持って損はない本だと思う。明治時代の「漢字廃止論」から始まる国語「改革」の潮流の説明から始まり、実質たった二ヶ月の検討で作られた戦後の当用漢字表の制定、人名用漢字の制定、そして常用漢字表の制定と平成時代のその改定と、戦後の漢字政策の流れがわかりやすくまとまっている。そして、そこで具体的にどういう改変が行われ、結果としてどんな問題が生じているのかも具体的に記述されている(ちなみに、「臭」の「犬じゃなくて大」問題についても書いてます)。
本書の記述の中で、僕が初めて知って面白かったものをあげていく。やや雑学的なものも含まれているが、どんな議論を経て当用漢字表が定められ、それがどんな問題を孕んでいるのかがよくわかる。
- 大正時代にも国民の学習負担軽減を目的とした「常用漢字表」制定が試みられた。これは、紙面に使う活字を減らして経費削減を図りたい新聞社の後押しもあって大正12年9月1日からこの表に基づいて新聞が作られるはずだったが、ちょうど関東大震災が起きて頓挫した。
- 戦後の当用漢字表は、昭和21年6月から8月にかけての実質2ヶ月ほどで原案が作られ、10月には審議終了して11月には内閣訓令として官報に掲載された。
- 「当用漢字表」に続いてまとめられた「当用漢字字体表」は、字源主義や康熙字典に範を取ることを明確に否定し、簡易化を目指して作られた。
- 戦後、当用漢字表に採録されなかったが故に、別の言葉に変えられる漢字や熟語がたくさん現れた。「探偵」の「偵」が表外字になったため、「探偵小説」に代わって「推理小説」という言葉が一般的になったり、「瀆職」が「汚職」になったりした。
- 熟語を構成する一字が表外字になった場合は同音の別字に変える例が多く、「肝腎」→「肝心」、「日蝕」→「日食」、「臆測」→「憶測」、「稀少」→「希少」などの例がある。
詳しくて面白い、当用漢字の制定事情
これらの中でも特に興味深かったのは、戦後の当用漢字の字体が、学術的な語源主義や規範主義(康熙字典体の規範化)を明確に否定して定められたというくだりである。字源的には違うとわかっていても形が似ていれば一緒にする方針で、当時の字体の選定に関わった文部省の嘱託職員(林大氏)の談話を引用しつつ、筆者は林氏を次のように批判している。
このずいぶん「お気楽」な談話から見れば、字体表における字体の選定は、専門家が議論をくりかえし、検討に検討を重ねておこなわれたものとはとうてい思えない。誤解をおそれずにいえば、ごく少数の人による密室の作業であって、その結果に対する外部からの意見はまったく反映されることがなかったようだ。(p113)
字体選定に関わった人々が、漢字を平易化することで国民の負担を減らすことを目的としていたのは疑いない。とはいえ、「しめすへん」が「示」から「ネ」になったのも、一画を減らして簡略にする意図だったようだが、それが逆に「ころもへん」との混乱を生んでしまっている現状を見ると、善意で敷き詰められた道がどこにつづいているのか心もとない感がある。とはいえ、それを批判して康熙字典体に戻せばいいかというと、そんなことはない。どんなに字源通りでなくても、実際に使われてしまっている現状は強力で、平成22年に29年ぶりの常用漢字表改定に関わった筆者自身が、なかなか慎重にその問題に対処している姿は印象的だ。
漢字の戦後史をたどる格好の書
戦後の国語改革を扱った本が大抵そうであるように、本書もまた国語改革に批判的な筆致である。でも、国語改革の歴史をたどり、また、ワープロが漢字の字体にどのような影響を与えたか(よく出てくる森鷗外の「鷗」が「鴎」になる問題)まで、漢字の戦後史をたどるには格好の書。
これまで読んできた本との関わりも書いておく。笹原宏之『漢字の歴史』は、日本以外の国も含めて漢字文化圏の広がりと、その中での日本の漢字需要について感じさせてくれ、円満寺二郎『漢字が日本語になるまで』は、漢字が日本に輸入されて音読みと訓読みが生まれ、そこからどうやって日本語としての漢字になっていくのかを、複数の視点から描いてくれている。
概説的なそれらの本に比べると、本書は戦後の当用漢字の成立や情報機器の影響による漢字の変化に話題を絞っており、その分、一つ一つの事例も詳しくて、「あの基本的な漢字も新漢字体だったのか」と思う事例も結構あった。漢和辞典アプリを弾きながらの楽しい読書。ぜひ、身近な漢字をあらためて見直す一冊にどうぞ。