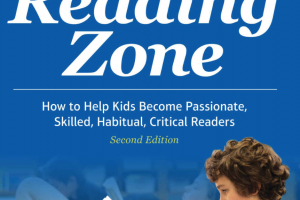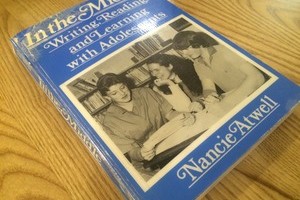In the MIddle読書日記もいよいよ後半戦。ジャンルを扱った第3部も、詩と回想録が終わり、Chapter.11はショート・フィクション。日本で言う掌編小説である。
▼
このジャンル、実は以前に読んだ第2版には存在していなかった。 「あ、今回はこんなのもあるんだ」と思いながら読みはじめたら、この章にはアトウェルがショート・フィクションを教えるに至る経緯が書かれていて、大変面白い。
▼
まず、アトウェルはもともと1980年代から1990年代まで(つまりIn the Middleの第1版と2版の時期)、生徒にフィクションは書かせていなかった。p462によると、これにはもともと、彼女のライティング・ワークショップの師がドナルド・マレーであることの影響も大きかったようだ。マレーは、ドナルド・グレイブスと並ぶプロセス・アプローチの初期の研究者・教育者で、アメリカの作文教育に多大な影響を与えた人。自身、ピュリッツァー賞を受賞したジャーナリストでもあるので、その影響を受けたアトウェルの作文教育も、「事実をどう伝えるか」という方面に偏りがちだった。また、フィクションを書かせない理由を聞かれた時にも「推敲することを学ばせたいから。生徒の書くフィクションは、白昼夢みたいな荒唐無稽のものだから、それに向かない」と否定的に答えている(p461)。
▼
そのアトウェルが変わったのは、自分がフィクションを教えない真の理由が「フィクションの教え方を知らないからだ」と自覚してからのことだ。彼女は、生徒がフィクションを書きたがることは知っていたので、まずショート・フィクションを集め、たくさん読むことからはじめる。とりわけ、マイクロ・フィクション(たぶんショート・フィクションの中でも比較的短い部類の小説)には、クラシックな小説の読者として偏見を持っていたので、その偏見を克服することからはじめたらしい。
こういう試行錯誤の中から、キャラクターに重点を置いてショート・フィクションを書く方法(p463-464)や、効果的なマイクロ・フィクションの評価基準(p473)などが生まれてくる。マイクロ・フィクションの評価基準は、この取り組みをはじめて3年目になって生徒と作ったものらしい。また、ハーバード大学の研究者に自分の生徒たちの作品を読んでもらって「日常性に根ざしたものが9割を占める」と指摘されると、「それはきっと自分の指導が彼らの想像力に制約をかけてしまっているせい」と反省もしている。
▼
この時のアトウェルはおそらく50歳を超えているはずだ。In the Middleの初版と第二版が作文教育における古典となり、自分の学校をたててそこでの実践も高い評価を受けている50歳代の人が、自分に欠けているものを素直に振り返り、新しいジャンルに挑戦する姿勢には、素直に感銘を受ける。何歳からでもはじめられる。何歳までも学び続けられる。「教師の教師」でもあるアトウェルは、学びつづける自分の姿を、意識して読者の僕たちに見せているのかもしれない。
[ad#ad_inside]