大村はまの教え子であり、晩年には世話もしていた苅谷夏子による、大村はまのエッセンスの紹介。大村はまの言葉の引用と、それについての苅谷のコメントという形式。
▼
今回読んで印象に残った大村の言葉をあげておく。特に、僕の関心のフィールドである作文についてから。
いい作品、おとながほれぼれするような作品ができるか、出来ないかということについては、私はたいへんおおらかに考えていまして、気にいたしませんでした。人間の成長がないところには文章の伸びはないということも考えますし、そんなに文章の上手な人はたくさんいないものだということも考えます。また、学習はいっしょにやっていますが、その結果が見られる時期は、じつにまちまちであることも考えます。結果、結果、 ――私がそういうことを気にしたら、子どもはどんなに不幸せかと思うのです。……もっともっと書く力というものは、根本に培われていくべきもの、そして、その人の上手・下手ということとかかわりない世界で根深く、根強く、成長するものと思うのです。(p128)
どんな考えでも、たとい、よい考えと思わなくても、これかなと心に出てきたことは、どんどん書いて、字で書かれた「目に見えるもの」にしていくといいのです。すると頭の中だけで、あれこれ思いくらべていた間とは違って、だんだん、光がさしこんでくるように、いろいろな考えの区別がついてきます。(p135)
この2点の考え方は、作文指導では比較的よく語られることだ。特に一つ目は、作品ではなく書き手を育てるというプロセス指導の根本的理念そのものでもある。
(子どもが作文を書きたがりません、という相談に対して)「子どもの数の二倍くらい、できれば三倍でも、題材を、あなたが拾ってみせるといいのです。先生なら、子どもたちとその生活をよく知っているのですから、それを大事な根拠として、一人ひとり顔を思い浮かべながら、あの子にはこの題材がいいだろう、この子にはぜひこれを書かせたい、というような具体的なとらえ方をするのです。そういう題材をてびきとして与えてごらんなさい。そして、それぞれの題材に、書き出しの一文を示すといいのです。きっと書き出しますよ」(p134)
この助言は面白い。同じプロセス重視の作文指導でも、一般的なライティング・ワークショップと大村はまの違いが明確だ。ライティング・ワークショップでは、「何を書きたいかは本人が一番知っている」スタンス。だから、書くことがないという生徒に対しても、カンファランスなどでの質問を通じて生徒の書きたい題材を引き出していく。一方の大村は、「生徒が本当に書きたいことは、生徒ではなく教師が知っている」というスタンスだ。
これは究極の「おしつけ」なのだろうか? しかし、徹底的に生徒のことを見る視線がないとこのスタンスは不可能で、「圧倒的な教材開発と、個々の生徒への深い理解に基づいて、最適なてびきを手渡す」事こそが、大村の真骨頂であり、誰にも真似できない点である(実際こんな助言されても実行不可能なんじゃないか…)。こういう「おしつけ」はもはや「おしつけ」ではない。
中学生なんかは、一生の間で、いちばん作文の下手なときではないかと思っているのです。どうしてかと言いますと、生意気で、あまり深くものごとを考えないのに、軽率に何か言い散らすのが得意な時代ですね。あまりものを深く考えることができないのです。ですけど、いろんなことを浅く知っているのです。そして、自分らしい考えなのか、それとも人の言ったことなのか、あまり区別のつかないときなのです。(p54)
中学生というのは小学生と違って、あまりつまらないことは書く気にならないからです。書く価値と思わないと書かないと思います。…なかなか頼もしいことだと思います。(p133)
ここに見られる「中学生」観も面白い。「いちばん作文の下手なとき」でありながら「頼もしい」。生徒を厳しく鍛えながらも尊敬していたという彼女らしい台詞だ。
▼
話し合い指導についての次の言葉は、話し合い指導に限らない普遍性がある。
(話し合いは、)誰かが誰かをバカにしているという教室では、どんなふうに教えても、どんなふうに指導しても、できません。バカにしている人と話し合いたいという気持ちが湧くはずもなく、バカにしている人の発言を誘ったり、バカにしている人の発言を心をこめて聞くなどということはできはしません。また、バカにされていると思っている子が発言するわけがありません。(p100)
「安心できる教室」がないところに学習はない。わかってはいる。それをどう作るのか。優劣の彼方で生徒が真剣に学ぶ場を作るというのが、大村の追求した課題だった。
そして、次の教師に向けた一言には、たしかにドキッとしてしまった。言葉へのこういう厳しさを、自分にも他人にも持ち続けた人なのだ。
一番先に浮かんだ言葉は使わないこと。たぶんそれは自分の癖だからいつも同じことを言っていることになる。(p79)
▼
ちなみに、同じ著者による大村はまの伝記はとても読み応えがある。未読の方はぜひどうぞ。
[ad#ad_inside]




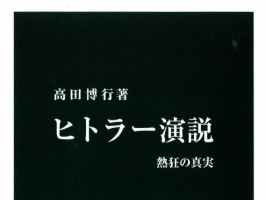
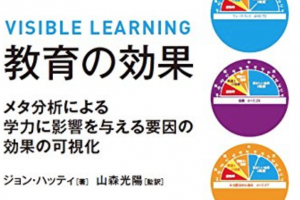


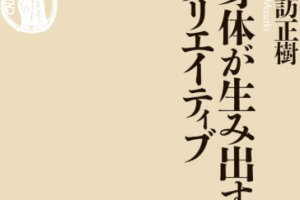


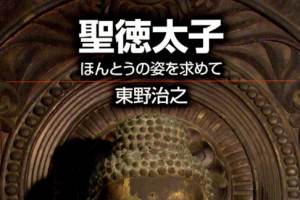
![[読書] これはこれでいいかも? さがら総『変態王子と笑わない猫』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/11/スクリーンショット-2016-11-22-18.03.54-50x50.png)
![[読書]オンライントークイベントに参加してきました。石井英真・編『流行に踊る日本の教育』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/02/f67a992cb759a5f85fe7ee8cf7c25157-50x50.png)