6月に入って一週間くらいたっちゃったけど、毎月恒例の読書エントリ。5月はゴールデンウィークもあってそこそこ本は読めたのだけど、結果的に児童書に印象深い本が多かった月。特に冒頭に掲げる一冊は、自分が「書くこと」について考えてきたテーマともかさなって、ゆさぶられた本だった。
目次
人が書けなくなるとき。磯みゆき『それで、いい!』
まずとりあげたいのは、磯みゆき、はたこうしろう(絵)『 それで、いい!』。絵を描くのがすきなキツネ。でも、やまねこは「へんなの、だっせえ」と笑い、あひるは「色がはみ出している」と欠点を指摘してくる。そこでキツネは、すごい絵を描こうとして「すごいもの」を探しにいくが、みんなにどう思われるかばかり心配になってきて、描けなくなってしまう….。というお話。
これ、ツイッターで教えてもらって読んだ本なのだが、まさに拙著『君の物語が君らしく』の「他者の視線を意識することで書けなくなる」問題そのまま。やまねこやあひるの発言に奮起して「すごい絵」を描こうとするキツネが、どんどん自分を追い詰めていく過程や、うさぎに出会って「描きたいから描く」をとりもどす過程は、読んでいて胸熱だった。テーマへの共鳴や、自分が120ページくらい費やして伝えようとしたことが、こうやってお話の形でも伝えられるんだな、という驚きや感心の意味もこめて、今月のベストに。
読んで楽しい、『エルマーのぼうけん』の作者の伝記
前沢明枝『「エルマーのぼうけん」を書いた女性ルース・S・ガネット』は、タイトル通り、あの『エルマーのぼうけん』の作者を扱ったノンフィクション。いわゆる伝記とはちょっと違って、2011年に当時90歳近い著者に会いに行った聞き書きの記録である(ちなみにwikipediaの記述が正しければ、ガネットさんは御年100歳で、まだご存命のようだ)。
まあ、このガネットおばあちゃんのお茶目なこと!小さな子と一緒にスキップしたり、雪道をものともせず車で行こうとしたり、かと思えばゴミ出しがなってない若者に説教したり…頑固で楽しいおばあちゃんという感じで、読んで親しみがわく。そんな中で、幼い頃の両親の離婚、お話づくりが大好きだったこと、「仕事」を中核に置いた、小学校でのオルタナティブな学び方など、彼女の人生に決定的な影響を与えることが語られていく。
数あるエピソードの中でも特に興味深かったのは、『エルマーのぼうけん』の原題がMy Father’s Dragonであり、語り手が常にエルマーのことをMy fatherと語っていた事実。これは、翻訳だけからはわからなかったな。継母もまきこんだ家族の一大プロジェクトとしての『エルマーのぼうけん』は、ルーシーにとって、子ども時代と「いま」の家族をつなぐ大事なプロジェクトだったんだと思う。職業としてのためでなく、自分のために書かれた『エルマーのぼうけん』の三部作。何度も読んだ本だけど、ちょっとまた読み方が変わりそうだ。
他にもよかった児童書が….!
同じ児童書つながりで、マイケル・モーパーゴ『トンネルの向こうに』。モーパーゴのライフワークでもある戦争を題材にした自動小説で、今回の舞台は第二次大戦中のイギリス。住む町がドイツ軍の空襲にあってコーンウォールに逃げる途中、少年バーニーと母は、汽車の中で不思議な男に会い、その友人ビリー・バイロンの話を聞く。ビリーは第一次大戦の英雄で、敵軍の若きドイツ兵を救ったが、実は救ったその相手がのちのアドルフ・ヒトラーだった…という話。人の命を救う行為が、のちの大量の人々の命を失わせる結果になったことを知ったビリーが、どんな選択に出るのか。なかなか重いテーマの小説だ。モデルとなった実在の兵士ヘンリー・タンディの存在自体はじめて知ったのだが、ほんと、実際にこの立場になったら、どんなふうに思うのだろう…。
児童書というか、絵本をもう一冊。M.B.ゴフスタイン『ピアノ調律師』。ピアノ調律師のルーベン・ワインストックが自分の孫娘のデビーにピアニストになってほしいと望むのだが、一方のデビーは祖父の姿を見てピアノ調律師になりたいと願っている。そんな親子のすれ違いの状態が解消され、やがてルーベンもデビーの選択を応援するようになる…という物語。ルーベンが口では「ピアニストのほうがいい」と伝えても、その仕事ぶりの素晴らしさで調律師の魅力が伝わってしまう話として、森田真生さんが紹介されていた。そういう文脈でも読めるし、でも心の奥底では、ルーベンはやっぱり自分の仕事に誇りを持っていたし、その仕事に孫娘が憧れることを、うれしく思っていたのではないかとも思う。いずれにせよ、うつくしい物語だ。
大人向けの本では、スケールの大きなこの一冊
というわけで5月は児童書の印象が強いのだけど、大人向けで面白かったのは、スティーブン・ジョンソン『世界をつくった6つの革命の物語』。これは、風越の有志中学生が参加するプロジェクト、日経Stockリーグの課題図書になっていたので読んだ一冊だ。
ガラス、冷たさ、音、清潔、時間、光という6つの発明をめぐる歴史。「新・人類進化史」のサブタイトルが象徴するように、「砂糖の世界史」のようなモノ視点の世界史を、もっと大きなスケールでやった本で、なかなか面白かった。特に興味深かったのは「冷たさ」かな。氷の貿易が始まった頃のドタバタも面白いが、冷房ができることで暑い地域にも人が住めるようになって人口の移動が起きるという話はとても興味深い。「音」のところで、エジソンが、「孤独な天才」というよりは商売上手な企業のリーダーという感じなのも面白かった。いま、高1の息子が『銃・病原菌・鉄』から『サピエンス全史』へと読書を進めているけど、今の彼に紹介したらちょうどいいだろうな。
ことばの力、詩の力
BRUTUS2024年6月号・特集「一行だけで。」も、ふだんあまり読まない雑誌ではあるが、非常に印象に残った読書体験だ。ちょうど「読書家の時間」で読んだ本からお気に入りの言葉を紹介する活動をしていた頃でもあり、その参考になった。本誌には、現代の比較的若い世代の詩人・歌人・俳人も多く登場して、中には僕の知らない人も多い。その意味で、勉強にもなったし、面白い一言や俳句、短歌をさがすのも楽しかった。これ、まだ手元にない人はぜひ次号が出るまえに入手しておくことをおすすめします。ことばの力を実感できる一冊です。
このBRUTUSの影響もあって今月は詩集や詩のアンソロジーをいくつか読んだのだけど、一番印象深かった詩集は張文經『そらまでのすべての名前』。ルクス・ポエティカという思潮社の新鋭詩人シリーズで、序詩「そのひとの呼吸」の「そのひとの胸に耳をおしあてると/とおい森がきこえた」という書き出しに惹かれて読み、購入することに。わかるかわからないかというとわからないのだけど、好きか嫌いかでいうと好き。好きだったのですべての詩を音読したのだが、自分がきちんとこの詩の良さを語る言葉を持っていないのがくやしい。こういう詩の良さを語る言葉を持ちたい。いつか、作家の時間の自分の作品で挑戦してみようかな。
今月の山読書からは、この一冊。
最後に、今月の山読書から。5月は下旬に学校行事のアドベンチャー登山の引率もあったので、実用目的の本もさらっといくつかさらったのだけど、ここに書き残したいのは、石田千『山のぼりおり』。小説家・石田千の登山エッセイ集。最初が北八ヶ岳の天狗岳で、親しみを持って読むことができた。この人の文章、とても描写的で、匂いや音がたちあがってくるような文章。力みのない感じもいい。こんなエッセイ、書きたいなと思わせる。この本を読んだあとに仕事の下見で天狗岳に行くことになって、その意味でもなんとなく「つながり」を感じさせてくれた一冊。これから山登りのシーズンも本格化。近所の里山へ、北八ツへ。そして今年は、南八ヶ岳の硫黄岳〜横岳〜赤岳も縦走したい。山読書で気分を盛り上げていこう。


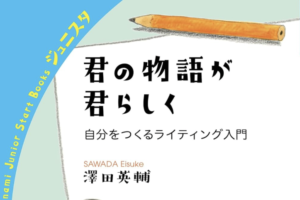
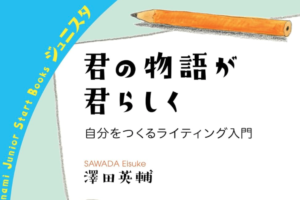

![[ITM初版]In the Middleのタイトルに込められた意味](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/51rNbV5S1ZL._SL160_-1-50x50.jpg)
![[読書]一年の最後に良い出会いが目白押し!2023年12月の読書](https://askoma.info/wp-content/uploads/2023/12/a-book-6213537_1280-50x50.jpg)
![[読書] 主人公を突き放した筆致がいいな。住野よる「よるのばけもの」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/04/スクリーンショット-2017-04-23-18.46.32-50x50.png)