先週の土曜日、北八ヶ岳の双子池のほとりで、向坂くじら『犬ではないと言われた犬』を一気読みした。詩人であり、国語教室ことぱ舎を運営する著者のエッセイ。第一エッセイ集『夫婦間における愛の適温』は結婚生活がテーマだったが、今回はことぱ舎での日常、書くこと、そして国語と関連する話題が中心のエッセイ集。学校ではない場所で、それでも「教える」ことにきちんと向き合っている人の言葉として、とても刺激的な一冊だ。
[ad#ad_inside]詩人であること、教える人であること
学校で、外部の詩人や作家を招いてワークショップを実施することは、よくあるとまでは言わないまでも、まあ教室ではしばしば見られることだ。ただ、残念なことにそこには、ある種の詩人の消費のされ方(とあえて書く)のパターンもある。それは、ふだんの学校の国語の授業とは一味も二味も違う、自由で、否定的評価のない創作ワークショップをして、「どの作品も素晴らしいですね!」「書くことって自由なんですよ」「みなさんも書くことを楽しんでくださいね」と明るく前向きに総括をしてチャンチャン…しかし、翌日からはまた変わらぬ国語の授業が繰り返される、というやつである。これは詩人や作家が悪いというよりも、一義的には、詩人や作家を「異邦人」として一種のガス抜きに使う構造の問題なのだけど、そういう構造を知りつつ、詩人の側が学校の期待にうっかり応えてしまう場面も多々あると思う。
向坂くじらは、違う。
….とまで言えるかどうかは、本当のところわからない(笑)。でも、このエッセイを読むと、書くことをめぐって「誰もが素晴らしいよ」「書くことは自由だよ」で終わらない彼女の心意気が各所にうかがえて、この人は詩人であることと教える人であることの両方の間で、まっとうに何かと切り結んで戦っている人であることがわかる。
国語教室を開く決意
その姿勢が最も鮮明に打ち出されているのは、巻末のエッセイ「ミケ」である。著者がある詩の創作ワークショップで出会った、本も教科書も読まない小4の少女をめぐるストーリーだ。彼女はミケとかつての自分を重ねて次のように書く。
あまり考えずに気軽にできるやり方で詩を作らせ、それを褒め、「学校ではこんなこと教えてもらえない」なんて言わせてしまうこと。それは暗に、勉強なんてしなくてもいい、ひいては成長なんてしなくてもいい、というメッセージを発してしまうのではないか。それも、私がその自由さをもって愛しているはずの詩を、錦の御旗に掲げて。
そして、あのときのわたしに必要だったのは、果たしてそんなものだったか。対等らしい関係や、誰にも等しく与えられる明るい褒め言葉、そんなもので、しじゅう腹をたてていたあの女が、本当に満足しただろうか。(p199-200)
彼女は、この創作ワークショップの帰り道、電車で聞いた歌の歌詞から、少女ミケや自分の過去に思いを巡らし、大泣きに泣き、電車を降りるときには国語教室を開く決意をする。現実に抵抗するための、たしかな力をつける場所として。
本書の最終章に配置されたこの開塾のエピソードは、ちょっとドラマチックにすぎるのだけど、読んだとき、自分の体がカッと熱くなった。急いで本をザックにしまい、池を出立して猛烈なスピードで双子山をのぼり、あっという間に大河原峠までかけおりた。それくらいの熱いエネルギーをもつ文章だ。「そのままのあなたでいいよ」と言ってあげることは簡単だが、向坂くじらは、その安易さに寄りかからない。
気になる言葉や思考がたくさん!
本書には、他にも刺激的な思考をもたらすエピソードや文章がたくさんある。そして何より、文章が抜群にうまいのだ。「口笛同好会が、空中分解していた。」という巻頭エッセイ「くちぶえ、ソロで」の書き出しなんて、その先が気になるでしょう?
かつて『檸檬』を扱った国語教師が言い放った許せないひとこと。自分には解けない詩の入試問題。ことぱ舎の塾生の作文に手を入れた教師への怒り。ことぱ舎の教室の机と椅子の配置をどうするか….。本書では、そんな、国語教師の読者にも身近な話題をとりあげつつ、でもこちらの発想を、時に軽々と超えたり、時にその隙をついたりする言葉がかしこに散りばめられている。
読んだり書いたりすることのもっともいいところは、ひとりでできるところである。…読むことと書くことだけが、わたしをはるばるとひとりぼっちでいつづけさせてくれる。それはさびしく、それでいてうれしくて、なによりこの上なく自由なことだった。(p12-13)
書きたいことを自由に書けないから、しかたなく型が必要になるのではない。書きたいことを自由に書くためにこそ、まず型が必要なのだ。
書くことによって事象は、書かれたことと書かれなかったことに二分される。なにをどう書こうとも、書かれなかったことがかならずあまる。(p154)
これらの中には、自分も共感できるけど、そこまでの切実さはなかったこと、はっとさせられたこと、自分はどうかなと思わず問い返してしまうこと…いろんな言葉がある。
学校ではない場所で戦っている人
著者は、学校の国語教師ではない。隣の人とのコミュニケーションの楽しさが、一人で言葉と対峙する楽しさを軽々と超えてしまうことを「大敗」(p14)と言ってしまうあたり、学校の教師には向かないだろう。というのも、学校とは、良くも悪くも、言葉をコミュニケーションのツールとして「人格の完成」(教育基本法)という崇高な目的に向かう場所だからだ。そこでは、常に言葉は手段として教育に隷従しなくてはならない。そんなのやってられっかばかばかしい、とまで公然と言い切る勇気は、僕にはない。おそらく彼女は言うだろう。
一方で、彼女は、学校教育のオルタナティブとして「なんでもあり」「そのままでいい」を標榜することもない。ことぱ舎で、生徒たちに、たしかな言葉の力をつけさせようとする。詩人なのに(詩人だから?)国文法の授業をきっちりとやる。受験生も受け持つ(詩の入試問題は解けないけど)。学校ではない場所で、でも確かに、子どもたちの成長のために、日々模索して、戦っている。例えば書く手が止まった生徒の横で、40分、自分も書きながら待ち続けるというように。
そういう人の言葉は、僕たち学校制度の中にいる人間にとって、ちょっと違う風景を見せてくれて、とても刺激的だ。僕は何度か直接お話しさせてもらったこともあるが、作文へのフィードバックをはかる「次を書いている」という言葉は、彼女との会話の中で得たもので、その後、指針となっているものだ。
そういうヒントが、本書の中からもたくさん見つかるかも知れない。でもそれ以前に、単純に面白いから読むといい。抜群に面白くて、こちらを突き動かす熱がある。『犬ではないと言われた犬』は、そういうエッセイ集だ。
[ad#ad_inside]




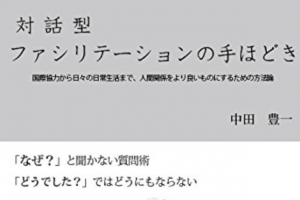

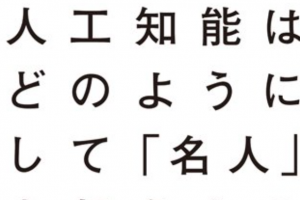


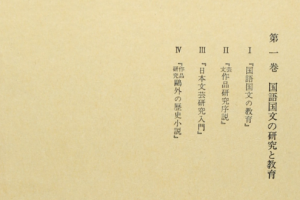


![[読書]ネガティブな感情に向き合える子をどう育てるか?藪下遊/髙坂康雅『「叱らない」が子どもを苦しめる』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2024/04/4e685d6ad4dbe60ad73a4e1359b7d9c5-50x50.png)