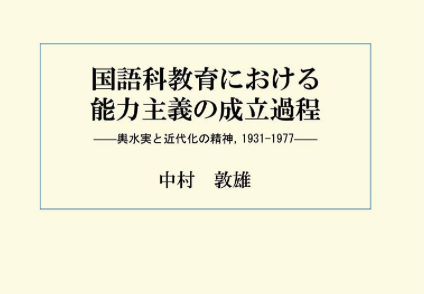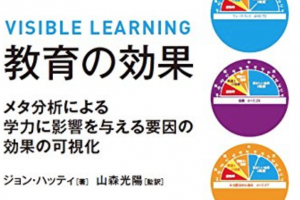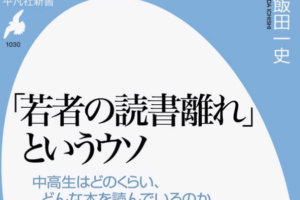中村敦雄「国語科教育における能力主義の成立過程」を読みました。読みの指導において「能力」がどのように定められ、指導されてきたかを論じる国語科教育史の本。本文でも650ページする本なので軽く目を通すだけのつもりが、面白くて最後まで読んでしまったよ…。
[ad#ad_inside]「読む力」が議論されてきた歴史
この本で扱う「能力主義」とは、能力の育成を教育活動の目標に据えて、その効果的な育成を重視する教育学の立場である。例えば、この本の主題である「読むこと」の教育でいうと、単に何かの教材を読むのではなく、その活動を通じて何らかの「読む力」を育てることを目標とする立場だ。今では当たり前のこのパラダイムがどのように成立し、そして「読む力」の具体がどのように議論されてきたのか。輿水実を軸にして戦前の1930年代から1970年代までの歴史を描いたのが本書である。
経験主義から能力主義へ
中心となるのは戦後期の1945年代〜60年代あたりだろうか。戦後すぐに始まったアメリカの新教育に範をとった児童中心の生活経験重視のカリキュラムが、教育目標を見失ってただ経験させるだけの「這い回る経験主義」となって失敗する。そこから、特定の能力を育てることを重視する能力主義へのシフトが始まり、その流れの中で、「読む力」の下位の要素も議論され、系統性が模索されていくのだ。
生活経験重視の風越学園のスタッフとしては、やはりここの経験主義から能力主義への展開が興味深い。結局、育てる力が何なのかの意図が不十分だったり、環境が整っていなかったりすると、経験主義がただのやらせっ放しになるのはよくわかる話である。
もちろん、「能力を育てるためにどのような経験をするのが良いか」という観点から言えば、経験主義と能力主義は決して相容れないものではないし、輿水実も倉沢栄吉も大村はまも、そういう意味では両者を対立的には捉えていない(経験主義の具体的な現れである授業や単元学習への評価はいろいろであるにせよ、だ)。
ただ、1956年(昭和31年)の全国学習調査やその後の学習指導要領改訂(昭和33年)を経て、育てる「能力」が前面に出て、しかもテストに対応する能力に矮小化されたことで、多くの国語の授業では、生きて働く場から切り離された「能力」が一人歩きしたのは、不幸な展開だったと思う。
興味深いトピックがたくさん
そういう大きな話を抜きにしても、こういう歴史の本には興味深いトピックがたくさんある。例えば、次のようなところ…
- 「全体をいくつかの段落に分けて最初にざっと全体を読んでから各段落の内容を丁寧に読む」指導法が1930年代にはすでに存在してて、しかも「発展を見せたいためのトリック」と痛烈な批判を受けている。
- 1941年の国民学校令で「読解力」という言葉が早くも登場していて、戦後期との連続性がある。ただし、「読解力」の下位要素は議論されていなかった。
- 戦後すぐの学習指導要領試案、現代の僕から見ると理想主義的で胸が熱くなるのだけど、当時は冷めた受け止められ方もしていた(占領されていたことを考えれば、まあ当然なのだけど…)
- 戦後、教員が児童中心&経験主義に傾倒した理由の一つに、教科書を黒塗りにする経験からくる教科内容への不信や、それを教えることへの忌避感があったようだ。まあ、昨日まで教えてた内容を「間違いだった」と黒塗りするのって、相当なトラウマかも…。
- 1950年代前半を中心に、文法を体系的に教えるのではなく、日常の言語使用の中で文法規則を発見させ、使えるようにする機能文法のブームがあった。
- 1956年(昭和31年)の全国学習調査の読解問題の低正答率が問題となり、説明文ブームが起きた。これより段落指導が説明文読解の典型的な方法となる。
ね、面白いですよね。この辺のトピック…。
歴史研究を読む意味は、フォーク・セオリーを変容させること
最後に。この本でもう一つ面白かったのが、「明子さん」という児童と田中という教師の事例を引用した後で、筆者が次のように述べているところ。
もし、明子さんが2010年代後半の小学校に通う児童だとしたら、どうだっただろうか。年配教師や指導主事等は、田中同様、能力主義に立脚した説明を行うのではないだろうか。一方で、若手教師のなかには、学習科学に立脚した説明によって、相手/目的意識や既有知識の喚起、対話的な学習過程、学習活動後のリフレクションといった枠組みから語るかもしれない。授業研究会等の場で、双方の説明が出し合われ、議論され、教師たちそれぞれが、新たなフォーク・セオリーを形成する機会になるかもしれないのである。
ここでのフォーク・セオリーとは、学問的経験の裏付けを持たない、個人や特定集団の経験知から紡がれる理論のこと。この部分を読んだ時、この筆者の指摘と同じことが、僕たち自身にも言えるのだろうな、と思った。
僕たちはそれぞれのフォーク・セオリーを持っている。でも、その変容は必ずしも簡単ではない。例えば、今ならどの研究会に行ってもリフレクションという発想から無縁でいることは難しい。今の教育の世界では、リフレクションはそれ自体が良いもの、正しいものになってしまっていて、教育の世界の支配的なフォーク・セオリーになっているからだ。
元々が社会的存在である僕たちは、みんなが使うリフレクションという概念を取り入れることで、その仲間に入れてもらいたがる。そこでは、僕のフォーク・セオリーの変容は、その集団内で支配的なフォーク・セオリーへの同化という形でしかなされない可能性が大きい。
しかし、つい50年前に遡れば、リフレクションという用語を全く使わずに、目の前の子どもや学習に関する現象を説明するフォーク・セオリーが、確かにそこにあったのである。「もしも経験主義の実践家がここにいたら」「もしも1960年代のバリバリの実践家がここにいたら」…彼らは、僕たちの時代に支配的なフォーク・セオリーとは異なる言葉で、目の前の事実を語っていくだろう。そんな想定をすることで、僕たちのフォーク・セオリーも変容する可能性がある。
そこに、こういう歴史研究の本を現場教員が読むことの意義の一つがあるのではないだろうか。目の前の他者との対話よりも、歴史書の中にいる実践家との対話の方が、現実の人間関係のしがらみがないだけに、自由に変容する可能性は一層大きいように思える。
[ad#ad_inside]