以前、「子供たちの「書けなさ」とどう向き合うか?」というエントリを書いた。全国大学国語教育学会での永井ほのりさんの発表を受けたものだが、永井さんの発表資料の「書けなさを可能性としてとらえる」姿勢は、今あらためて読んでも、とても大事なものに思われる。
ところでこのエントリでは、次のように、たしかどこかで読んだ大村はまの言葉を記憶に頼って書いていた。今日は、これについてのエントリ。
[ad#ad_inside]たしか大村はまが語っていたように(ごめんなさい、これ国語教室のどこかにあったと思って探したけど見つからなかったです…)、中学生の書けなさを「頼もしい」と捉える姿勢。
大村はまがとらえる中学生のすがた
この引用箇所、その後に全集『大村はま国語教室』をひっくりかえしてもわからずじまいになっていたところ、「この本のこの箇所ではないか」というご指摘をTwitterでいただいた。その本は『大村はまの国語教室 ことばを豊かに』。刊行は40年前の1981年。なんと、野地潤家と倉澤栄吉が聞き手となって大村はまに国語教育の話をしてもらうという、国語教育研究のレジェンド鼎談の古本だった。
この表紙に記憶がないので、おそらく僕が読んだのはまた別の本かもしれないのだが、しかし、『大村はまの国語教室』にも、確かに彼女がとらえる中学生の「書けなさ」について書いてあった。
小学生の書けなさと、中学生の書けなさ
中学生なんかは一生の間で、いちばん作文の下手なときではないかと思っているのです。どうしてかと言いますと、生意気で、あまり深くものごとを考えないのに、軽率に何か言い散らすのが得意な時代ですね。そして、あまりものを深く考えることができないのです。ですけど、いろんなことを浅く知っているのです。そして、自分らしい考えなのか、それとも人の言ったことなのか、あまり区別のつかないときなのです。ことばをあまり知らないのですが、その知っている聞きかじったことばをめちゃめちゃに使ってみたいし、だいたい話がおおげさで、ちょっとしたことをおおげさに表現したり、言ったりするのが好きというわけです。そういうふうな、中学生特有の一つの時期を暮らしているわけです。(p177-178)
ここで、「一生の間で、いちばん作文の下手なとき」とする大村の中学生観が、とても興味深い。たしかに、と思わされることが多々ある。それは、小学生の「下手さ」とは違う。下記エントリにも書いたけど、小学生の「下手さ」とは、書く技術も内容もないまま、思いつきで無計画に書くがゆえの「下手さ」であり、一方でそれゆえの(あえてこう書くが)「蛮勇」という強みもある「下手さ」である。
それに対し、小学校高学年あたりから心身ともに変化を迎え、中学生になると、視野が広がり、社会に(他者に)目が向くようになる。自分を客観視することも、以前よりできるようになる。自立心も強くなる。少し大人っぽい文章にも触れ、新しい語彙にも出会う。目新しい考えや、これまでの権威であった大人たち(親や先生)の言葉を否定する意見に出会うと、とても喜び、真似もしたくなる。けれど、深く考えたり、自分をコントロールしたりなんて、多くの子にとってはまだまだだ。口ほどに手はうごかない。「生意気で、あまり深くものごとを考えないのに、軽率に何か言い散らすのが得意な時代」という大村の評言は、もっともだなと思う。背伸びが楽しく、深いところでは苦しい時期。それを大村は「成長したしるし」ととらえる。
小学生というのは、どんな内容が浅いことでも、それこそ、朝起き、顔洗い、ご飯を食べ式のことでも、得々として書いて、五枚書いたの、六枚書いたのと喜びますね。それはそれで、その時期はもうどんどん、どんどん書けさえすればいい時期ですから、結構だと思いますが、中学生になりますと、ばかばかしいと思うことは書かないわけなのです。こんなつまらないこと、だれが読んだってつまらないこと、こんなばかばかしいこと書いたってしようがない、こんなことを下手に書いたってしようがない、と思うのが中学生ですし、それは責めることでもなくて、成長したしるしだと思うのです。(p179)
深いこと、内容のあることを書きたいと(あさはかに)思ってしまう。どこかで読んだ格好良い言葉や文章を、よく理解しないままに使ってみたくなる。つまらないもの書くことへの抵抗が強まる。周囲からどんな文章を期待されているかをなんとなく察知し、それにあわせようとしたり、それでうまくいかなくなったりする。うまく合わせた時も、自分のものではないように思う。そうやって試行錯誤してなんとか書いたものを、勝手に親や周囲の人に公開されて傷つく。前よりもふかく考えられるようになっているけど、それを言い表す言葉を知らない….。中学生が抱える書けなさは、小学生の書けなさとはやはり違う。それは、大村の言う通り「成長したしるし」でもある。小学生の書けなさとは別の、しかし、中学生なりの可能性を持った「書けなさ」である。
作品ではなく、「書く力」を育てる
大村の中学生観は、大村の作文教育観をも導いていく。ふたたび、『大村はまの国語教室』から引用する。
ことばはおおげさで、心が浅くて、人生経験が乏しいとか、そんなかたが、いい文章を書くとは考えられない。いい文章を書かないと思う人の標本みたいなのが、中学生だと思いますので、書く力そのものをつけることはできますけれども、いい作品というのができないのはほんとではないかと、あるとき気がついたのです。
ですから、もう作品中心にいくということは大違い。よくコンクールなどにいい作品があって、それはそういうかたがあって結構ですけれど、みんなにそういうことを求めないので、筆不精ではなくて、何か書くことがあれば、書くのを面倒くさくもなく、なんとか、書ける、というようにして、書く力そのものをつけておいたら、その人が、これから思想も育ち、人間も育って、一個のちゃんとした人になった場合、その筆力を使って書いてくれればいいのではないかなと思ったのです。(p178)
最初に断っておくと、僕は、この大村の言葉に全て賛同しているわけではない。僕は「書くこと」を見つける事自体が「書く力そのもの」の大きな要素だと思っているし、大村の「良い文章は良い人格に宿る」的な文章観には古さも感じる(それはちょうど、大正時代から連綿と続く「詩の書き方は教えられない」という主張と相似形をなすようだ)。中学生には大人の基準と違う中学生なりの「良い作品」があるだろうとも思う。
ただ、大村が、「いちばん作文の下手なとき」という中学生観から出発して、だから「作品中心にいくということは大違い」という結論にたどり着いたことには、やはり彼女の洞察の深さを感じる。「作文の質を求めない」と宣言することは、今でも勇気のいることだ。
そういう僕自身も、かつては「良い作品を書かせるのではなく、良い書き手を育てる」という言葉の意味がよくわかっていなかった(下記エントリ参照)。
いま、ライティング・ワークショップをはじめて何年もかかってやっと自分なりにその意味を構築しつつあるのだが、大村はまは、40年前の本でずっと先を行っていた、というわけだ。偉大な先達である。
その年代の子たちの姿を理解する大切さ
永井ほのりさんの資料や大村の言葉に触れてあらためて思うのは、その年代の子たちの抱える課題を、子どもたちの視線で理解することの大切さだ。子どもには、子どもの世界があり、論理がある。ナンシー・アトウェルの「私たちが教える論理が、子どもたちが学ぶ論理と同じとは限らない」を思い出す(正確には、彼女が出会ったグレンダ・ビセックスの言葉である)。
ああ、そうだ。これは、赤木和重さんの『「気になる子」と言わない保育』の姿勢、そして、奥村高明『子どもの絵の見方』と同じ姿勢ではないか。大人の目から見たときにちょっと肯定しにくい子どもの動き、子どもの絵、そして子どもの作文…その背景には、いずれもその子どもたちなりの「論理」「文脈」「必然性」がある。その当たり前のことを理解し、受け止めることが、まだまだ自分には足りていない。風越に来て、小さな子どもたちと関わるようになってから子どもに意識を向けつつあるけれど、まだまだだと思う。
子どもの「書けなさ」を「可能性」として捉える
そして、小学生や中学生の「作文の書けなさ」という、「なんとかすべき課題」となりがちなことを、どう肯定的に受け止め、活かしていくのか。肯定的に受け止め、活かすことの大切さは直感的にわかる。けれど「どう活かすか」というhowの部分になると、とたんにあやしい。もちろんこれはノウハウのある問いではないのだが、自分はこの「書けなさを尊重し、活かす」を意識しながら、同時に子どもたちの書く力を伸ばす国語科教員としての自分の役割(社会的要請)に応えていけるだろうか。書き手としての子どもたちの成長を長い目で見ながら、それぞれにあったことをする。言うのは簡単だが、それはなかなかにチャレンジングな職人仕事である。
[ad#ad_inside]







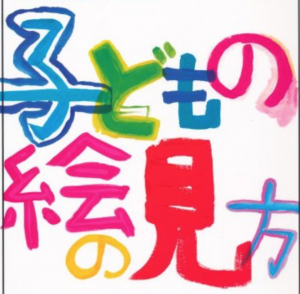









![[動画紹介] 哲学対話をもっと知りたい方に。哲学対話系再生リスト](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/02/スクリーンショット-2017-02-04-11.04.49-50x50.png)
