先週末、全国大学国語教育学会がありました。一週間経ってしまったけど、忘れたくないことをメモ。複数回に分けて更新します。
「書けなさ」と「ありのまま」の発表
今回、一番心に残ったのは、B会場の永井ほのりさん「中学生の『書けなさ』を可能性として捉える」という発表だった。中学生の「書けなさ」は、「書く技術が全くない」という意味での「書けなさ」とは異なり、「書こうとはしていても書けない」「書いてはいるが、書こうとするものと離れている」という指摘から始まったこの発表は、その「書けなさ」を思春期の子供たちの一つの価値として捉えて、では教師はどのような姿勢で彼らを見とるべきかという問題を、「言語の限界」を切り口として扱ったものだ。ご自身の被教育者としての経験がベースにあるせいか、聞いていて「ああ、本当にそうだよね」と共感できる問題意識だった。
また、同じB会場の金田唯人さん「『ありのまま』に書くことを強いられた学習者の戦略」は、「ありのままに書く」ことを求められた学習者の対応についての発表で、僕も特に小学校の中・高学年のころは「ありのまま」になんて書かない子だったので、非常に面白く、興味深く聞いた。
この2つの発表は、書くことの教室で子供達がどういう状況に置かれているのかという観点で、同じ問題を扱っている。子どもが「書けなさ」に直面する典型的な場面が、教師という空間で、教師に「ありのまま」に書くことを求められた時なのだ。真剣に「ありのまま」に向き合おうとして、それを「ありのまま」に表出できず苦しくなる子もいれば、かつての僕のように早々に「先生の期待する『ありのまま』フォーマット」を探して、自分の内面を深める手段としての「書くこと」を放棄してしまう子もいるだろう。後者のタイプの子は、書く技術は持っていても書き手としての自分に向き合おうとしない点で、「書けない」子なのだと言ってもいい。
「書けなさ」とどう向き合うか?
この「書けなさ」は年齢的な要因もあるし、一方で「ありのまま」をつい子供に期待してしまう僕たち教師や、同世代の人たちが多数集まっているという、「教室」という場がもたらすものもある。そんな難しさをはらむ書くことの教室で、僕たちはどうしたら良いのだろうか。
一番大きいのは、永井さんが述べられた通り、子どもの「書けなさ」をいったん価値として受け止めることなのだろう。「書けなさ」には色々ある。自分と向き合う苦しみからの「書けなさ」、自己開示を求められて教師の視線に合わせてしまう「書けなさ」、あるいは逆に「ありのまま」が文章として表出できない「書けなさ」、自分が読んでいるものと書いているもののギャップからくる「書けなさ」、周囲の子に比べて自分の書いた文章の価値が感じられないことからくる「書けなさ」….。
それらの「書けなさ」が、いずれも、まずは「より良い存在でありたい」というその子の願いから来るものとして受け止めること。たしか大村はまが語っていたように(ごめんなさい、これ国語教室のどこかにあったと思って探したけど見つからなかったです…)、中学生の書けなさを「頼もしい」と捉える姿勢。実際の文章の質を向上させることより前に、僕たちはこの視点を持って書くことの授業をする必要がありそうだ。
思えば、「教師も必ず書く」「ペンネームでもいい」「自分の書いた文章を自己評価する」などのライティング・ワークショップの手法は、教室における生徒の「書けなさ」への苦痛を和らげ、また自分の「書けなさ」と向き合うための手段ともなっている。また、僕も生徒も「物語を書く(僕の場合は授業で書かせる)」ことを好むけれど、「物語」=フィクションという形式も、「ありのまま」を回避することで語りやすくする一つの助けになる。同じライティング・ワークショップでも、そういう意識を持っているのといないのとでは、大きな違いがありそうだ。
まずは、「書けなさ」を価値として認めること。そして、余計なハードルを減らすことで、生徒が「書くこと」や自分の「書けなさ」と向き合えるようにすること。そのためにどんな工夫が実際にできるのかということ。書くことの教室を作る上で、大切な問題が取り扱われていた、お二人の発表だった。
[ad#ad_inside]



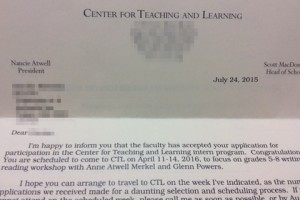





![[読書]「読書とひきかえに何も求めない」は可能か?ダニエル・ペナック『ペナック先生の愉快な読書法』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2022/04/e23e738e73e713da7befb5e0cc1f0f9e-50x50.png)