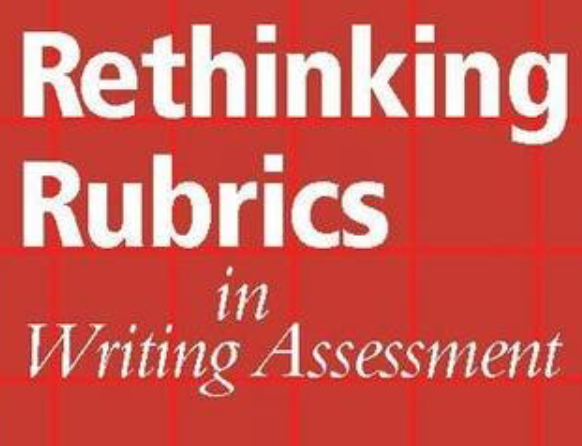過去にこのブログで何度か書いているが、現時点での僕は作文教育でのルーブリックの利用に消極的だ。もともと僕が影響を受けたライティング・ワークショップの実践者には、ナンシー・アトウェルをはじめルーブリックの利用に消極的な人が多い。
しかし僕は近年のルーブリックをめぐる議論を追いかけていないので、そろそろルーブリック関連の本をきちんと勉強しないと、という気持ちもある。そこで、今回のエントリではその第一歩として、以前に読んだことのある作文教育におけるルーブリック批判の本Rethinking Rublics in Writing Assessmentを読み直して、まとめてみた。ここから出発してルーブリックについての本を何冊か読んでみようと思う。
[ad#ad_inside]ルーブリックが嫌がられる理由
なぜアトウェルはルーブリックの利用に消極的なのだろう。僕の推測をひと言で言うと、「本物の読者も作者もそんなものは使わないから」である。そもそも、1970-80年代のアメリカで広まったプロセス・アプローチは「本物の書く体験を教室の中に持ち込む」運動なのだ。だから、実際の読み書きの場面で使われないルーブリックをわざわざ教室で使うことには批判的なのだと思う。
ルーブリックへの違和感から生まれた本
そして、ルーブリックへの批判論として僕が4年前に読んだのが、Maja WilsonのRethinking Rublics in Writing Assessment。これは、2000年代のアメリカでルーブリックの利用が当然視されていた状況への批判として書かれたものだ(刊行は2006年)。高校英語教師であるウィルソン自身がルーブリックを使ったときに、「自分が良いと思う作品でもルーブリックだと点数が低くなる」点に違和感を抱え、それが執筆のきっかけとなったらしい。
ルーブリックの歴史
彼女はまずこの本の中で、英語圏の小論文試験の歴史をたどり、そこでルーブリックが利用されるようになる過程を描く。ここがコンパクトながら読み応えがある。彼女によれば、かつては特権階級だけのものだった閉じた大学が、女性を含む一般市民に開かれるにつれ、「公平で信頼できる」入試の基準が要求されるようになる。こうして生まれたのが選択式テストや論述試験のルーブリック利用なのだ。ルーブリックは、もともとアセスメント(教育のための評価)よりはランク付け・グレード付けの必要から生まれてきたという点は、忘れてはいけないポイントに思う。
ウィルソンのルーブリック批判
この本の中で、ウィルソンがルーブリックを批判する根拠は、次のようなものである。
- 実際の読者はルーブリックを使って読まない(プロセス・アプローチの実践者と同じ理由)
- ライティングは、項目の足し算ではない。もっと複雑。
- 項目から漏れるものがあるし、かといって項目を増やすと使えないものになる
- 生徒たちにとって意味のあるフィードバックにならない
- 標準化された書き手を作り出すだけ
彼女は、ルーブリックが表面的なエラーの修正や教師の時間節約に有効なことは認めるのだが、ライティングの教師の仕事はあくまでみんなを伸ばすことであって、ルーブリックではそれはできないと考えているのだ。
教育と評価方法の理論的ずれ
加えて、ウィルソンが強調するのは、教育とその評価の理論的前提がずれてはいけないということ。現代のアメリカでは書くという営みのプロセスを指導する意識が少なからずあるが、こうした実践の背景にある構成主義的な世界観と、ルーブリックに代表される実証的な世界観の間にはずれがあるというのだ。
ウィルソンのルーブリック批判の中でも、このパラダイムのずれはもっともクリティカルな批判であるはずだ。僕がきちんと理解するには、ルーブリックの背景にある理論的前提が何なのかを勉強しないといけない。
主観的な、多様なフィードバックを
この本でウィルソンがルーブリックに代わって提案し、また実例を紹介しているのは、「客観性」を追求しないフィードバックのあり方である。ルーブリックの背後には集団思考につきものの「客観的な評価」「誰もが納得する評価」への欲望があるが、彼女によれば、対立をおそれてはいけないのだ。
むしろ十分な意味のある書く文脈を与えた上で、「異なる読者が、書くプロセスの途中で随時フィードバックをすることが書き手の成長につながる」という。地元の人、プロの書き手、教育系の大学生など、さまざまな人に評価者として関わってもらうことを提案している。
これについても、「いろいろな人が違うことを言うと生徒が混乱する」という向きが出てきそうだが、ライティングというのはそういうものだ、と僕は思う。誰もが一致して評価する文章などない。むしろ、複数の他者から異なるフィードバックを得て、どれをどのように取り入れるかを決める。その決断の積み重ねが、書き手としての自立につながっていく。作文のフィードバックは、客観的なものではなく、間主観的なものだ。その感覚は、いろいろな人から評価されながら徐々に身につけていくしかない。その際の混乱は、必要な混乱だと思う。
また、ウィルソンが紹介する事例では、作文のグレード付けもしていない。これはアトウェルの学校にも共通しているけれど、個々の作品にグレードをつけると、生徒はリスクをとりにくくなるからだということ。自分の学校では成績付けの必要から出来ていないけれど、僕はこれにも共感するところが大きい。
Meg J.Petersenによるレビュー
https://wac.colostate.edu/journal/vol20/petersen.pdf
欠けている「プロセスを支えるルーブリック」の視点
さて、Rethinking Rublics in Writing Assessmentを久しぶりにざっと眺め直すと、今読んでも共感できる部分が多くて、やはり自分はルーブリックが好きではないんだなと実感した(笑) 自分のルーブリックへの態度は、やっぱり今も消極派かな。
でも、ウィルソンの議論には欠けている点もある。ここでは、ルーブリックが完全に「成果物の質を測定するもの」として扱われていて、たとえば生徒が書くプロセスを支えるために自分でルーブリックを作る事例などはまるで考慮されていない。ここは、やはりちょっと議論が古い(2006年刊)からなのだろうか。今のルーブリックをめぐる議論はこの水準ではないのではと思うので、最近の議論も追いかけて、ルーブリックにもう少し向き合ってみようと思う。
ということで、識者のみなさま、「ルーブリックの議論ならこれを読め」というのを教えて下さいませ!
[ad#ad_inside]