作文教育にとって悩みの種はいつも「成績評価」(ここでは形成的評価ではなくいわゆる「評定」に話題を絞る)である。作品の質を重視するプロダクト・アプローチでも、どうその「質」を定義して測定可能なものにするかが問題になるが、プロセスを重視すれば「そもそもプロセスを評価するって一体何?監視でもするの?」という話になる。
2014年時点のアトウェルの作文の評価
ナンシー・アトウェルの評価の方法を見てみよう。まずは2014年、自分の学校を作ってそこで理想の評価を追求している彼女の評価方法のおさらい。
ざっくりまとめると、彼女の評価方法の柱はこんなところである。
・評価の中心を担うのは生徒の自己評価である
・生徒は、学期末の一週間を使ってポートフォリオを作る
・教師はそれを読んで詳細なコメントを書く(グレードはつけない)
・その後、生徒・教師・保護者の3者で面談が開かれる。
ここでの「グレードをつけない」というのはコメントを読んでもらうには有効なやり方なのだが(複数の研究で、評価のコメントにAやBなどのグレードをつけると、コメントだけの時より効果が落ちることが報告されている)、普通の学校に勤務している身としてはちょっと現実的ではない。では、彼女が自分の学校を作る前の、公立中学校勤務時代はどうだったのだろうか?
公立中時代の「評価カンファレンス」
初版p114-120によると、公立中学校時代(ここでは中学二年生)でも、アトウェルは各学期の最後の一週間を「評価ウィーク」に当てて、そこで生徒全員と「評価カンファレンス」を行っている。
「評価カンファレンス」の前半は生徒への4〜5つのインタビューだ。中でも「良い書き手になるために何をしたか?」「この学期で書いたもののうち、一番の作品はどれか?そしてそれはなぜか?」「次の学期の目標は何か? 書き手として何をしたいか」の3つは必ず聞く項目らしい。こうした質問項目は評価カンファレンスの一週間前にミニレッスンで掲示されて、どんなことを聞きたいのか、ちゃんと伝えるのだというから、生徒もそれなりに準備をしてくることが期待されているのだろう。
「評価カンファレンス」の後半では、来学期の目標が話し合われる。アトウェルは、その生徒が次に何が必要そうかということを授業中の観察から事前にメモしているが、実際に提示するのは1つかせいぜい2つだそうだ。というのも、生徒は前半のインタビューから自分で次のゴールを見つけ出すことを期待されているからである。
設定した目標に基づいたグレードづけ
この、評価カンファレンスで設定された次の学期の目標に基づいて、次の学期の成績はつけられる(つまり、成績の基準は生徒一人一人で異なる)。生徒が目標を完全に達成していれば「A」、事前の期待以上にやっていれば「B」、まずまずなら「C」という風に。そして、評価カンファレンスの最後には、前学期の目標に応じてこのグレードが生徒に告げられる、という仕組みだ。
あれ、じゃあ最初の学期はどうなるの? と言うと、生徒個々が目標を設定する余裕がないので、最初の一週間に次のような評価基準を配布し、これに基づいて成績をつけていたそうだ。
・題材を探したか
・その題材について情報を収集したか
・それらの情報を効果的に並べたか
・明確で整ったやり方でその情報を提示したか
・スペルや構文などの習慣を守ったか
・書くことにたくさんの時間や努力を注いだか
・リスクをとって、主体的に書いたか
・準備は十分だったか
プロセス・アプローチにおけるグレードづけの難しさ
しかし、こうしたやり方をみても、やはりプロセス・アプローチと「成績をつける」ことの相性は悪いなあと思う。僕はアトウェルのこのやり方が生徒の力を伸ばすだろうという見通しは持てるのだが、一方で「グレード」という形で生徒が序列化されることがセットになると、
|
「書く力はあってもその学期の目標を達成できなかった生徒がCになり、書く力があまりないけど頑張った生徒がAになる」ことに、生徒から不満が出るのではないか
生徒はAをとるためにわざと「達成容易な目標」を事前に用意するのではないか |
ということが頭をよぎる。だから、例えば推薦入試などで評定平均が生徒にとって重要な時は、こうした方法は現実的に取れないだろう。結果としての「作文」だけ取り出して、ルーブリックを使って要素に分割して「納得できる」評価と共にグレードを書いた方が、はるかに「安全」である。
いずれにせよ1987年の初版では、p120-121で他の実践者による別の成績のつけかたも紹介されているから、この当時のアトウェルもまだ試行錯誤中だったのだろうなということがうかがえる。この後で自分の学校を作った彼女は、文章による評価だけでグレードをつけないようになった。もしグレードをつけなくてもいいのなら、書き手としての成長を見るにはそれが一番良いのだろう。





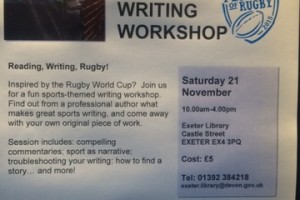







![[資料] これは便利、学習指導要領(案)の新旧対照表](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/03/スクリーンショット-2017-03-13-18.13.02-50x50.png)
