10月の大村はま国語教育の会で、桑原隆先生が大村はまの「旅の絵本」実践を取り上げていたので、改めて『大村はま国語教室』で読み直していました。今日はそのメモのエントリです。
中学生はどういう年齢か?
この授業、まず驚いたのは、安野光雅「旅の絵本」が刊行されて半年も経たないうちの実践だったこと。常に新しい素材で単元を構想した彼女ならではです。そして、『大村はま国語教室第6巻』では、大村が中学生という年齢について書いている箇所に、なるほどと思わされました。
小学生というのは、どんな内容が浅いことでも、それこそ、朝起き、顔を洗い、ご飯を食べ式のことでも得々として書いて、五枚書いたの、六枚書いたのと喜びますね。それはそれで、その時期はもうどんどん、どんどん書けさえすればいい時期ですから、結構だと思いますが、中学生になりますと、ばかばかしいと思うことは書かないわけなのです。こんなつまらないこと、だれが読んだってつまらないこと、こんなばかばかしいこと書いたってしょうがない、こんなことを下手に書いたってしょうがない、と思うのが中学生ですし、それは責めることでもなくて、成長した印だと思うのです。(8ページ)
確かに、質への欲求が高まると同時に「こんなつまらないことを書いても…」という思いが出てくるのは自然なことです。それを「成長した印」と認めつつ、ではどうするか?というところで、大村は「題材は教員が与える」という選択肢を選ぶんですね。かと言って、「これこれについて書きなさい」という指示ではなく、「ヒント」という形で。大村はまは、「旅の絵本」を素材に、ヒントを散りばめて、子供達に書く価値のある題材をつかませようとします。
細かなヒントで生徒のアイデアを導く
この「ヒント」が本当に細かい…。「旅日記」「旅だよりその日その日」「子どもに語る」「人生断片(訪問/労働/誕生というふうに捉えて)」「ここにも人の生活が」(働く、笑う、走る…というように動詞で捉えて)「吹き出しをつける」「ここに人間がいる、と始まる詩」「ぼくは馬に乗って人生を探しに行った」から始まる創作、「もし加えるなら、私はこの1ページを」などなど…。これだけ多くの切り口を一人で見つけられること自体が彼女の実力の証とも言える、素晴らしいものでした。これなら、アイデアが浮かばない生徒も、この中から選んで書くことができるでしょう。
「教えないことこそ良いこと」という考え方も人によってはあるかもしれませんが、これだけの手だけを講じるからこそ、どんな子も書くことに一歩踏み出せる。彼女は、こうも書いていました。
…ことに創作の場合、何か与えられたらその先へつづけて書くということは、その子の思いつきではないので創作とは申しませんが、創作力をつける作業としてはできるだろうと思ったのです。
創作力をつける授業は、必ずしもゼロから創作することとイコールではない。大切な視点だと思いました。
こちらも充実した「あとがきの手引き」
なお、大村はこの実践で生徒に「あとがき」を書かせる時にも「手引き」を配っている。その手引きも細かくて、
- 色々迷ったけれども…
- うまくいかなくて、たいへんだった。
- へたでも、一生懸命にやったのだから…
のような文例にわざわざバツをつけて、こうした後書きのどこがいけないか、どう書くといいかを述べています(p116-117)。でもそれ以上に、後書きの手引きの最後に書いてある、
六、全体として、自分の作品を大切にする、かわいがるような気持ちで書きなさい。
の一行は、いいなあと思いました。そう、あとがきで一番大事なのは、そのことですよね。
創作を支える、「手引き」の細かさ
大村はまの手引きの細かさは、ナンシー・アトウェルの準備の丁寧さを彷彿とさせるものです。「こんなに細かい手引きは押しつけだ」「もっと子どもの中から生まれるものを大事に」と感じる人もいるかもしれません。でも、こうやって細かな手引きによって質を担保するからこそ、質を意識して書けなくなる時期の子どもたちを支えることができるのでしょう。もちろんそれ以前に、一人一人の生徒のことを想像しながら、こんな細かい手引きを書けること自体が素晴らしい。「創作ではとにかく自由にさせるのが良い」というナイーブな姿勢を問い直す力が、大村はまの実践には確かにある。イキイキとした創作を、細かな手引きが支えている。改めてそう思う、大村はまの実践でした。





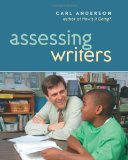


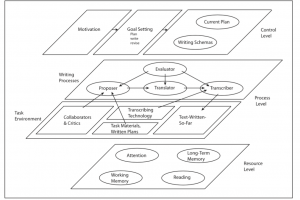
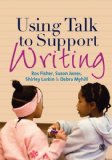
![[読書] ほとばしる前向きパワー! 市川拓司「僕が発達障害だからできたこと」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/07/スクリーンショット-2017-07-18-22.42.37-50x50.png)

