年末年始は読書教育の本を何冊か読んだので、勉強用のエントリ。国語の授業時間に読む文章と日常の読書が結びついていない印象を持つ人は少なくないと思う。学校では、教科書や国語教師が選んだ「読むべき価値のある」短い文章を、何時間もかけて「読解」する。一方で、日常の「読書」はそんなに時間をかけることはめったにしない。どちらも「読むこと」なのに、国語の授業の「読解」と日常の「読書」は別物のようだ。どうしてこうなったのだろう?
当たり前ではない?「読解」と「読書」の区別
まず確認しておくと、この「読解」と「読書」はどちらも英語でreadingである。精読を意味するclose readingという言い方もあるのだが、基本的には英語では読解と読書を区別しない。授業で一冊の本を読むこともままある。リーディング・ワークショップもそんな授業のひとつだ。
また、個人的な経験を言えば、昨年子供たちが通ったイギリスの現地公立小学校でも、何時間もかけて一つの短い文章を全員で読む授業が一切なく、驚いた。
つまり、一つの短いテクストを何時間もかけて「読解」する授業は、決してそれが「どこでも当たり前」のものではない。
注目は昭和30年代の学習指導要領の改訂
この問題については、足立幸子さんの論文が大変参考になるので、その内容を紹介したい。
足立幸子(2015)「国語科学習指導要領における読書指導の位置付けと課題」
http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/handle/10191/35856
この論文では戦後の学習指導要領で読書指導がどのように扱われたのか、その変遷を追っているのだが、注目すべきは1958(昭和33)年の学習指導要領改訂である。
1958(昭和33)年の学習指導要領は系統性重視になったことで知られる学習指導要領だ。書くことの教育でも「創作」が大幅に後退し言語技術が重視された(下記エントリ参照)。
そしてこの時、読むことの教育でも、国語科の「目標」として初めて「読解」という言葉が登場する。
中学校学習指導要領 第2章 各教科:国語科
https://www.nier.go.jp/guideline/s33j/chap2-1.htm
経験を広め,知識を求め,教養を高めるために,話を確実に聞き取り,文章を正確に読解し,あわせてこれらを鑑賞する態度や技能を身につけさせる。
また、各学年の「読むこと」についての目標も、以下のように前後半に分かれて記述される。足立さんの分析によると、前半(「〜とともに」まで)が「読解」に相当し、後半が「読書」に相当する内容である。
- 読むことの基礎的な技能を身につけさせるとともに,読み物に親しむ態度を養う。(中1)
- 読むことの技能をいっそう高めるとともに,必要なものを選んで正確に読む態度を養う。(中2)
- 目的や形態に応じて読むことの技能を確かにさせるとともに,考えながら読む態度や読書の習慣を身につけさせる。(中3)
ちなみにこれを、約10年前の戦後すぐ1947(昭和22)年の学習指導要領(試案)と比べてみよう。1947年版では、国語科学習指導の目標のうち、読むことに関する部分が、
知識を求めるため,娯楽のため,豊かな文学を味わうためというような,いろいろなばあいに応ずる読書のしかたを,身につけようとする要求と能力とを発達させること。
と、「読書」という言葉で説明されている。少なくともこの段階では、「読書のしかた」は「読みかた」とほぼ同義であり、「読書」と「読解」は未分化である。昭和30年代の改訂で、この二つが分かれていくのである。その背景には、「技能」をしっかり教えるべきという姿勢が見える。
教室から追いやられる「読書指導」
こうした「読解」と「読書」の分化は、一体何をもたらしたのだろう。国語教育の大家である倉澤栄吉は、『情報化社会における読解読書指導』で次のように述べる。
読解の文字は,戦前からも使われていた。しかし,今日のごとく一般化した意味で用いられ普及したのは,昭和三十年以降である。それは,従来の読みの指導が一種の心情主義に陥ったり,不正確な曖昧な読みをゆるしていたりしたのではないかという反省に基づいている。読みは生活に根ざしたものであるが,学校で教えるべきことは,生活の基礎になるべき力である。だから,生活に根ざした読みを認めながらも,学校では,文字・文章と正しく対面して,その意味をただしくかつ十分に理解すべきであるというのは,当然の考えである。かくして,学校における読みは二つに分化した。(p.360)
「文字・文章と正しく対面して,その意味をただしくかつ十分に理解」するために、「読解」は「読書」から分かれていった。倉澤のこの説明自体には、両者の分化に対して否定的なトーンは感じられない。
しかし、学校教育における「読み」の、「読解」(=正しい読み)と「読書」(=生活に根ざした読み)への分化は、「両者を対立的に捉え、二者択一的にする考え方」(倉澤, p361)という弊害を生んだようだ。それが結果的に、「読解」の絶対視と「読書」の教室からの疎外をもたらしたのではないかという見方もある。
『読書教育実践史研究』を著した増田信一は、昭和30年代を振り返って次のように述べている。
確かに、昭和30年代の読解主義を絶対視する国語教育観は、いろいろなヒズミをもたらした。読書指導を邪魔者扱いする風潮が強かったから、読書指導を積極的に推進するのには、勇気が必要だったのである。(p.183)
こういう風潮の中、国語の授業から読書指導が疎外されていったのではないか。国語の授業から追い出されただけでなく、学校図書館がカリキュラム上にきちんと位置付けられない状況が長く続いたことから、時間割からも疎外されてしまった。
つまり、教室では国語教師が「読解」の技術を丁寧に教え、読書は生徒が教室の外で個別に行う私的なもの、ということになったのである。学校の国語の先生は、「本を読め」と言うことや課題図書を課すことはあっても、授業中に実際に本を読む時間を取ることはない。授業中は、先生が選んだ文章や教科書の文章を、全員で「読解」する。そんなスタイルが「当たり前」になっていったのである。
今も続く?「読解」と「読書」の二分法
あくまで個人的な感覚だが、こうした状況は、今も基本的には変わっていないのではと思う。小学校の図書の時間や、一部の中学校で行われている朝の読書運動を例外として、学校で「本を読む」時間はあまりない。授業は、教科書や先生の用意した短い文章を精読することが中心になる。
もっとも、2000年代以降、ブックトーク、ビブリオバトル、ポップづくりなど、読書を通じた交流の授業は近年増えてきた。しかし、それですら、授業中に行うのは「読書の結果としての交流活動」であって、実際に本を読むのはあくまで授業外であることは少なくない。
「読解/読書」の二分法に基づいて、「授業では読解を」とする姿勢は、今でも大きくは変わっていないように思える。この二分法、いつまで続くのだろうか。そして、それには、どんな功と罪があるのだろうか。もう少し調べてみたいと思う。
[ad#ad_inside]







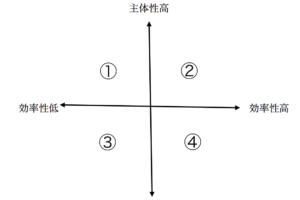






![[読書]現代の教育の問題点に納得。神代健彦『「生存競争(サバイバル)」教育への反抗』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2020/12/1dee47ed7278af8b6834c63c4d55c6fc-50x50.png)
![[読書]登山しない人にも読んでほしい、可能性にあふれた若き登山家の散文集。2024年9月の読書。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2023/12/a-book-6213537_1280-50x50.jpg)
そんなに日が浅い(戦後だった)のか、読解指導重視!と驚きです。読書指導を勧めるには勇気が要るにも共感です。意味ある読解指導、読書につながっていく見通しのある読解指導がしたくて、模索中です。
ありがとうございます。勇気、いるんですよね。高校だと特に…。