最近、ある仕事の関係で「評価」についての本を数冊読んでいる。評価の中でも総括的評価や評定は僕の仕事のもっともいい加減な部分であり、まさにゼロから読んでたんだけど、その中で一番面白かったのがこの本、関田一彦・渡辺貴裕・仲道雅輝『教育評価との付き合い方』である。学習指導要領を踏まえて評価の方法を解説してくれる良書は他にもあるが、この本はタイトル通り、教師が「教育評価との付き合い方」を考える本という意味で、とてもユニークな存在だからだ。
[ad#ad_inside]「評価の仕方」ではなく、「評価との付き合い方」を
まず大事なのは、本書は「評価の仕方」がわかるためだけの本ではないということだ。例えば、学習指導要領の三観点を踏まえて、指導と評価の一体化を狙った授業をどう設計すべきか、みたいなことを知りたければ、石井英真・鈴木秀幸(編)『ヤマ場をおさえる学習評価 深い学びを促す指導と評価の一体化入門』シリーズの方がずっと良さそうだ。僕は小学校編しか読んでないが、大変良い本で、指導要領が想定している理想的な授業設計の理屈がよくわかった。国立教育政策研究所(国研)が出している例の「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」(小学校国語・中学校国語)と併読することをお勧めする。
一方、本書(関田・渡辺・仲道)は、そういう「ねばならぬ」系の「やり方」本を一旦傍に置きながら、「とはいえさあ…」「そもそもテストって…」と同僚と喋りたくなるような、そんな本だ。まず「テスト」「真正の評価(パフォーマンス評価)」という代表的な評価方法を取り上げ、それぞれのやり方を説明しつつ、その限界を論じている。「これからの時代では逆向き設計に基づいたパフォーマンス評価が求められるので、それをやりましょう」というスタンスでないのが良い。「教師にとって大事なのは、目の前の子が伸びることです。自分の力で伸びていく可能性を広げることです」(p4)という願いに基づき、「評価から指導にどうつなげるのか」(p130)という問題意識で書いているので、「評価のやり方」を超えて、「この評価は目の前の子にどう影響するんだっけ?」と一歩立ち止まって考えられる構成なのだ。
「逆向き設計の限界」の項目が印象的
個人的に一番印象的だったのは、「逆向き設計の限界」を述べる節で、ちくまプリマー新書の内田樹『先生はえらい』を引用しつつ、次のように述べているところ。
しかし、本来、学習というのはそれ(=目指すべき状態が事前に見通せること, 引用者注)にとどまるものではない。むしろ、学習後の姿を本人が事前に見通せないような学習、存在の仕方の変容を伴うような学習のほうが根源的なものであるだろう。内田(2005)は、本来的な学習とは、学習者の側が「自分がどのような知識、どのような技術を欠いているのかをあらかじめ知っている」という前提に立つようなものではなく、「自分がその師から何を学ぶのかを、師事する以前には言うことができない」ものだとしている。事後になって初めて自分が何を学んだかを意識できるのである。
芸術系の学習においてはこれが現れやすい。合唱であれ描画であれ、学習者は、教師から指導を受けながら、以前には気にもとめなかったような微細な差異を感じ分けられるようになり、何が善きものなのか、何を目指すべきなのかという感覚そのものを学んでいく。…..
そのため、学習を目標と評価基準を学習者自身が把握してその達成を目指すものとして捉えてしまうと、本人が予測可能な範囲内での漸次的変化へと学習の可能性が狭められてしまう危険がある。(p41-42)
この話は、最近の作文の課題設計で考えることと近いので印象的だった。例えば、先に挙げた『ヤマ場をおさえる学習評価・小学校編』でも、ちょうど国語の作文教育の優れた事例が紹介されているのだが(p58-61, ちなみに著者は筑波大附属小の青山由紀先生)、個人的にはどうしても「一本道」感が気になるのだ。
僕自身は、こちらの手渡したいもの・触れて欲しいものも持って授業の大枠を設計しつつ、その中で子どもがそれぞれに自分で新しい挑戦に出会って学んでいける作文課題を理想としているので(理想はプレーパークだということは以下のエントリで書いた)、本書の指摘は逆向き設計の違和感を言語化してくれたと思う。
「評価の本」としては異色だが…
なお、内田樹『先生はえらい』が引用されるのも、評価の本としては異色だが、本書では他にも「ジョハリの窓」「コーチング」「認知カウンセリング」など、よくある評価の本ではお目にかからない事項が出てくるのも特徴的だ。異色と行ってもいい。でも、評定をつける上で必要な「正しい評価のやり方」はさておいて、「目の前の子が、自分の力で伸びていく可能性を広げる」ために、評価とどう付き合うかを考えるという、本書のコンセプトがよく表れている、とても真っ当な箇所なのである。
他にも「テストは『公平』で『正確』であるべきなのか?」や「評価に『リアルさ』は必要か?」という問いに考えを巡らせる「論談」コーナーも非常に面白く、「だからどうすればいいのか」はちっとも教えてくれないのだが、それを自然と考えたくなる。また、評価と付き合う上では、これまでの日本の教育評価史を概観する章が最後にあるのも素晴らしい。
読んでいると、「評価、どうしよう?」と考えたくなる本。全体で130ページほどの薄い本。この薄さだったら職場で読書会もできるかもしれない。やってみたら面白いだろうな。
[ad#ad_inside]
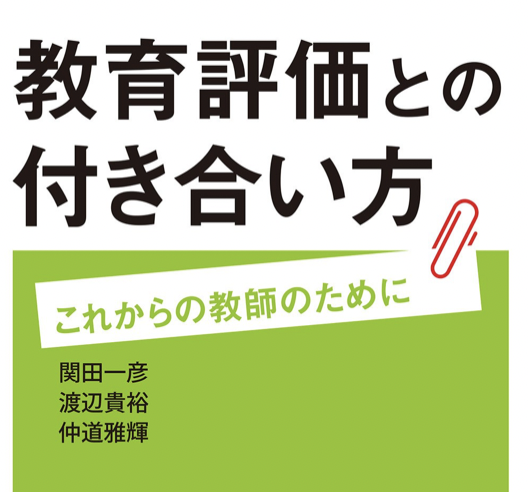



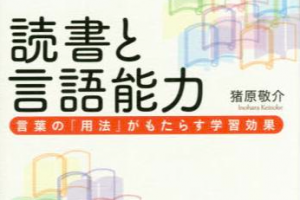





![[読書] ジジと灰色の男たちがいとおしい。ミヒャエル・エンデ「モモ」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/04/キャプチャ-50x50.png)


「逆向き設計への違和感」のお話、考えさせられました。11月20日ごろの先生のツイートもこの問題と関わりがあるものとして読みました。
自分の授業の評価では、「逆向き設計」をそこまで意識しているつもりではなかったのですが、学期や学年の初めに総括評価のルーブリックを示して、「この目標を達成できるように読み書きしていきましょう」と生徒にも話し、その目標を生徒が達成して(よい成績が取れるように)ミニレッスンを準備して、授業をしていきます。これって完全に逆向き設計ですね笑。
前任校のRWの実践でも、アトウェルに私淑してやっていたつもりがいつの間にかメタ認知やスキルを重視して教えてしまっていて、これはいかんぞと思って現任校でのWW RWを始めたのですが、だんだん現任校でもメタ認知とスキル重視なってきてしまいました。これ、総括評価としてのルーブリック評価(≒逆向き設計)がそうさせるんですね。数字で評定を出さないといけないこともあり、ルーブリック評価をするわけですが(そういう消極的な理由だけでなく、ルーブリックで事前に目標を示すのが生徒に主体性を育むという積極的な理由づけもありますが)、それによって、生徒の読み書きを多角的かつ詳細に評価することができていないという問題や、生徒が書きたいものが書けない、自分の目標よりこちらがルーブリックで指示する目標を優先せざるを得ないという問題(それによって結果的に書けないという問題も)が起きていると思います。
あと、人数の問題も大きいなと思います。今私だと、時間割の中の授業で3種類(3学年)、約200人の生徒を見ているのですが(そのうちWW RWが約70人)、記録をつけていても生徒一人一人の読み書きをなかなか把握できません。そうすると、逆向き設計的に、これは結局ほぼイコール一斉授業的にと言えるなと今思いましたが、生徒の目標をコントロールせざるを得ない状態にもなっています。
この辺りのことをどう考えるかは、教育方法の問題というより、教育観、あるいはそれを超えて人生観の問題なのかもしれません。
取り止めのないコメントを書いてしまいましたが、落とし所としては、WW RWの実践として、生徒の書き物や読み物が限定されたり、読んだり書いたりしにくくなってしまっている問題は解決しないといけないなと思います。改めて考えさせられました。
吉田さん、ありがとうございます(コメント確認が遅れてすみません)! 逆向き設計の良いところも、書かれている通りにたくさんあるわけですし、教育がそもそも働きかける側の意図に基づく以上、そうなるのは自然なことだとも思います。まして、200人を見ている状態では…。僕自身、実は、作家の時間/読書家の時間では頑としてルーブリックを使わないのですが、国語に比べたら大してこだわりもなく、他のスタッフとの共同が必要なテーマプロジェクトでは、子どもにルーブリックを示して、なかなかいいもんだなと思いました(笑)
月刊国語教育研究の次の2月号くらいに載る予定なのですが、逆向き設計については、目標を先に示すとそこからの落差として子どもたちを見てしまう(いろんな目標に進みうる可能性に自分が気づかなくなる)のがしんどいなと思うところです。これは、自分の見取りの技術の問題なのですね。「この子は目標に向かっててなんとかなりそう、この子は…」みたいに見ちゃうんですよね。この弊害は大きいなあと。