作家の時間(ライティング・ワークショップ)と読書家の時間(リーディング・ワークショップ)の実践仲間である冨田明広さん(トミー)を誘って、1時間半ほどの『国語の未来は「本づくり」』のミニ読書会をした。冨田さんは、『読書家の時間』執筆メンバーでもあり、その後、『社会科ワークショップ』も刊行。ワークショップという形式に可能性を感じている人だ。その冨田さんとの1時間半ほどのおしゃべりを通じて考えたことをメモしておきたい。
[ad#ad_inside]social agencyの土壌となる「承認」
今回の読書会は、本書p46に書かれている「社会主体性」(social agency)をネタに話が進んだ。本書は、ワークショップのもっとも大切な特徴に、読み書きの活動を社会的主体性(social agency)のためと位置づけている点を挙げている(p58)。そしてその姿勢は、冨田さんが「ワークショップ」という形式の良さを、「子ども一人ひとり多様な関わりができ、お互いを承認できる、その土壌を提供する」点に認めているのと共通しているのだ(下記エントリ参照)。というのも、自分が(自分自身に/他者に)承認されることが、その人が「自分の活動によって社会に良い変化を起こせるという信念」=社会主体性を持つ土壌となるからである。
教室は自信のゼロサムゲームの場
ところが(と、ここから話は本書の内容を外れていく)、実際の教室では、社会主体性の土壌となる「承認」を、全員に与えることが難しい。一部の子だけが承認され、自信を得て、社会主体性を発揮することになりがちだ。なぜか。それは、教室ではこの「承認」が、他者との比較にもとづいた「優劣」によってなされがちだからである。冨田さんの言葉を借りれば、教室は自信の「ゼロサムゲーム」の場である。ある子が優劣の「優」の立場を得て自信を得ると同時に、他の子は「劣」の立場に置かれて自信を失っていくのだ。
多元性を保証する場としての「ワークショップ」
冨田さんは、その「ゼロサムゲーム」打開の可能性を「ワークショップ」に見る。ワークショップは、「唯一のものさし」に子どもを乗せない。ライティング・ワークショップ(作家の時間)では「書く題材」を指定しないし、リーディング・ワークショップ(読書家の時間)では「読む文章」を指定しない。ワークショップは、「多元性」、つまり様々な活躍や承認のありかたを保証する場なのである。
念のため書いておくと、こういう多元性を保証する活動は、もちろんワークショップの専売特許ではない。教室の中に複数の尺度を意識的に持ち込むことで一本のレールの上での「優劣」で子どもを測れなくする試みは、子どもが様々な単元を同時に学ぶ自由進度学習や、さらにそれを拡張した複数教科での自由進度学習(例えば、授業づくりネットワークの『個別最適な学び』号で紹介された、竹内淑子さんや高橋尚幸さんの実践)でも実践されている。さらには、中核となる材に子どもが多様な関心・能力から関わる設計の生活総合も同じ枠組みだろう。
「作家の時間」「読書家の時間」の中で、どう多元性を保証するか?
ただ、こういう複数教科の自由進度学習や生活総合にあまり興味はない自分でも、ライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップで、同じことはできる。もともと通常の国語授業よりもずっと多元性を保証しているこの実践だが、さらにそれを拡張することだってできる。例えば、一回に書くジャンルの指定をやめれば、ジャンル指定のライティング・ワークショップよりも尺度はぐっと多元的になる。さらに一歩進んで、通常の国語で扱う文章とは異なる文章、例えば数学のレポートや音楽のレビューを書くこともできる。ゲームの攻略本を書くこともできる。リーディング・ワークショップの中で、数学や化学の本を読むこともできる。どんな教科内容でも日本語で書かれてさえいれば、ライティング&リーディング・ワークショップの対象にできてしまうのが、この実践の沼のような魅力なのだ。「それって国語なんですか?」と聞かれたら、「日本語で書いてるんだから国語です」が成り立ってしまう。こういう自由さ・おおらかさ、大切にしたい。
ここで我が身をふりかえると、実は、前任校の筑駒時代の自分のほうが、こういう自由さやおおらかさを持っていたように思う。それは、彼らがもともと優秀な子揃いだったし、教員も自由にのびのびやれる校風だったから、安心して「楽しむこと」に重点を置けていたからなのだろう。ところが、学力的には決して高い子揃いではない風越に来て「力もちゃんとつけなきゃ」という思いが強まったばかりに、ジャンルを指定したりして、僕はかえって実践の足場を掘り崩していたのかもしれない。ちょっとそんなふうに反省した。
言うまでもなく、多元性を拡張すればするほど、こちらの指導は難しくなる。「今回はエッセイですよ」とジャンルを指定し、評価軸を定めるほうが、指導する側はずっと楽だ。できる子にとっては力がつきやすいのも事実。ただ、書くことにもともと傷ついている子は、そうやって評価軸を定めることで、一元的尺度に乗せられ、いっそう苦しくなっていくのである。
….というわけで、2022年度の自分の実践の目標の一つは、自分にとってパニック・ゾーンにならない程度に、ワークショップの多元性を拡張し、子どもがお互いに一元的尺度で比較できなくすることだ。指導はしにくくなるけれど、ライティング・ワークショップの経験を重ねたいまの自分なら、なんとか対応できるのでは、という気もする。単一の尺度での「できる」「できない」から、多元的な尺度での「あれもいいね」「自分ってけっこういけてるじゃん」へ。そこにチャレンジしてみたいな。….という発見までの話につきあってくれたトミー、どうもありがとう。
やってみたい!子どもと作家を同列に扱う工夫
最後に、他にも、この読書会から生まれた「やってみたいこと」を軽くメモ。本書の中で僕も冨田さんも「いいな」と思ったのが、子どもが気づいた「作家の技」を、気づいた子の名前とともに書いた模造紙だ(p30)。p97でも作家の書き出しの技が作家名とともにリストされているが、こんなふうに子どもの名前と作家の名前が同じように扱われているのがいい。これ、実在の作家の技と、子どもが使う作家の技と、それを発見した子どもが、全て同じ模造紙に書いたらもっといいだろうな。子どもの名前と実際の作家の名前が同じ紙の中に混在している感じ。こういうちょっとした取り扱いで、「自分も書き手だ」という主体意識が育っていくはず。こういう小さな、でも具体的な示唆をくれるこの本は、やはり良い本だと思う。冨田さんとこの本をめぐって話ができてよかった。またやりましょう。
[ad#ad_inside]




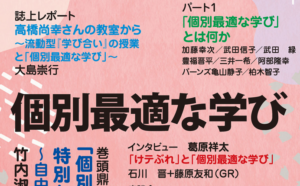


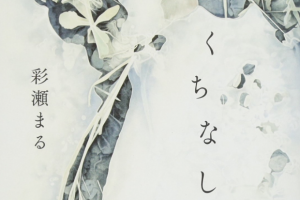






![[読書]服部真里子『行け広野へと』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/515sege7DWL._SL160_-50x50.jpg)
